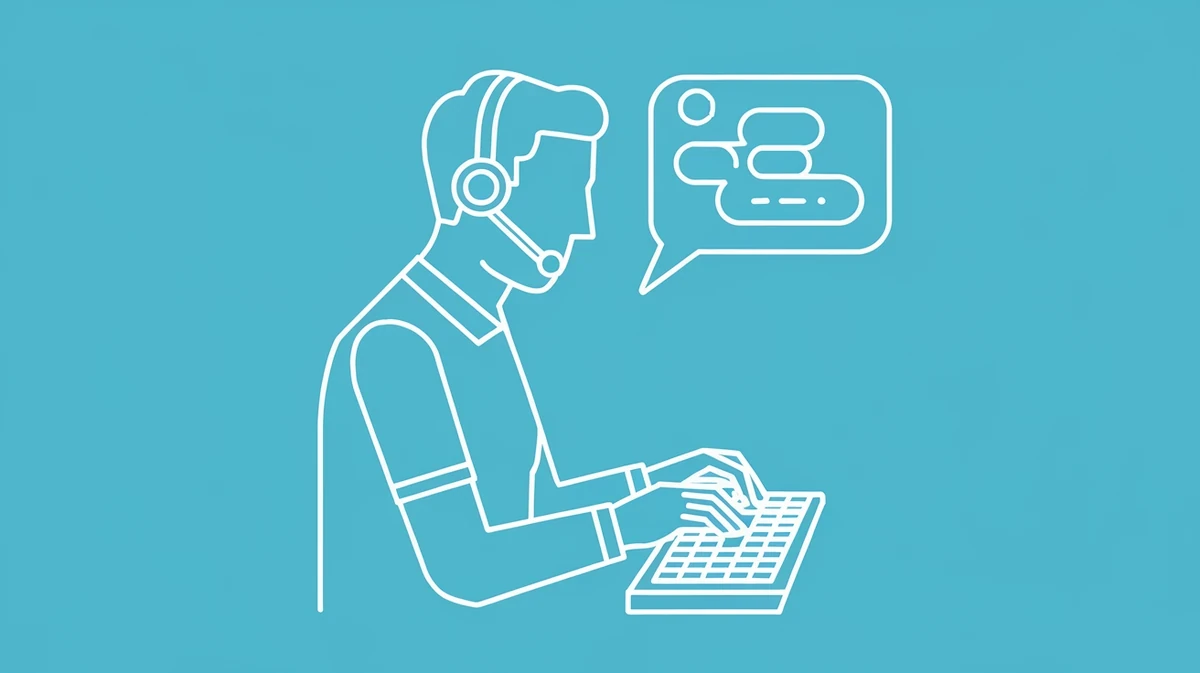【例文付き】丁寧かつ毅然と!クレーム対応メールの失敗しない書き方
丁寧かつ毅然としたクレーム対応メールの書き方

クレーム対応メールの作成って、本当に気が重い作業ですよね。
「どう書けば相手の気持ちを和らげられるだろう…」
「でも、会社の立場も守らないといけないし…」
なんて、板挟みになって悩んでいませんか?
実は私も、お客様からの厳しいご指摘メールにどう返信すべきか、頭を抱えた経験がたくさんあります。
丁寧すぎると弱気だと思われ、かといって強く出れば火に油を注ぐことになりかねません。
このバランス感覚が、クレーム対応メールの最も難しいところではないでしょうか。
今回は、そんなあなたの悩みに寄り添いながら、丁寧さを保ちつつも毅然とした態度で対応するための、クレーム対応メールの書き方について、具体的なポイントや例文を交えながらご紹介します。
この記事を読めば、クレーム対応メールへの苦手意識が少しでも和らぎ、自信を持って対応できるようになるでしょう。
クレーム対応メールの基本的な考え方

まず最初に、クレーム対応メールを作成する上での基本的な考え方を押さえておきましょう。
なぜ丁寧さと毅然さの両方が必要なのか、そして、クレームの裏にあるお客様の気持ちをどう理解すれば良いのか、一緒に見ていきましょう。
なぜ丁寧さと毅然さの両方が必要なのか?
クレーム対応において、「丁寧さ」と「毅然さ」は、どちらか一方だけでは不十分です。
丁寧さだけを重視してひたすら謝罪を繰り返していると、お客様によっては「非を認めた」と捉えられ、過度な要求につながる可能性があります。
また、企業の立場として、安易に全ての要求を受け入れるわけにはいかない場面も少なくありません。
一方で、毅然とした態度だけを前面に出してしまうと、お客様は「話を聞いてもらえない」「誠意がない」と感じ、さらに感情的になってしまう恐れがあります。
企業の信頼を大きく損なうことにもなりかねません。
だからこそ、お客様の気持ちに寄り添う「丁寧さ」と、事実に基づき、できないことはできないと伝える「毅然さ」、この二つのバランスが非常に重要なのです。
このバランスを保つことで、顧客満足度を維持・向上させつつ、企業としてのリスクを適切に管理することができます。
クレームの裏にある顧客の本当の気持ちを理解する
お客様がクレームを伝えるとき、その言葉の裏には様々な感情が隠れていることが多いです。
単に怒っているだけでなく、「期待していたのに裏切られた」という失望感、「このままだと損をするのではないか」という不安、「自分の状況を理解してほしい」という切実な思いなどが複雑に絡み合っています。
表面的な言葉だけに捉われず、なぜお客様がこのような気持ちになっているのか、その背景にある本当の気持ちを想像し、理解しようと努めることが大切です。
例えば、製品の不具合に対するクレームであれば、単に交換や返金を求めているだけでなく、「楽しみにしていたのに使えなくて残念だ」「急いでいたのに予定が狂って困った」といった感情があるのかもしれません。
その気持ちに寄り添い、共感を示すことで、お客様は「自分のことを理解してくれている」と感じ、冷静さを取り戻しやすくなります。
スピード対応の重要性とその理由
クレーム対応において、迅速な対応は非常に重要です。
お客様は、問題を抱えて不安や不満を感じている状態です。
対応が遅れれば遅れるほどその不満は増大し、「軽視されている」「誠意がない」と感じてしまう可能性が高まります。
もちろん、事実確認や原因究明には時間がかかる場合もあります。
しかし、まずは「ご連絡ありがとうございます。内容を確認し、改めてご連絡いたします」といった一次返信を迅速に行うだけでも、お客様の心証は大きく変わります。
「きちんと受け止めてくれている」という安心感を与えることができるのです。
特に日本では、ビジネスコミュニケーションにおいて返信の早さが重視される傾向があります。
迅速な対応は、問題解決への真摯な姿勢を示す上で不可欠と言えるでしょう。
クレーム対応で避けるべきNG行動
良かれと思ってした対応が、逆にお客様の怒りを増幅させてしまうこともあります。
以下のようなNG行動は避けましょう。
- 感情的な反論: お客様が感情的になっていても、こちらも感情的になって反論するのは絶対にNGです。火に油を注ぐだけです。
- 責任転嫁: 「それは〇〇部署の問題で」「以前の担当者が…」など、責任を他者に押し付けるような言い方は、お客様に不信感を与えます。
- 曖昧な回答や言い訳: 事実確認ができていない段階で憶測で話したり、言い訳に終始したりするのは避けましょう。誠実さに欠ける印象を与えます。
- 上から目線のアドバイス: お客様が求めているのはアドバイスではなく、問題の解決や共感です。一方的なアドバイスは反感を買う可能性があります。
- テンプレートの丸写し: 明らかに定型文だとわかるような、心のこもっていないメールは、お客様をさらに失望させます。
これらのNG行動を避け、常に誠実な姿勢で対応することを心がけましょう。
丁寧かつ毅然としたクレーム対応メールの構成要素

それでは、どのような要素を盛り込み、どのような点に注意すれば、丁寧かつ毅然とした印象を与えられるのでしょうか。
実際にクレーム対応メールを作成する際の、具体的な構成要素について見ていきましょう。
件名:一目で内容がわかるように具体的に
メールの件名は、お客様が最初に目にする部分であり、メールの重要度を判断する要素にもなります。
「お問い合わせありがとうございます」のような一般的な件名ではなく、何についての返信なのかが一目でわかるように、具体的かつ簡潔に記載しましょう。
例えば、
「【〇〇(商品名)】の不具合に関するお問い合わせについて」
「〇〇(サービス名)ご利用時の件につきまして」
のように、具体的な商品名やサービス名、クレームの内容を簡潔に示すのがポイントです。
これにより、お客様はメールの内容をすぐに把握でき、企業側も後でメールを検索しやすくなります。
冒頭:謝罪と共感の言葉(ただし、過度な謝罪は避ける)
メールの冒頭では、まず、ご迷惑やご不快な思いをさせてしまったことに対する謝罪の言葉を述べましょう。
ただしここで注意したいのは、事実確認が完了する前に、全面的に非を認めるような過度な謝罪は避けることです。
「この度は、〇〇(商品名)に関しまして、ご不快な思いをおかけし、誠に申し訳ございません」
「先日は、弊社の〇〇(サービス)ご利用に際し、ご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」
といった形で、まずはご不便をおかけした事実に対して謝罪します。
同時に、
「さぞご不便だったことと存じます」
「ご心配をおかけし、大変心苦しく思っております」
のように、お客様の気持ちに寄り添う共感の言葉を添えることで、丁寧な印象を与えることができます。
事実確認:客観的な状況把握と経緯の説明
次に、お客様からのご指摘内容に基づき、客観的な事実確認の結果や経緯を説明します。
ここでは、感情を交えず、あくまでも客観的な事実を淡々と述べることを心がけましょう。
「お問い合わせいただきました〇〇(商品名)の件につきまして、社内で状況を確認いたしましたところ、〜〜という事実が確認できました」
「お客様からご指摘いただいた〇〇(日付)の〇〇(状況)につきまして、担当者に確認いたしました結果、〜〜であったことが判明いたしました」
といった形です。
もしお客様の認識と事実が異なる場合は、その点を丁寧に説明する必要がありますが、お客様を責めるような口調にならないよう注意が必要です。
「お客様のお話と一部異なる点がございますが、弊社の記録によりますと〜〜となっておりました」
のように、あくまで客観的な情報として伝えましょう。
原因究明:可能な範囲での原因説明(推測や断定は慎重に)
事実確認に基づき、問題が発生した原因について、可能な範囲で説明します。
ただし、原因が特定できていない段階で、憶測や不確かな情報を伝えるのは避けましょう。
また、原因を説明する際には専門用語を避け、
「今回の不具合は、製造過程における〇〇が原因である可能性が高いことが判明いたしました」
「調査の結果、システムの設定に一部誤りがあったことが原因でございました」
といったお客様にわかりやすい言葉で説明することが大切です。
原因が特定できない場合や調査に時間がかかる場合は、
「現在、詳細な原因につきまして調査を進めております。判明次第、改めてご報告させていただきます」
のように、その旨を正直に伝え、今後の調査方針や報告時期の目安を伝えましょう。
解決策の提示:具体的かつ実現可能な提案
お客様が最も知りたいのは、問題がどのように解決されるのか、ということです。
事実確認と原因究明に基づき、具体的かつ実現可能な解決策を提示しましょう。
例えば、
「つきましては、代替品を〇日までに発送させていただきます」
「ご迷惑をおかけしたお詫びといたしまして、〇〇をご提供させていただきます」
「システムのエラーにつきましては、〇月〇日までに修正を完了する予定でございます」
といった形です。
提示する解決策は、企業の規定や方針に沿ったものである必要があります。
安易に規定外の対応を約束しないよう注意しましょう。
もし、客様の要求に完全に応えられない場合は、その理由を丁寧に説明し、代替案を提示するなど、可能な限りお客様の不満を解消できるよう努める姿勢が重要です。
代替案の提示(必要な場合)
お客様の要求にそのまま応えられない場合や、提示した解決策に納得いただけない場合に、代替案を提示することが有効な場合があります。
代替案は、お客様の状況や要望を考慮し、企業として対応可能な範囲で、できる限りお客様の不利益を軽減できるような内容を検討しましょう。
例えば、
「誠に申し訳ございませんが、ご要望いただいた〇〇(要求内容)につきましては、弊社の規定上、対応致しかねます。代替案といたしまして、△△をご提案させていただきたく存じますが、いかがでしょうか」
といった形でお伝えします。
代替案を提示する際も、一方的に押し付けるのではなく、お客様の意向を確認する姿勢を示すことが大切です。
結び:今後の対応と再発防止への言及、締めの言葉
メールの結びでは、今後の具体的な対応(代替品の発送、返金手続きなど)について改めて触れ、お客様に安心感を与えましょう。
また、
「今後は、このようなことがないよう、品質管理体制を強化し、再発防止に努めてまいります」
「今回の件を真摯に受け止め、従業員教育を徹底し、サービス向上に努めてまいる所存です」
のように、同様の問題が再発しないよう、具体的な再発防止策に言及することで、企業の真摯な姿勢を示すことができます。
最後に、
「この度は、多大なるご迷惑をおかけいたしましたこと、重ねてお詫び申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒お願い申し上げます」
と改めて謝罪の言葉をお伝えし、今後のご愛顧をお願いする言葉で締めくくります。
シーン別 クレーム対応メールの書き方ポイント

クレームの内容は様々です。
ここでは、よくあるクレームのシーン別に、メール作成のポイントを見ていきましょう。
製品・サービスの不具合に関するクレーム
製品やサービスの不具合に関するクレームは、お客様が具体的な損害や不便を感じているケースが多いです。
まずは、ご不便をおかけしたことへの謝罪と共感をしっかりと伝えましょう。
その上で、不具合の状況を具体的にお伺いし、事実確認を迅速に行います。
原因を特定し、交換、修理、返金などの具体的な解決策を提示します。
代替品の発送や修理にかかる期間など、今後のスケジュールも明確に伝えることが重要です。
再発防止策についても具体的に言及し、お客様の不安を取り除くように努めましょう。
接客態度に関するクレーム
スタッフの接客態度に関するクレームは、お客様の感情的な側面が強い場合があります。
まずは、不快な思いをさせてしまったことに対して、真摯に謝罪することが重要です。
具体的な状況を丁寧にお伺いし、事実確認を行います。
もしスタッフに非があった場合は、指導・教育を徹底する旨を伝え、再発防止に努める姿勢を示します。
ただし、スタッフ個人の名前を挙げて過度に責めるような表現は避け、組織としての問題として捉え、改善に取り組むことを伝えましょう。
お客様の気持ちに寄り添い、失った信頼を回復できるよう、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
誤解や認識の違いによるクレーム
時には、お客様の誤解や認識の違いからクレームに発展するケースもあります。
この場合、頭ごなしに否定するのではなく、まずは「ご指摘ありがとうございます」と受け止める姿勢を示しましょう。
その上で、お客様の認識と事実が異なる点を、客観的な情報や資料(契約書、利用規約など)に基づいて丁寧に説明します。
お客様の誤解を解くことを目指しますが、決して責めるような口調にならないよう、言葉遣いには細心の注意が必要です。
「弊社の説明が不足しており、誤解を招いてしまい申し訳ございません」といった形で、自社にも配慮が足りなかった点があれば、その点も伝えることで、お客様の怒りの感情を和らげることができます。
理不尽な要求を含むクレームへの対応
残念ながら、中には社会通念上、受け入れがたい理不尽な要求を伴うクレームもあります。
このような場合でも、まずは冷静に対応することが重要です。
感情的にならず、お客様の言い分を一旦は傾聴する姿勢を示しましょう。
その上で、企業の規定や法令に基づき、対応できることとできないことを明確に線引きし、毅然とした態度で伝えます。
「誠に申し訳ございませんが、ご要望いただいた〇〇につきましては、弊社の規定(あるいは法令)により、対応致しかねます」
といった形で理由を丁寧に説明し、代替案があれば提示しますが、無理な要求に応じる必要はありません。
対応が難しい場合は、上司や関連部署に相談し、組織としての方針を決定することが重要です。
必要であれば、弁護士などの専門家への相談も検討しましょう。
クレーム対応メール作成を効率化するために

クレーム対応メールの作成は、精神的にも時間的にも大きな負担がかかる業務です。
少しでも効率的に、そして質の高い対応を行うための工夫について考えてみましょう。
定型文・テンプレートの活用とその注意点
よくあるクレームに対しては、ある程度の定型文やテンプレートを用意しておくと、メール作成の時間を短縮できます。
謝罪の言葉、事実確認の依頼、解決策の提示パターンなど、基本的な構成要素をテンプレート化しておくと便利です。
ただし、テンプレートをそのまま使うのではなく、必ずお客様の状況やクレームの内容に合わせて、具体的な情報を追記したり、表現を調整したりすることが重要です。
テンプレート感が強く出てしまうと、かえってお客様に不誠実な印象を与えてしまう可能性があるため注意しましょう。
あくまで「下書き」や「骨子」として活用するのがポイントです。
チーム内での情報共有と対応方針の統一
クレーム対応は、担当者一人で抱え込まず、チーム全体で情報を共有し、対応方針を統一することが大切です。
どのようなクレームがあり、どのように対応したのかを記録・共有することで、同様のクレームが発生した場合にスムーズに対応できます。
また、対応に困った場合や、判断に迷う場合は、すぐに上司や同僚に相談できる体制を整えておくことも重要です。
特に、日本の組織では「報・連・相(報告・連絡・相談)」が重視されます。
属人化を防ぎ、一貫性のある対応を行うためにも、チーム内でのコミュニケーションは欠かせません。
AIを活用したメール作成支援という選択肢
近年、AI技術の進化により、メール作成を支援するツールが登場しています。
こうしたツールを活用するのも、クレーム対応の効率化に有効な手段の一つです。
例えば、簡単な指示や要点を入力するだけで、AIが状況に応じた丁寧なメール文面を作成してくれるサービスがあります。
また、過去の対応履歴を学習し、類似のクレームに対して適切な返信案を提示してくれる機能を持つものもあります。
もちろん、AIが作成した文章をそのまま送信するのではなく、必ず人間の目で内容を確認し、お客様の状況に合わせて修正を加える必要はあります。
しかし、ゼロから文章を考える手間が省けるだけでも、大幅な時間短縮と精神的な負担の軽減につながるのではないでしょうか。
特に、人手不足が深刻な日本の労働市場において、こうしたツールは業務効率化の大きな助けとなる可能性があります。
ここで、AIを活用したメール作成支援ツール**『代筆さん』**をご紹介します。
『代筆さん』は、簡単な指示や要件を伝えるだけで、AIがビジネスメールを作成してくれるWebサービスです。
クレーム対応のような、定型的でありながらも丁寧さが求められるメール作成において、その力を発揮します。
相手からのクレームメールの内容を貼り付けて、「謝罪と原因調査、今後の対応について返信して」のように指示するだけで、状況に応じた返信文案を作成してくれます。
よく使う指示内容をテンプレートとして保存しておけば、毎回同じ指示を入力する手間も省けます。
もちろん、最終的な確認と修正は必要ですが、メール作成の時間を大幅に短縮し、より重要な業務に集中できるようになるはずです。
感情的な負担を軽減する工夫
クレーム対応は、精神的に大きな負担がかかる仕事です。
お客様からの厳しい言葉に、心が疲弊してしまうこともあるでしょう。
自分一人で抱え込まず、上司や同僚に相談したり、時には気分転換をしたりすることも大切です。
また、クレーム対応は「個人の問題」ではなく「組織の問題」として捉え、チームで支え合う意識を持つことが重要です。
適切なツールを活用して業務負荷を軽減することも、感情的な負担を和らげる一つの方法と言えるでしょう。
まとめ:信頼回復につなげるクレーム対応を目指して

丁寧さと毅然さのバランスが鍵
クレーム対応メールで最も重要なのは、やはり「丁寧さ」と「毅然さ」のバランスです。
お客様の気持ちに寄り添う丁寧な言葉遣いを心がけつつ、事実に基づき、伝えるべきことは明確に伝える毅然とした姿勢を保つこと。
このバランスを意識することで、お客様の感情を鎮め、建設的な対話へと導くことができます。
クレームは改善のチャンス
クレームは、決してネガティブなものだけではありません。
お客様からのご指摘は、自社の製品やサービス、業務プロセスを見直す貴重な機会を与えてくれます。
クレームの背景にある原因を真摯に受け止め、改善につなげることで、より良いサービスを提供できるようになります。
ピンチをチャンスに変える、という視点を持つことも大切ですね。
ツールを活用して効率化を図る
クレーム対応メールの作成には、多くの時間と労力がかかります。
テンプレートの活用やチーム内での情報共有に加え、AIを活用したメール作成支援ツールの導入も検討してみてはいかがでしょうか。
例えば、**代筆さん**のようなツールを使えば、メール作成の時間を短縮し、より迅速で質の高い対応を実現できる可能性があります。
日々のメール業務の負担を軽減し、より本質的な業務に集中するための一つの選択肢として、ぜひ検討してみてください。
この記事が、あなたのクレーム対応メール作成の一助となれば幸いです。