モンスタークレーマーへの正しい対応策|冷静かつ毅然と対処する方法
モンスタークレーマーへの具体的な対応策

「またこのお客様か…」と、特定のお客様からの連絡に、思わずため息をついてしまうことはありませんか?
理不尽な要求を繰り返したり、大声で威嚇してきたり、長時間にわたって担当者を拘束したり…。
いわゆる「モンスタークレーマー」と呼ばれる人たちの対応に、心をすり減らしている方は、本当に多いのではないでしょうか。
実は私も、以前の職場で同じような経験をしたことがあります。
丁寧に対応しようとすればするほど、相手の要求がエスカレートしていくようで、どうすればいいのか分からなくなってしまったんです。
毎日、そのお客様からの電話が鳴るのが怖くて、精神的にかなり追い詰められていました。
でも、安心してください。
モンスタークレーマーへの対応には、適切な方法があります。
今回は、そんなあなたの悩みに寄り添いながら、モンスタークレーマーに冷静かつ毅然と対応するための具体的な方法を、ステップバイステップでご紹介します。
この記事を読めば、あなたはモンスタークレーマーの特徴を理解し、適切な初期対応から、組織的な対策まで、具体的な行動プランを立てられるようになります。
もう一人で抱え込まずに、一緒に解決策を見つけていきましょう。
モンスタークレーマーとは?その特徴を理解する

まず、私たちが向き合っている「モンスタークレーマー」とは、一体どのような存在なのでしょうか。
彼らの特徴をしっかり理解することが、適切な対応への第一歩になります。
通常のクレームとの違い
大前提として、お客様からのクレームやご意見は、サービス改善につながる貴重な声である場合も多いですよね。
商品やサービスに不備があった場合、それに対する正当なご指摘は、真摯に受け止め、改善に繋げるべきです。
しかし、モンスタークレーマーの要求は、その範囲を大きく逸脱しています。
例えば、以下のような点が、通常のクレームとの大きな違いと言えるでしょう。
- 要求の過剰性: 社会通念上、明らかに度を超えた金銭やサービスの要求をしてくる。
- 手段の不当性: 大声で怒鳴る、脅迫的な言動をとる、長時間居座る、SNSで誹謗中傷するなど、目的達成のためなら手段を選ばない。
- 目的の歪み: 問題解決そのものよりも、担当者を困らせたり、自分の要求を無理やり通したりすること自体が目的になっている場合がある。
通常のクレームは「問題解決」を目指す対話ですが、モンスタークレーマーの場合は、対話が成立しにくい、一方的な要求であることが多いのです。
モンスタークレーマーが生まれる背景
なぜ、このような行動をとる人が現れるのでしょうか。
一概には言えませんが、いくつかの社会的背景も関係していると考えられています。
例えば、ストレス社会における精神的な不満のはけ口を求めているケース。
あるいは、過去に何らかのトラブルで強い要求が通ってしまった成功体験から、同じ方法を繰り返しているケース。
また、インターネットの普及により、匿名で過激な要求を伝えやすくなった側面もあるかもしれません。
日本の「お客様は神様」という考え方が、過剰な期待を生み、少しでも意に沿わないことがあると、強い不満につながってしまう、という文化的背景も指摘されています。
もちろん、これらの背景がすべてのケースに当てはまるわけではありませんが、彼らの行動の裏にあるかもしれない要因を少しでも理解しようとすることは、冷静さを保つ上で役立つかもしれません。
モンスタークレーマーの典型的な行動パターン
モンスタークレーマーには、いくつかの典型的な行動パターンが見られます。
これを知っておくことで、初期段階で「これは通常のクレームとは違うかもしれない」と気づき、冷静に対応を準備することができます。
- 威圧・恫喝: 大声を出す、机を叩く、暴言を吐くなどして相手を萎縮させようとする。
- 長時間拘束: 何時間も電話を切らせない、店舗に居座るなどして、担当者を疲弊させる。
- 繰り返し・執拗な要求: 同じ要求を何度も繰り返したり、担当者を変えさせたりして、根負けさせようとする。
- 揚げ足取り・論点のすり替え: 話の本筋とは関係ない細かいミスを指摘したり、次々と論点を変えたりして、相手を混乱させる。
- 不合理な要求: 法外な金銭賠償、土下座の強要、個人的な情報の開示など、常識的に考えて受け入れられない要求をする。
- 関係者の巻き込み: 上司を出せ、社長に謝罪させろ、など、関係のない人物を巻き込もうとする。
- SNSなどでの拡散: 要求が通らないと、SNSや口コミサイトで一方的な情報を拡散すると脅したり、実行したりする。
これらのパターンが見られた場合は、特に慎重な対応が必要になります。
モンスタークレーマー対応の基本原則
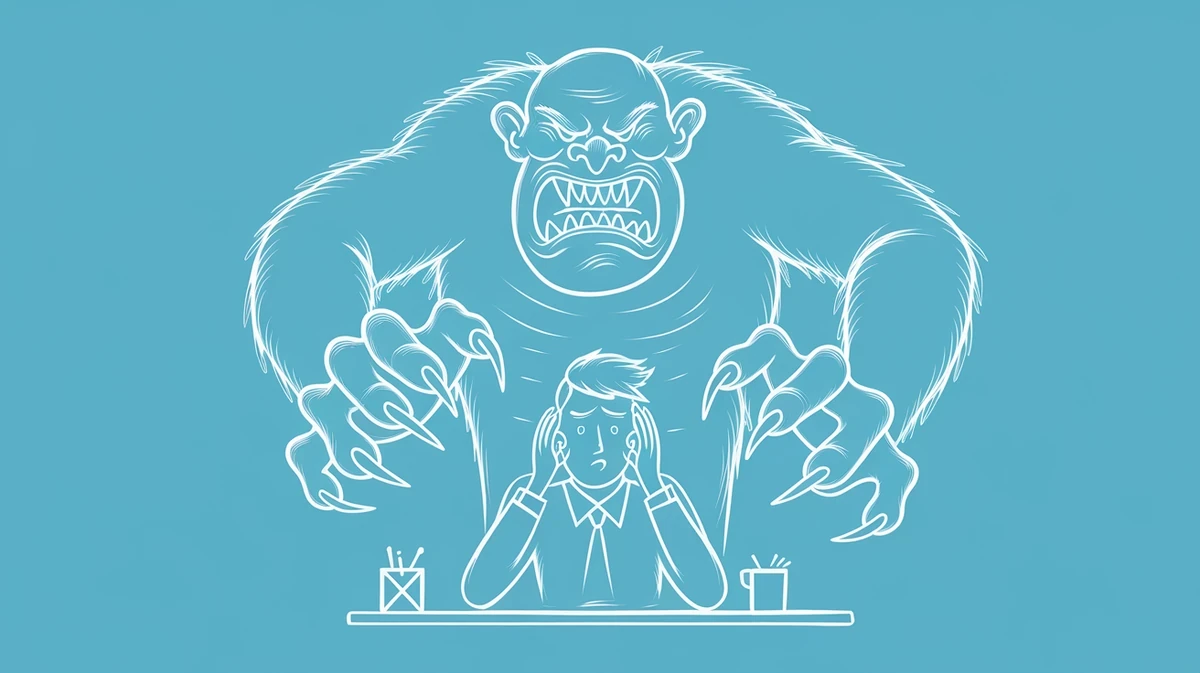
モンスタークレーマーに遭遇してしまった時、パニックにならず、適切に対応するためには、いくつかの基本原則を押さえておくことが非常に重要です。
これらの原則を常に意識することで、状況が悪化するのを防ぎ、自分自身を守ることにも繋がります。
冷静さを保つことの重要性
これが最も重要であり、同時に最も難しいことかもしれません。
相手が感情的に攻撃してきても、こちらも感情的になってしまっては、相手の思うつぼです。
深呼吸をする、一旦席を外す(電話なら保留にする)などして、意識的に冷静さを取り戻す時間を作りましょう。
「相手の感情に引きずられない」と心の中で繰り返すだけでも、少し効果があるかもしれません。
冷静さを失うと、不適切な発言をしてしまったり、安易な約束をしてしまったりするリスクが高まります。
常に「プロフェッショナルとして対応する」という意識を持つことが大切です。
傾聴の姿勢を示す(ただし、要求にすべて応えるわけではない)
相手の話をまずは聞く、という姿勢は重要です。
「ちゃんと話を聞いてもらえている」と感じさせることで、相手の興奮が少し収まることもあります。
相槌を打ったり、相手の言葉を繰り返したりして、「あなたの話を理解しようとしています」というシグナルを送りましょう。
ただし、注意点があります。
「傾聴」=「相手の要求をすべて受け入れる」ではありません。
あくまで、相手の言い分を把握するために聞く、というスタンスです。
共感を示す際も、「お気持ちお察しします」といった表現に留め、安易な謝罪や、要求を受け入れるような発言は避けましょう。
事実確認を徹底する
相手の主張を鵜呑みにせず、客観的な事実を確認することが不可欠です。
「いつ」「どこで」「何が」起こったのか、具体的な状況を、冷静に、かつ丁寧に質問します。
感情的な訴えと、事実を切り分けて考えることが重要です。
もし、相手の主張と事実が異なる場合は、その点を毅然と指摘する必要があります。
ただし、喧嘩腰になるのではなく、あくまで客観的な証拠(記録、防犯カメラ映像、第三者の証言など)に基づいて説明するように心がけてください。
対応記録を残すことの重要性
モンスタークレーマーとのやり取りは、必ず詳細な記録を残しましょう。
いつ、誰が、誰と、どのような内容で、どのくらいの時間話したのか。
相手の具体的な要求内容、こちらの対応内容、発言などを、時系列で記録します。
可能であれば、会話を録音することも有効な手段です。
(録音する場合は、相手にその旨を伝えるのが望ましいですが、状況によっては難しい場合もあります。法的な側面も考慮し、社内ルールを確認しましょう。)
この記録は、後々、上司や関連部署に報告する際や、万が一、法的な問題に発展した場合に、非常に重要な証拠となります。
また、記録を残すことで、対応の経緯を客観的に振り返ることができ、今後の対策を立てる上でも役立ちます。
具体的な対応ステップとフレーズ例
では、実際にモンスタークレーマーと思われる相手と対峙した場合、具体的にどのように対応を進めていけば良いのでしょうか。
段階ごとのステップと、使えるフレーズ例をいくつかご紹介します。
初期対応:まずは落ち着いて話を聞く
最初の接触が非常に重要です。
ここで慌てたり、逆に突き放したりすると、状況が悪化しかねません。
まずは相手の話を遮らずに、最後まで聞く姿勢を見せましょう。
H4: 共感を示す言葉(ただし謝罪は慎重に)
相手の感情を受け止める言葉は有効ですが、謝罪は慎重に行う必要があります。
-
OKフレーズ例:
- 「〇〇(相手が訴える不便や不快な状況)とのこと、ご不便をおかけし申し訳ございません。」(事実に対して)
- 「そのようなお気持ちになられたのですね。お察しいたします。」(感情に対して)
- 「貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。」
-
NGフレーズ例:
- 「全面的に私どもの責任です。」(事実確認前に非を認めてしまう)
- 「大変申し訳ございませんでした!」(過剰な謝罪は、さらなる要求を引き出す可能性も)
安易な謝罪は、非を認めたと捉えられ、後の交渉で不利になる可能性があります。
謝罪するとしても、具体的な事実関係が確認できてから、どの点について謝罪するのかを明確にすることが大切です。
H4: 事実確認のための質問例
相手の話を聞きながら、冷静に事実を確認するための質問を挟んでいきましょう。
- 「恐れ入りますが、もう少し詳しく状況をお伺いしてもよろしいでしょうか?」
- 「それは、いつ頃のことでしょうか?」
- 「具体的に、どのような点が問題だとお感じになられましたか?」
- 「〇〇ということについて、確認させていただいてもよろしいでしょうか?」
高圧的な相手に対しても、あくまで丁寧な言葉遣いを崩さないことがポイントです。
要求内容の整理と判断基準
相手の言い分を一通り聞いたら、次にその要求内容を整理し、対応可能かどうかを判断する必要があります。
H4: 正当なクレームか、過剰な要求かの見極め
ここで重要なのは、客観的な視点です。
- 要求は具体的か?: 漠然とした不満ではなく、具体的な要求があるか。
- 要求は社会通念上、妥当か?: 提供したサービスや商品の対価として、要求内容が見合っているか。法外な金額や、実現不可能な要求ではないか。
- 原因は自社にあるか?: 相手の主張する問題の原因が、本当に自社の製品やサービス、従業員の対応にあるのか。
これらの点を冷静に分析し、正当なクレームであれば誠実に対応し、過剰または不当な要求であれば、毅然とした態度で臨む必要があります。
H4: 社内ルールや法律との照らし合わせ
対応方針を決める際には、必ず社内で定められたクレーム対応のルールやガイドラインを確認しましょう。
また、要求内容によっては、消費者契約法や特定商取引法など、関連する法律の知識が必要になる場合もあります。
不明な点があれば、自己判断せず、必ず上司や法務担当部署などに相談してください。
対応可能な範囲と限界を明確に伝える
全ての要求に応える必要はありません。
むしろ、できないことはできないと、はっきりと伝えることが重要です。
H4: できないことは「できない」と伝える勇気
曖昧な返事をしたり、期待を持たせるような言い方をしたりすると、相手はさらに要求をエスカレートさせる可能性があります。
- 「大変申し訳ございませんが、そのご要望にお応えすることは致しかねます。」
- 「社内の規定により、〇〇といった対応はできかねます。」
- 「法律上、〇〇することは認められておりません。」
伝える際には、感情的にならず、あくまで会社のルールや法律といった客観的な理由を添えて説明すると、相手も納得しやすくなります(もちろん、納得しない場合も多いですが…)。
H4: 代替案を提示する際の注意点
完全に要求を拒否するだけでなく、可能であれば代替案を提示することも有効です。
ただし、その代替案が、新たな火種にならないように注意が必要です。
- 実現可能で、かつ会社として許容できる範囲の代替案であること。
- 代替案を提示する際も、「これでいかがでしょうか?」と一方的に決めるのではなく、「〇〇という方法であれば、対応可能ですが、いかがでしょうか?」と、相手の意向を確認する形をとる。
- 代替案に対しても、相手がさらに過剰な要求をしてくる場合は、深追いせずに、再度「それ以上の対応は難しい」と伝える。
エスカレーション:手に負えない場合の対応
担当者一人で対応できる範囲には限界があります。
「これは自分だけでは手に負えない」と感じたら、迷わずエスカレーション(上司や専門部署に対応を引き継ぐこと)しましょう。
H4: 上司や専門部署への相談タイミング
以下のような状況になったら、速やかに上司や関連部署(カスタマーサポート部門、法務部など)に相談・報告しましょう。
- 相手の要求がエスカレートし、収拾がつかなくなった場合
- 脅迫、名誉毀損、威力業務妨害など、違法行為の可能性がある言動が見られる場合
- 担当者個人への攻撃が始まった場合
- 長時間の拘束が続き、業務に支障が出ている場合
- 対応方針について判断に迷う場合
決して一人で抱え込まないでください。
組織として対応することが重要です。
H4: 弁護士や警察への相談も視野に入れる場合
状況によっては、弁護士や警察への相談が必要になるケースもあります。
- 弁護士への相談: 法的な対応が必要な場合(損害賠償請求、契約解除など)、要求が不当であることを法的に示したい場合。
- 警察への相談: 脅迫、暴行、器物損壊、不退去(店舗などから立ち去らない)など、身の危険を感じる、または犯罪行為が行われた場合。
これらの専門機関に相談する際にも、前述した「対応記録」が非常に役立ちます。
やってはいけないNG対応

モンスタークレーマーへの対応では、良かれと思って取った行動が、逆に事態を悪化させてしまうことも少なくありません。
ここでは、絶対に避けるべきNG対応について確認しておきましょう。
感情的になる、反論する
相手の挑発に乗ってしまい、感情的になったり、強い口調で反論したりするのは最悪の対応です。
相手は、あなたを感情的にさせること自体を楽しんでいる可能性もあります。
また、不用意な発言は、後で揚げ足を取られる原因にもなりかねません。
常に冷静さを保ち、プロフェッショナルとしての態度を貫きましょう。
その場しのぎの安易な約束をする
早くこの場を収めたい一心で、実現できないことや、社内ルールに反することを安易に約束してしまうのは絶対にNGです。
その場は収まったとしても、後で約束が守られないとなれば、さらに大きなクレームに発展し、信頼を失うことになります。
守れない約束は、絶対にしてはいけません。
できないことは、正直に「できない」と伝える勇気が必要です。
相手の土俵に乗ってしまう(個人攻撃に応じるなど)
クレーマーの中には、担当者個人を攻撃してくる人もいます。
「あなたの態度が悪い」「あなたでは話にならない」といった人格否定や、能力を貶めるような発言です。
これに対して、「そんなことはありません!」と反論したり、個人的な感情で応酬したりするのは避けましょう。
あくまで「会社の代表」として、組織の問題として対応するという姿勢を崩さないことが大切です。
個人への攻撃が続く場合は、上司に交代してもらうなどの対応を検討しましょう。
一人で抱え込む
「自分が対応しなければ」「他の人に迷惑をかけられない」といった責任感から、一人で問題を抱え込んでしまうケースがあります。
しかし、モンスタークレーマー対応は、精神的に大きな負担がかかります。
一人で対応し続けることで、心身ともに疲弊し、適切な判断ができなくなる可能性もあります。
前述したように、手に負えないと感じたら、あるいは少しでも不安を感じたら、すぐに上司や同僚に相談し、情報を共有することが重要です。
組織全体で対応するという意識を持ちましょう。
組織としての対策と予防策

モンスタークレーマーへの対応は、個人のスキルだけに頼るのではなく、組織全体で取り組むべき課題です。
しっかりとした対策と予防策を講じることで、従業員を守り、健全な企業活動を維持することができます。
対応マニュアルの整備と共有
どのような場合に、誰が、どのように対応するのかを明確にしたマニュアルを作成し、全従業員で共有することが基本です。
- クレームの受付方法(電話、メール、対面など)
- 初期対応の手順
- 事実確認の方法
- エスカレーションの基準と手順
- 記録の残し方
- 言ってはいけないNGワード、推奨されるフレーズ例
- 弁護士や警察への相談基準
マニュアルは、一度作ったら終わりではなく、実際の事例を踏まえて定期的に見直し、改善していくことが重要です。
また、マニュアルの内容を理解し、実践できるよう、ロールプレイングなどの研修を実施することも効果的です。
担当者の精神的ケアとサポート体制
クレーム対応、特にモンスタークレーマー対応は、担当者に大きな精神的ストレスを与えます。
- 相談しやすい環境づくり: 担当者が一人で抱え込まず、いつでも上司や同僚に相談できる雰囲気を作ることが大切です。
- 担当者の交代: 特定の担当者に負担が集中しないよう、必要に応じて担当を交代できる体制を整える。
- 定期的な面談: 上司が定期的に担当者の状況を確認し、精神的なフォローを行う。
- 専門家への相談窓口: 必要であれば、産業医やカウンセラーなど、外部の専門家への相談窓口を設けることも検討しましょう。
従業員のメンタルヘルスを守ることは、組織の重要な責務です。
顧客との良好な関係構築の重要性
普段から顧客との良好なコミュニケーションを心がけ、信頼関係を築いておくことも、モンスタークレーマー化を防ぐ上で有効です。
もちろん、これだけで全てのモンスタークレーマーを防げるわけではありませんが、普段から丁寧な対応を積み重ねていれば、些細なことで大きなクレームに発展するリスクを減らすことができます。
感謝の気持ちを伝えたり、顧客の声をサービス改善に活かしたりする姿勢を示すことが大切です。
日々の丁寧なコミュニケーションが予防につながる
結局のところ、日々の業務における一つ一つの丁寧なコミュニケーションが、クレームの発生を未然に防ぐ最も基本的な対策と言えるかもしれません。
分かりやすい説明、迅速な対応、誠実な態度を心がけることで、顧客満足度を高め、理不尽な要求に繋がるような不満の芽を摘むことができます。
特に、メールや文書でのやり取りは、記録にも残り、誤解を生みやすいため、より一層の注意が必要です。
丁寧かつ毅然としたコミュニケーションをサポートする

モンスタークレーマー対応においては、対面や電話だけでなく、メールや文書でのやり取りも重要になってきます。
特に、記録を残すという意味では、文書でのコミュニケーションは非常に有効です。
メール対応での注意点
メールでクレーム対応を行う場合、以下の点に注意しましょう。
- 迅速な返信: まずは受信確認だけでも早めに返信する。
- 丁寧な言葉遣い: 対面以上に、言葉遣いには細心の注意を払う。敬語の使い方なども重要です。
- 誤解のない表現: 感情的な表現は避け、客観的な事実に基づいて、分かりやすく記述する。
- 記録の保管: 送受信したメールは、必ず全て保管しておく。
しかし、毎回適切な言葉を選び、丁寧かつ毅然としたトーンでメールを作成するのは、なかなか骨が折れる作業ですよね。
特に、相手が感情的になっている場合、どのような言葉を選べば良いか迷ってしまうこともあるでしょう。
記録に残る文書でのやり取りの重要性
前述の通り、クレーム対応の経緯を記録として残すことは非常に重要です。
メールでのやり取りは、その記録として有効な手段の一つです。
後から「言った」「言わない」の水掛け論になるのを防ぐためにも、重要な合意事項や、対応の経緯については、メールなどの文書で確認し合うことが望ましいでしょう。
適切な言葉遣いをサポートするツールの活用
日々のメール作成、特にクレーム対応のような神経を使う場面での文章作成は、想像以上に時間と労力がかかりますよね。
丁寧さを心がけつつも、こちらの主張はしっかりと伝えなければならない…そのバランスが難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。
そんな悩みを解決するのが、『代筆さん』です。
代筆さんは、簡単な指示や要件を伝えるだけで、AIがビジネスメールを作成してくれるWebサービスです。
例えば、クレーマーへの返信メールを作成したい場合、相手のメール内容と、「丁寧にお断りしたい」「代替案を提案したい」といったあなたの意向を伝えるだけで、AIが状況に応じた適切な文章を作成してくれます。
もちろん、AIが作成した文章をそのまま使うのではなく、あなたの言葉で修正を加えることも可能です。
これにより、メール作成にかかる時間を大幅に短縮できるだけでなく、感情的にならず、常に冷静で適切なトーンの文章を作成する手助けとなります。
特に、同じような内容の問い合わせやクレームが繰り返し寄せられる場合には、指示をテンプレートとして保存しておけば、さらに効率的に対応できます。
クレーム対応で疲弊してしまう前に、このようなツールを活用して、少しでもあなたの負担を軽減することを考えてみてはいかがでしょうか。
まとめ:冷静かつ毅然とした対応で、自分と組織を守る

今回は、モンスタークレーマーへの具体的な対応策について、その特徴から、基本原則、具体的なステップ、NG行動、そして組織的な対策まで幅広くお伝えしてきました。
モンスタークレーマーへの対応は、本当に精神力を使いますよね。
しかし、正しい知識と手順を身につけ、冷静かつ毅然とした態度で臨めば、必ず乗り越えることができます。
重要なのは、一人で抱え込まず、組織として対応すること、そして、あなた自身の心を守ることです。
対応記録をしっかり残し、できないことは「できない」と伝える勇気を持ちましょう。
そして、日々のコミュニケーションにおいては、丁寧さを心がけることが、無用なトラブルを防ぐ一番の近道です。
もし、メールや文書でのコミュニケーションに負担を感じているなら、代筆さんのようなツールを活用するのも一つの手です。
あなたの貴重な時間とエネルギーを、より前向きな業務に使えるように、ぜひ検討してみてください。
この記事が、あなたの悩みを少しでも軽くし、明日からの対応に役立つことを心から願っています。




