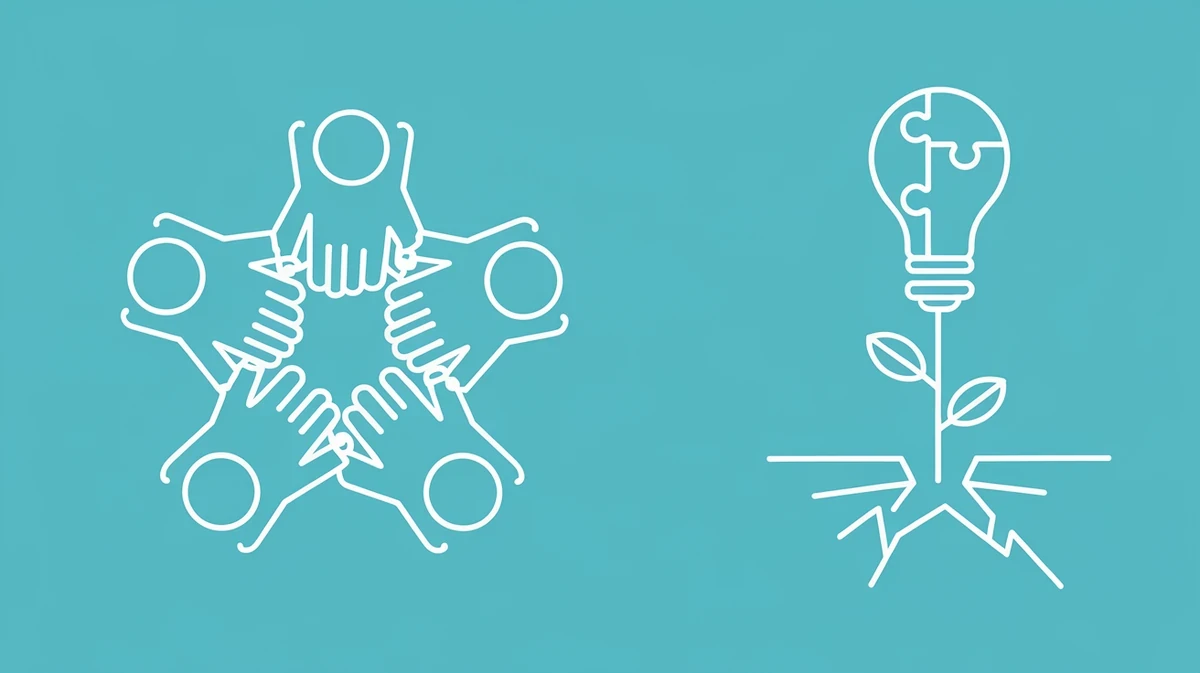メンタルヘルスケアを促す従業員向けメール 3つのステップと例文
メンタルヘルスケアの案内

件名:【ご相談】最近のご状況について
株式会社[会社名]
[従業員名]様お世話になっております。
[会社名]、[部署名]の[担当者名]です。[従業員名]さんのご活躍を日々拝見しております。
いつもありがとうございます。さて、[従業員名]さんのご様子について、少し気になっていることがございます。
もし差し支えなければ、最近のご状況について、お聞かせいただけないでしょうか。[従業員名]さんの状況に応じて、[社内相談窓口]や[専門カウンセラー]のご紹介など、[会社名]としてできる限りのサポートをさせて頂きたいと考えております。
もちろん、お話しにくいことがあれば、無理にご回答いただく必要はございません。
まずは、[従業員名]さんの心身の健康が第一ですので、何かお困りのことがございましたら、遠慮なくご連絡ください。
ご都合の良い時間にご連絡いただけると幸いです。
メンタルヘルスケア、ちゃんとできていますか?
時には心も体も「ちょっと休憩…」って言いたくなる時がありますよね。
この記事では、従業員のメンタルヘルス不調にいち早く気づき、適切なケアへと繋げるためのメールについて、具体的な方法やポイントを解説していきます。
「なんだか最近、元気がないな…」と感じる従業員がいるけれど、どう声をかけたらいいかわからない。
そんな悩みを抱える人事担当者や管理職の方々にとって、この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです。
記事は、まずメンタルヘルス不調を早期発見するメールの重要性から始まり、メール作成の基本ステップ、状況別の例文、そしてサポートを促進するポイントへと進みます。
それでは、一緒に見ていきましょう。
従業員のメンタル不調を早期発見するメールの重要性

メンタルヘルス不調のサインを見逃さないために
従業員のメンタルヘルス不調は、早期発見がとても大切です。
なぜなら、心の不調は、放置すると深刻化してしまうことがあるからです。
例えば、いつもは明るく元気な人が、急に口数が減ったり、集中力がなくなったり。
些細な変化でも、見過ごさずに「もしかして、何かあったのかな?」と気に掛けることが大切です。
メンタルヘルス不調のサインは、人によって様々です。
例えば、以下のようなサインが挙げられます。
- 遅刻や欠席が増える
- ミスが多くなる
- 以前よりイライラしやすくなる
- 表情が暗く、元気がない
- 食欲不振や睡眠障害を訴える
これらのサインにいち早く気づき、適切な対応を取ることが、従業員の心身の健康を守る第一歩となります。
そのための有効な手段の一つが、メンタルヘルスケアを促すメールなのです。
メールは、対面での会話が難しい場合でも、従業員の状況を把握し、必要なサポートへと繋げるための大切なツールとなります。
次の章では、メンタルヘルス不調に気づくためのメールがなぜ重要なのか、さらに深掘りしていきます。
メンタルヘルスケアメール作成3つのステップ

メンタルヘルスケアを目的としたメールを作成する際には、従業員が安心して相談できるような配慮が必要です。
ここでは、具体的なステップとして、件名、本文、行動喚起の3つのポイントに分けて解説します。
これらのステップを踏むことで、より効果的なメンタルヘルスケアメールを作成することができます。
件名で緊急度と目的を明確に伝える
メールの件名は、受信者が最初に目にする部分であり、メールの重要度を判断する上で非常に重要です。
メンタルヘルスに関するメールの場合、件名で緊急度や目的を明確に伝えることで、受信者の注意を引き、迅速な対応を促すことができます。
例えば、
- 【重要】メンタルヘルスに関するご相談
- 【至急】体調不良に関するご連絡
といった件名は、メールの重要度を明確に示し、従業員が安心してメールを開封するきっかけとなります。
件名を見ただけで内容が理解できるように、具体的かつ簡潔な表現を心がけましょう。
本文で具体的な状況とサポートを提示する
メール本文では、従業員の状況を具体的に把握し、適切なサポートを提示することが重要です。
まずは、従業員の状況を丁寧に聞き取り、共感の姿勢を示すことから始めましょう。
例えば、「最近、[従業員名]さんのご様子が少し心配です」といった具体的な表現を用いることで、相手への配慮を示すことができます。
次に、利用できるサポート体制を具体的に提示します。
例えば、「社内の相談窓口」や「専門カウンセラーの紹介」などを案内し、従業員が安心して相談できる環境を整えましょう。
具体的なサポート内容を提示することで、従業員は「自分は一人ではない」と感じ、安心して相談することができます。
返信を促す行動喚起を入れる
メールの最後に、返信を促す行動喚起を入れることで、従業員からのフィードバックや相談をスムーズに促すことができます。
例えば、「何かお困りのことがあれば、遠慮なくご連絡ください」といった言葉で、返信を促すことができます。
また、「ご都合の良い時間にご連絡いただけると幸いです」と伝えることで、従業員の負担を軽減し、より気軽に相談できる雰囲気を作ることが可能です。
返信期限を設定することで、早期の対応を促すことも有効ですが、従業員にプレッシャーを与えないように配慮する必要があります。
状況別 メンタルヘルス不調連絡メールの例文と書き方

従業員のメンタルヘルス不調を早期に把握し、適切な対応をするためには、状況に応じたメールの使い分けが重要です。
ここでは、軽度な不調、休職を検討している場合、緊急性の高い状況の3つのケースに分けて、具体的なメールの例文と書き方を解説します。
それぞれの状況を理解し、従業員に寄り添った対応を心がけましょう。
軽度な不調を訴える従業員へのメール例
まずは、従業員から軽度な不調の訴えがあった場合のメール例です。
この段階では、状況を詳しく把握し、適切なサポートを提供することが大切です。
焦らず、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。
軽度な不調を訴える従業員へのメール例
件名:ご体調について
[従業員名]様
先日は、体調がすぐれないとのこと、ご心配です。
現在の状況について、詳しくお聞かせいただけますでしょうか。
もし、お話しにくいことがあれば、無理にご回答いただく必要はございません。
状況に応じて、[利用可能なサポート]などのご案内もできますので、お気軽にご相談ください。
まずは、ゆっくりと休養してください。
[会社名] [担当者名]
このメールは、従業員の体調を気遣いつつ、具体的な状況を尋ねることで、状況把握とサポートの提供を目的としています。
また、状況によっては無理に回答する必要がないことを伝えることで、従業員の心理的な負担を軽減するように配慮しましょう。
休職を検討している従業員へのメール例
次に、従業員が休職を検討している場合のメール例です。
この段階では、従業員の意思を尊重しつつ、必要な情報を提供し、休職の手続きを円滑に進めることが大切です。
休職中のサポートについても伝え、安心して休養できる環境を整えましょう。
休職を検討している従業員へのメール例
件名:休職に関するご相談
[従業員名]様
休職のご検討について、ご連絡ありがとうございます。
まずは、ご自身の心身をゆっくりと休ませることが大切です。
休職をご希望される場合は、[休職に関する手続き]についてご案内させていただきます。
また、休職期間中の[給与や保険に関する情報]、復職に向けたサポートなどについても、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
安心して休養できるよう、私たちもできる限りのサポートをさせていただきます。
[会社名] [担当者名]
このメールは、従業員の休職意思を尊重し、必要な手続きや情報を提供することを目的としています。
休職中の不安を軽減するために、サポート体制についても具体的に伝え、安心感を与えるように努めましょう。
緊急性の高い状況に対応するメール例
最後に、従業員の状況が緊急性が高いと思われる場合のメール例です。
この場合は、迅速な対応が求められます。
まずは従業員の安全を最優先に考え、状況に応じて医療機関や専門機関への相談を促すことが重要です。
緊急性の高い状況に対応するメール例
件名:緊急のご連絡
[従業員名]様
ご連絡いただいた状況から、緊急を要すると判断いたしました。
まずは、ご自身の安全を確保してください。
[緊急連絡先]までご連絡いただくか、難しい場合は、[医療機関名]にご相談ください。
また、ご家族やご友人など、信頼できる方にご連絡することも検討してください。
私たちは、[会社名]として、できる限りのサポートをさせていただきます。
[会社名] [担当者名]
このメールは、従業員の安全を最優先に考え、速やかに医療機関や専門機関へ相談することを促すことを目的としています。
緊急時には、躊躇せずに外部機関と連携し、従業員をサポートすることが重要です。
メンタルヘルスサポートを促進するメールのポイント

相談しやすい環境を作るための工夫
従業員がメンタルヘルスの問題を打ち明けやすい環境を作ることは、早期発見と適切なサポートに不可欠です。
メールでサポートを促す際には、以下のような点に注意しましょう。
まず、メールの文面はできるだけ温かく、共感的な tone を意識します。
たとえば、
いつも頑張っている[従業員名]さんのことを、私たちは大切に思っています。
といった言葉を添えることで、心理的な距離を縮めることができます。
次に、相談内容の秘密厳守を徹底することを明確に伝えましょう。
相談内容は決して外部に漏れることはありませんので、ご安心ください。
といった一文を加えることで、安心して相談できる環境をアピールできます。
また、相談しやすい雰囲気を作るために、相談窓口の担当者の顔写真や自己紹介を掲載するのも有効です。
担当者の人柄が伝わることで、従業員はより気軽に相談できるようになるでしょう。
さらに、メール以外にも、チャットや電話など、複数の相談方法を用意することで、従業員の状況や好みに合わせたサポートが可能です。
選択肢を提示することで、より相談しやすい環境を構築できます。
専門機関との連携について言及する
メンタルヘルスの問題は、専門的な知識やサポートが必要となる場合があります。
そのため、メールでメンタルヘルスサポートを促す際には、専門機関との連携について言及することが重要です。
まず、社内カウンセリング制度がある場合は、その利用方法や予約方法を具体的に伝えましょう。
たとえば、
社内カウンセラーの[カウンセラー名]が、[曜日]の[時間]に相談を受け付けています
といった情報を記載します。
次に、外部の相談窓口や医療機関を紹介することも有効です。
専門機関の連絡先やウェブサイトのリンクを掲載することで、従業員がよりスムーズに専門的なサポートを受けられるようにしましょう。
また、従業員が医療機関を受診する際の費用補助制度がある場合は、その内容を具体的に伝えましょう。
医療機関の受診費用を一部補助する制度がありますので、ご希望の方は人事部までお問い合わせください。
といった文言を加えます。
加えて、専門機関と連携していることをアピールすることで、従業員は「会社が自分のメンタルヘルスを真剣に考えてくれている」と感じ、安心して相談できるようになるでしょう。
従業員のメンタルヘルスケア 支援メールまとめ

これまでの内容を振り返り、特に重要なポイントをまとめると、以下の3つが挙げられます。
- メンタルヘルス不調のサインに早期に気づき、適切なサポートを提供すること
- 従業員が安心して相談できる環境をメールを通じて作ること
- 状況に応じたメールの使い分けと、具体的な支援策を提示すること
これらのポイントを踏まえ、日々の業務でメールを活用していきましょう。
まずは、今回の記事を参考に、メンタルヘルスケアに関するメールのテンプレートをいくつか作成してみることをお勧めします。
そうすることで、いざという時にスムーズに対応できるようになるはずです。
従業員の皆さんが心身ともに健康で、それぞれの能力を最大限に発揮できるよう、組織全体でサポートしていきましょう。