【例文あり】非がない場合のクレーム対応はどうする? 誠意が伝わる上手な断り方
非がない場合のクレーム対応方法

「えっ、うちには何の落ち度もないはずなのに…。」
そんな風に、身に覚えのないクレームを受けて困惑した経験はありませんか?
実は私も、以前の職場で同じような状況に何度も直面し、どう対応すればいいのか頭を悩ませていました。
お客様の言い分は理解できるものの、明らかにこちらに非がない場合、どう説明したら納得していただけるかが本当に難しい問題ですよね。
下手に強く反論すれば火に油を注ぎかねませんし、かといって安易に謝罪すれば非を認めたことになってしまう…。
今回は、そんな「非がない場合のクレーム対応」という、非常にデリケートな問題について、私の経験も踏まえながら、具体的な対応方法や考え方のヒントをお伝えしたいと思います。
この記事を読めば、あなたも自信を持って、誠意を伝えながら上手に対応できるようになるはずです。
クレーム対応の基本姿勢 - 非がない場合でも大切なこと

まず大前提として、たとえこちらに非がないと思われるクレームであっても、お客様が何らかの不満や疑問を感じているという事実は受け止めなければなりません。
その上で、どのような姿勢で対応に臨むべきか、基本的なポイントを確認しましょう。
まずは冷静に、お客様の話をしっかり聞く姿勢
クレームを受けた瞬間は、驚きや戸惑い、時には「なぜ?」という怒りの感情が湧いてくるかもしれません。
でも、ここで感情的になってしまっては、問題解決は遠のくばかりです。
まずは深呼吸して、冷静さを保ちましょう。
そして、何よりも大切なのが、お客様の話を最後まで、遮らずにしっかりと聞く「傾聴」の姿勢です。
相手が何に怒っているのか、何に不満を感じているのか、その背景にある事情は何なのか。
注意深く耳を傾けることで、問題の本質が見えてくることがあります。
たとえ内容に同意できない点があったとしても、「まずは聞く」という姿勢を示すことが、信頼関係を築く第一歩になります。
共感の言葉で相手の感情を受け止める
お客様の話を聞く中で、「それは違うのに…」と思う部分があっても、すぐに反論するのは避けましょう。
まずは、「〇〇な点にご不満を感じていらっしゃるのですね」「ご不便をおかけし、申し訳ございません(※状況に応じて)」といった共感の言葉を伝え、相手の感情を受け止めることが大切です。
ここで重要なのは、「謝罪=非を認める」ではないということです。
お客様が不快な思いをされたという「感情」に対して寄り添う姿勢を示すことで、相手の興奮を鎮め、冷静な話し合いができる土壌を作ることができます。
「お気持ちお察しいたします」「ご心配をおかけしました」といった言葉も有効ですね。
事実確認を丁寧に行うことの重要性
お客様の話を一通り聞いた後は、客観的な事実確認が不可欠です。
「いつ」「どこで」「何が」起こったのか、具体的な状況を丁寧にお伺いしましょう。
この時、詰問するような口調にならないよう注意が必要です。
「恐れ入りますが、もう少し詳しく状況をお伺いしてもよろしいでしょうか?」
「〇〇について、確認させていただいてもよろしいでしょうか?」
といった、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
お客様の記憶違いや勘違いである可能性も考えられますし、こちら側の記録やデータと照らし合わせることで、問題の原因が明確になることもあります。
焦らず、一つひとつ事実を積み重ねていくことが、的確な対応への近道です。
なぜ「非がない」と感じるクレームが発生するのか?
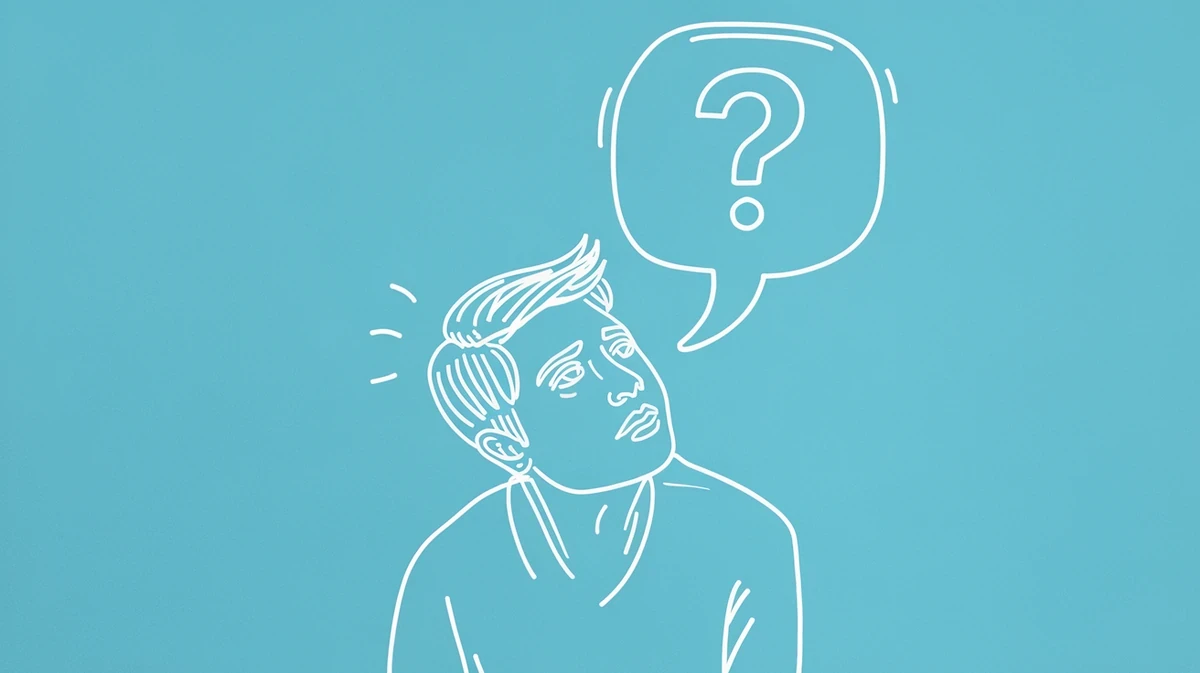
そもそも、なぜこちらに非がないと思われるクレームが発生してしまうのでしょうか?
その原因を探ることで、今後の対策や、より適切な対応方法が見えてきます。
お客様の誤解や期待とのギャップ
最も多い原因の一つが、お客様の誤解や、事前の期待とのギャップです。
例えば、商品の仕様やサービス内容について、お客様が独自に解釈してしまい、実際とは異なる期待を抱いてしまうケースがあります。
「当然〇〇できると思っていたのに、できなかった」
「説明にはこう書いてあったけれど、実際は違った」
こうした声の背景には、お客様側の思い込みや確認不足があるかもしれません。
しかし、同時に、私たちの説明が不十分だったり、誤解を招きやすい表現だったりした可能性も否定できません。
コミュニケーション不足によるすれ違い
日々のコミュニケーションの中で、ちょっとした言葉の行き違いや認識のズレが、後々クレームにつながることも少なくありません。
特に、メールやチャットなど、文字だけのコミュニケーションではニュアンスが伝わりにくく、誤解が生じやすいものです。
丁寧な言葉遣いを心がけていても、相手にとっては冷たく感じられたり、説明が足りないと思われたりすることもあります。
日本特有のビジネス文化として、遠まわしな表現を好む傾向がありますが、それがかえって曖昧さを生み、すれ違いの原因になることも考えられます。
商品・サービスの説明不足や分かりにくさ
商品カタログやウェブサイト、利用規約などの説明が分かりにくかったり、重要な情報が目立たない場所に記載されていたりすると、お客様は「そんなことは知らなかった」「聞いていない」と感じてしまいます。
特に、専門用語が多い説明や、細かすぎる注意書きは、一般のお客様にとっては理解が難しい場合があります。
「誰にでも分かりやすく伝える」という視点が欠けていると、意図せずクレームの種をまいてしまうことになりかねません。
お客様側の個人的な事情や感情
時には、商品やサービスそのものへの不満というよりは、お客様側の個人的な事情や、その時の感情がクレームという形で表出されることもあります。
例えば、たまたま機嫌が悪かった、時間に追われて焦っていた、他のことでストレスを抱えていたなど、様々な要因が考えられます。
もちろん、だからといって理不尽な要求を受け入れる必要はありませんが、クレームの背景にこうした個人的な要因が隠れている可能性も、頭の片隅に置いておくと、より冷静に対応できるかもしれません。
非がない場合の具体的なクレーム対応ステップ

では、実際に非がないクレームを受けた場合、どのような手順で対応を進めれば良いのでしょうか?
具体的なステップを見ていきます。
Step1: 傾聴と共感 - まずは相手の言い分を受け止める
繰り返しになりますが、最初のステップは「聞く」ことです。
お客様が話し終わるまで、じっくりと耳を傾けましょう。
相槌を打ちながら、「なるほど」「そうだったのですね」といった言葉で、聞いている姿勢を示します。
そして、話の内容に対してではなく、お客様が不快に感じている「感情」に対して、
「ご不快な思いをさせてしまい、申し訳ございません」「〇〇な点に不満をお持ちなのですね」といった共感の言葉を伝えます。
この段階では、まだ事実確認や反論はせず、ひたすら受け止めることに徹しましょう。
Step2: 事実確認 - 客観的な情報を集める
お客様の感情が少し落ち着いたタイミングを見計らって、具体的な事実確認に移ります。
「いつ頃のことでしょうか?」
「どのような状況でしたでしょうか?」
「〇〇という認識でよろしいでしょうか?」
など、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識しながら、客観的な情報を収集します。
必要であれば、社内の記録や関連部署にも確認を取り、正確な情報を把握しましょう。
ここでの丁寧な事実確認が、後の説明の説得力を左右します。
Step3: 丁寧な説明 - なぜ非がないと判断したのかを伝える
事実確認の結果、やはりこちらに非がないと判断した場合、その根拠を丁寧にお客様に説明する必要があります。
この時、ただ「非はありません」と突き放すのではなく、「なぜ」そう言えるのか、具体的な理由や証拠を添えて説明することが重要です。
例えば、
「お問い合わせの件について確認いたしましたところ、弊社の記録では〇月〇日に〇〇というご案内をさせていただいておりました。」
「ご利用規約の第〇条に記載の通り、〇〇の場合は保証の対象外となっております。」
といった形で、客観的な事実に基づいて説明します。
専門用語は避け、誰にでも分かる平易な言葉で、冷静に、しかし誠意を持って伝えることを心がけましょう。
メールで説明する場合は、文章が冷たい印象にならないよう、クッション言葉(「恐れ入りますが」「誠に申し訳ございませんが」など)を効果的に使うと良いでしょう。
Step4: 代替案の提示(可能な場合) - 解決に向けた姿勢を示す
非がないと説明した上で、もし可能であれば、何らかの代替案や、お客様の不満を少しでも和らげるための提案ができないか検討しましょう。
例えば、
「今回の件につきましては、弊社の規定によりご希望に沿うことは難しいのですが、代わりに〇〇という方法でしたらご提案できますがいかがでしょうか?」
「今後の改善点として、〇〇について社内で検討させていただきます。」
といった形です。
必ずしも何かを提供する必要はありませんが、「できる範囲で何か力になりたい」という姿勢を示すことで、お客様の納得感を得やすくなります。
ただし、安易に譲歩しすぎると、前例となってしまう可能性もあるため、慎重な判断が必要です。
Step5: 毅然とした態度と謝罪の使い分け - どこで線引きするか
説明を尽くし、代替案も提示したにも関わらず、お客様が納得せず、理不尽な要求を繰り返すような場合は、どこかで線引きをし、毅然とした態度で対応することも必要です。
「これ以上の対応は致しかねます」
「弊社の見解は先ほど申し上げた通りです」
といった言葉で、丁寧ながらもはっきりと断る勇気も時には求められます。
ただし、この際も感情的にならず、あくまで冷静に対応することが重要です。
また、「謝罪」の言葉の使い分けも意識しましょう。
お客様の感情に対しては「ご不快な思いをさせて申し訳ございません」と謝罪しても、事実関係については「弊社の規定により、ご要望にはお応えできません」と明確に伝える、という使い分けが必要です。
非がないクレーム対応で避けるべきNG行動
良かれと思って取った行動が、かえって事態を悪化させてしまうこともあります。
非がない場合のクレーム対応で、絶対に避けるべきNG行動を確認しておきましょう。
頭ごなしに否定する
お客様の話を聞かずに、「そんなはずはありません」「それはお客様の勘違いです」などと、頭ごなしに否定するのは最悪の対応です。
相手の感情を逆なでし、さらなる怒りを買ってしまうだけです。
まずは受け止める姿勢が大切です。
感情的になる、反論する
相手の言葉にカッとなって、感情的に言い返したり、強い口調で反論したりするのも絶対に避けましょう。
売り言葉に買い言葉となり、収拾がつかなくなってしまいます。
常に冷静さを保ち、プロフェッショナルとしての対応を心がけてください。
言い訳や責任転嫁をする
「〇〇部署の担当者が言ったことなので」「それは以前の担当者のミスで」といった言い訳や、他部署・他者への責任転嫁も、お客様からの信頼を失う原因になります。
会社として、組織として、責任ある対応を示すことが重要です。
あやふやな回答でごまかす
事実確認が不十分なまま、「たぶん」「おそらく」といった曖昧な言葉で回答したり、その場しのぎでごまかそうとしたりするのもNGです。
後で辻褄が合わなくなり、さらに大きな問題に発展する可能性があります。
分からないことは正直に「確認して折り返しご連絡します」と伝え、正確な情報に基づいて対応しましょう。
非がないクレームを未然に防ぐためのヒント

そもそも、非がないクレームが発生しないように、日頃からできる対策もあります。
いくつかヒントをご紹介します。
事前の丁寧な説明と期待値コントロール
商品やサービスを提供する前に、その内容、仕様、料金、利用規約、注意点などを、お客様に分かりやすく、丁寧に説明することが最も重要です。
メリットだけでなく、デメリットや制限事項についても正直に伝えることで、お客様の過度な期待を防ぎ、「こんなはずじゃなかった」というギャップを減らすことができます。
これを「期待値コントロール」と呼びます。
お客様が理解・納得した上で利用を開始できるように、事前のコミュニケーションを大切にしましょう。
分かりやすい資料やマニュアルの整備
口頭での説明に加えて、分かりやすい資料やマニュアルを用意しておくことも有効です。
専門用語を避け、図やイラストを活用するなど、誰が見ても理解しやすいように工夫しましょう。
ウェブサイトのFAQ(よくある質問)セクションを充実させるのも良い方法です。
お客様が疑問を感じたときに、自己解決できる手段を提供することで、問い合わせやクレームの発生を抑制できます。
定期的なコミュニケーションと関係構築
特に継続的な取引があるお客様とは、日頃から定期的にコミュニケーションを取り、良好な関係を築いておくことが大切です。
ちょっとした疑問や不満を、クレームに至る前に気軽に相談してもらえるような関係性があれば、大きなトラブルに発展するのを防ぐことができます。
挨拶や近況報告など、些細なことでもコミュニケーションを積み重ねることが、信頼関係の基盤となります。
クレーム対応の負担を軽減するために

クレーム対応は、精神的にも時間的にも大きな負担がかかる業務です。
特に、人手不足が深刻な日本の労働市場においては、担当者一人にかかる負荷は増大しがちです。
少しでもその負担を軽減するための工夫も考えてみましょう。
対応マニュアルの整備と共有
非がない場合のクレームを含め、様々なケースを想定した対応マニュアルを作成し、社内で共有しておくことは非常に有効です。
どのような手順で対応するか、どのような言葉遣いをすべきか、判断基準などを明確にしておくことで、担当者による対応のばらつきを防ぎ、誰もが一定の品質で対応できるようになります。
また、新人教育にも役立ち、業務の属人化を防ぐことにもつながります。
対応記録の重要性と活用方法
クレーム対応の内容は、必ず記録に残しておきましょう。
いつ、誰から、どのような内容のクレームがあり、どのように対応し、結果どうなったのかを詳細に記録しておくことで、同様のケースが発生した場合の参考になります。
また、記録を分析することで、クレームが発生しやすい傾向や、商品・サービスの改善点が見えてくることもあります。
クレームは、見方を変えれば、業務改善のための貴重なヒントの宝庫なのです。
AIを活用したメール作成支援ツールの可能性
クレーム対応の中でも、特にメールでの返信は、言葉遣いやニュアンスに細心の注意が必要で、時間も労力もかかりますよね。
丁寧な説明を心がけたいけれど、文章を考えるのが苦手だったり、時間がなかったり…。
そんな悩みを解決するのが、『代筆さん』です。
代筆さんは、簡単な指示や要件を伝えるだけで、AIが状況に応じた丁寧なビジネスメールを作成してくれるWebサービスです。
例えば、お客様からのクレームメールの内容と、「こちらに非はないが、丁寧にお断りしたい」という指示を入力すれば、AIが適切な断り方のメール文面を提案してくれます。
もちろん、AIが作成した文章をそのまま使うのではなく、ご自身の言葉で修正を加えることも可能です。
何度も同じような説明を繰り返す必要がある場合など、定型的な返信文を考える手間を大幅に削減できます。
また、日本語で指示を出しても、相手の言語に合わせてメールを作成してくれる機能もあるので、海外のお客様からのクレーム対応にも役立つかもしれません。
人が操作するので、完全自動化というわけにはいきませんが、日々のメール作成の負担を軽減し、より重要な業務に集中するためのサポートツールとして、活用を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ - 非がないクレーム対応を乗り越える

今回は、「非がない場合のクレーム対応」という難しいテーマについて考えてきました。
大切なのは、まず冷静に相手の話を聞き、感情に寄り添うこと。
そして、客観的な事実に基づいて、丁寧になぜ非がないのかを説明することです。
毅然とした態度も時には必要ですが、最後まで誠意を持って対応する姿勢が、最終的な信頼につながります。
クレーム対応は大変ですが、避けては通れない道でもあります。
対応マニュアルの整備や記録の活用、そして便利なツールの導入も検討しながら、少しでも負担を減らし、前向きに取り組んでいきましょう。
もし、クレーム対応のメール作成に時間がかかっている、もっと効率化したいと感じているなら、AIメール作成支援ツール代筆さんを試してみるのも一つの手です。
簡単な指示で、丁寧なビジネスメールを作成する手助けをしてくれます。
この記事が、あなたのクレーム対応の悩みを少しでも軽くする一助となれば幸いです。




