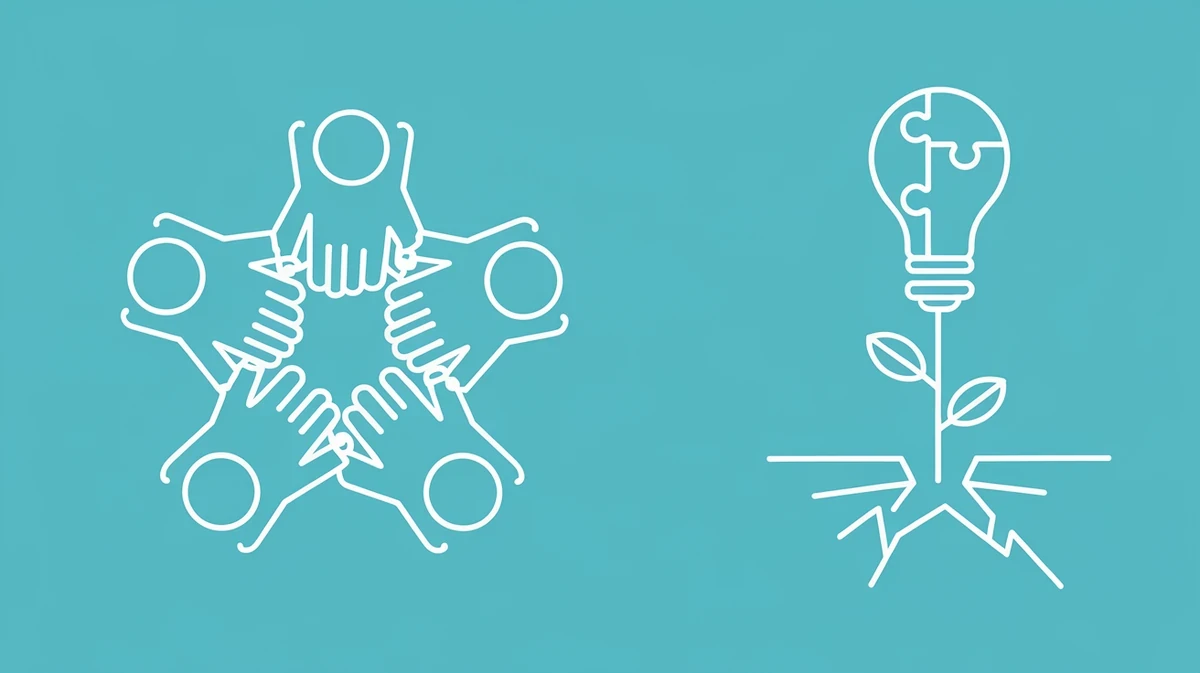機密情報メールのリスク回避 5つの鉄壁セキュリティ対策
機密情報の取り扱いに注意

ビジネスシーンにおいて、メールは欠かせないコミュニケーションツールです。
しかし、その利便性と引き換えに、機密情報の漏洩という深刻なリスクも潜んでいます。
お客様や取引先の情報、社内の重要な経営情報など、取り扱う情報によっては、ひとたび漏洩すれば企業の信頼失墜、損害賠償請求、果ては事業継続の危機にまで発展しかねません。
「自分は大丈夫」という過信は禁物です。
メールの誤送信、添付ファイルのウイルス感染、不正アクセスなど、情報漏洩の原因は多岐にわたります。
日々の業務で何気なく使っているメールに、どれほどのリスクが潜んでいるのか、改めて認識する必要があるのではないでしょうか。
この記事では、ビジネスメールにおける機密情報漏洩のリスクを具体的に解説し、その上で、安全に情報を送受信するための対策を5つのパートに分けてご紹介します。
メールセキュリティの基本から、社内規定の整備、添付ファイルの取り扱い、誤送信防止策まで、実践的な内容を網羅しています。
本記事を読むことで、機密情報メールのリスクを正しく理解し、明日からすぐに実践できるセキュリティ対策を習得できます。
ぜひ、ご自身の、そして組織全体の情報セキュリティ意識向上にお役立てください。
ビジネスメールにおける機密情報漏洩のリスクとは
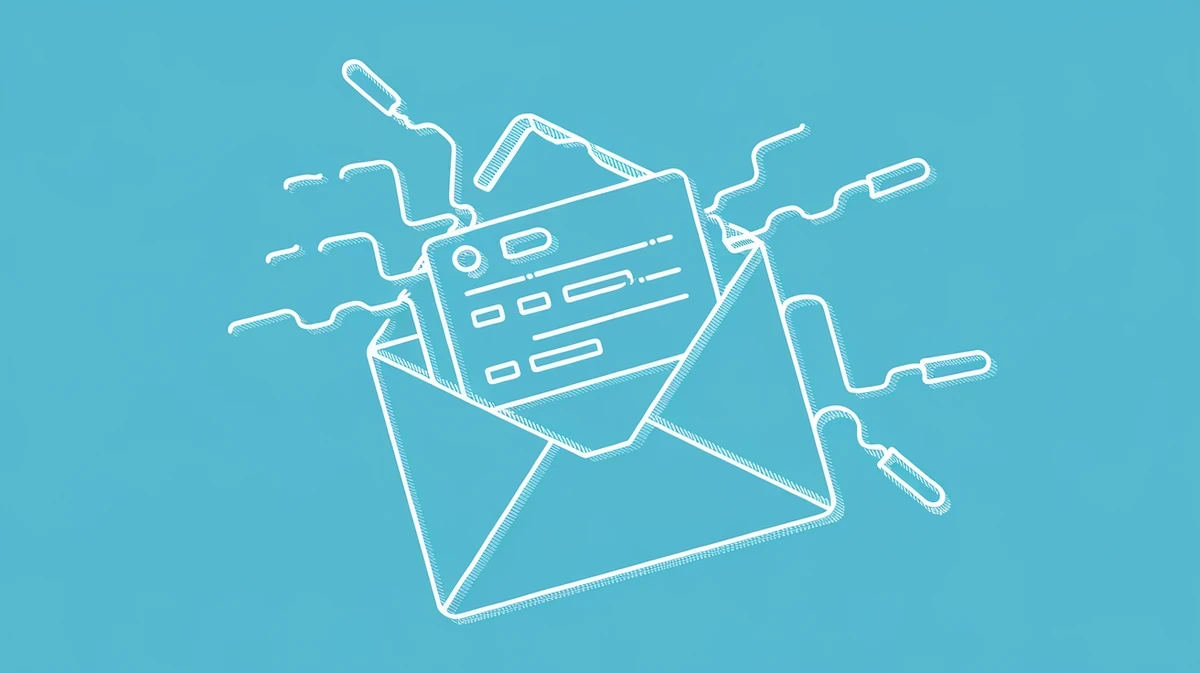
まずは、ビジネスメールにおける情報漏洩のリスクについて、具体的に見ていきましょう。
日常業務に潜む危険性を認識することが、対策の第一歩となります。
メール誤送信による情報漏洩の危険性
メールの誤送信は、情報漏洩の最も多い原因の一つです。
宛先の入力ミス、CCとBCCの使い分けミス、自動補完機能による意図しない宛先選択など、誰にでも起こりうる人的ミスが、重大な情報漏洩につながる可能性があります。
例えば、顧客情報を誤って別の顧客に送信してしまった場合、個人情報保護法違反に問われるだけでなく、企業の信用問題にも発展します。
そのような事態を避けるためにも、送信前の確認は徹底しましょう。
添付ファイル経由でのウイルス感染
メールに添付されたファイルを開くことで、ウイルスに感染するリスクも軽視できません。
たとえば、Emotet(エモテット)と呼ばれるマルウェアが、WordやExcelなどのOfficeファイルを装って添付され、感染を広げる事例が多発しています。
ウイルスに感染すると、PC内の情報が盗み取られたり、他のPCへの攻撃の踏み台にされたりする可能性があります。
機密情報が外部に漏洩するだけでなく、社内システム全体が停止してしまうなど、事業活動に甚大な影響を及ぼすことも考えられます。
例文:ウイルス感染を警告する社内メール
件名:【重要】不審なメールにご注意ください
社員の皆様
情報システム部より、不審なメールに関する注意喚起です。
最近、[件名]や[差出人]を装った不審なメールが多数確認されています。これらのメールには、[ファイル形式]のファイルが添付されており、開封するとウイルスに感染する恐れがあります。
不審なメールを受信した場合は、絶対に添付ファイルを開かず、速やかに情報システム部までご連絡ください。
ご協力よろしくお願いいたします。
上記は、社内でウイルス感染の疑いがある場合に、注意喚起を行うメールの例文です。
不審なメールは開かない、添付ファイルは安易に開かない、という意識を徹底しましょう。
不正アクセスによるメール盗み見のリスク
ID・パスワードの漏洩や、脆弱なネットワーク環境を利用することによる不正アクセスも、情報漏洩の大きなリスクです。
悪意のある第三者にメールアカウントを乗っ取られると、過去のメールを盗み見されたり、なりすましメールを送信されたりする可能性があります。
特に、Webメールを公共のWi-Fiなどセキュリティが低い環境で利用する場合は、通信内容が傍受される危険性が高まります。
例文:不正アクセスを警告するメール
件名:【重要】アカウントの不正利用に関する警告
[サービス名]をご利用いただきありがとうございます。
お客様のアカウントにおいて、[日時]に[場所]から不審なアクセスが確認されました。
お客様ご自身によるアクセスの場合は問題ございませんが、身に覚えのない場合は、速やかにパスワードを変更し、[サポート窓口]までご連絡ください。
今後とも[サービス名]をよろしくお願いいたします。
上記は、サービスプロバイダからユーザーに対して、不正アクセスの可能性を警告するメールの例文です。
このような警告を受けたら、速やかにパスワードを変更するなどの対策を取りましょう。
機密情報を安全に送るためのメールセキュリティ対策

前述のようなリスクを回避し、ビジネスメールで機密情報を安全にやり取りするためには、具体的なセキュリティ対策が不可欠です。
ここでは、すぐに実践できる効果的な対策を3つご紹介します。
メール本文と添付ファイルの暗号化
機密情報をメールで送る際、最も重要な対策の一つが「暗号化」です。
暗号化とは、特定のルール(鍵)を知っている人だけが元の内容を読めるように、データを変換することです。
万が一、メールが盗み見されたり、誤送信されたりしても、内容を解読されるリスクを大幅に減らせます。
- メール本文の暗号化: S/MIME(Secure Multipurpose Internet Mail Extensions)などの暗号化方式を利用することで、メールソフト上で簡単にメール本文を暗号化できます。
- 添付ファイルの暗号化: ファイル自体を暗号化したり、パスワード付きのZIPファイルに圧縮したりすることで、添付ファイルも保護できます。
例文メール本文の暗号化
件名:【暗号化】〇〇プロジェクトに関するご報告
株式会社[会社名]
[部署名] [役職] [氏名]様いつもお世話になっております。
株式会社△△の[氏名]です。〇〇プロジェクトに関するご報告を、本メールに添付いたします。
(このメールはS/MIMEで暗号化されています)
[署名]
メールソフトで暗号化設定を有効にすると、上記のように自動的に暗号化されたメールが送信されます。
受信者も同じ暗号化方式に対応したメールソフトを使用していれば、特別な操作なしに復号して内容を確認できます。
パスワード付きZIPファイルの適切な利用
添付ファイルを暗号化する際、広く利用されているのがパスワード付きZIPファイルです。
しかし、パスワードの取り扱いを誤ると、かえってセキュリティリスクを高めてしまう可能性があります。
- パスワードはメールとは別の手段で伝える: 電話やチャットなど、メールとは異なる経路でパスワードを伝えることで、メールとパスワードが同時に漏洩するリスクを回避します。
- 推測されにくいパスワードを設定する: 名前、誕生日、単純な数字の羅列など、推測されやすいパスワードは避け、複雑な文字列を設定しましょう。
- パスワード付きZIPファイルは過信しない: ZIPファイルの暗号化強度は、使用する圧縮ソフトや設定によって異なります。
より強固な暗号化が必要な場合は、専用のファイル暗号化ソフトの利用も検討しましょう。
例文パスワード付きZIPファイル送付時の注意喚起
件名:〇〇に関する資料(パスワード付きZIPファイル)
[会社名]
[部署名] [役職] [氏名]様いつもお世話になっております。
株式会社△△の[氏名]です。〇〇に関する資料を添付ファイルにてお送りいたします。
添付ファイルはパスワード付きZIPファイルで保護しております。
パスワードは後ほど、別途ご連絡いたします。お手数をおかけしますが、ご確認よろしくお願いいたします。
[署名]
このように、パスワードを別の手段で伝える旨を明記することで、受信者に注意を促すことができます。
送信前の宛先確認とダブルチェックの徹底
どんなに高度なセキュリティ対策を施しても、メールの誤送信を防ぐことはできません。
誤送信は、情報漏洩の大きな原因の一つです。
送信前に、宛先(To、Cc、Bcc)を必ず確認し、ダブルチェックを徹底しましょう。
- 宛先を再確認する: 氏名、会社名、メールアドレスに間違いがないか、送信前に必ず確認しましょう。
- 自動補完機能に注意する: メールアドレスの自動補完機能は便利ですが、意図しない宛先が選択されている可能性もあります。
- 複数人で確認する: 重要なメールは、自分だけでなく、他の人にも宛先や内容を確認してもらうと、より安心です。
例文送信前の宛先確認依頼
件名:【要確認】〇〇に関する資料(送信前確認)
[上司/同僚の名前]さん
お疲れ様です。
〇〇に関する資料を、[宛先]様に送付する予定です。
添付ファイルの内容と宛先に間違いがないか、ご確認いただけますでしょうか。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
[署名]
このように、送信前に同僚や上司に確認を依頼することで、誤送信のリスクを減らすことができます。
これらの対策は、機密情報をメールで安全に送るための基本的なものです。
しかし、セキュリティ対策は、組織全体で取り組む必要があります。
次のセクションでは、情報漏洩を防ぐための社内規定とメール運用ルールについて解説します。
情報漏洩を防ぐ 社内規定とメール運用ルール

ここまでは、個々のメール送信におけるセキュリティ対策を見てきましたが、組織全体で情報漏洩を防ぐためには、より包括的なアプローチが必要です。
そこで重要になるのが、社内規定とメール運用ルールの整備です。
機密情報の定義と取り扱いに関する社内規定
まず、何が「機密情報」にあたるのかを明確に定義しましょう。
顧客情報、財務情報、人事情報、新製品の開発情報など、企業によって機密情報の範囲は異なります。
- 機密情報の定義: 具体的にどのような情報が機密情報に該当するのかを明文化します。
- 取り扱いレベルの設定: 機密性のレベルに応じて、取り扱い方法(保管場所、アクセス権限、送信方法など)を規定します。
- 罰則規定: 情報漏洩が発生した場合の罰則を明確にすることで、従業員の意識向上を図ります。
これらの規定を設けることで、従業員はどの情報が重要で、どのように扱えば良いのかを理解できます。
メール利用に関するセキュリティポリシーの策定
次に、メール利用に関するセキュリティポリシーを策定します。
これは、メールを安全に利用するためのルールブックのようなものです。
- 私用メールアドレスの利用制限: 業務上のやり取りに個人のメールアドレスを使用することを禁止します。
- 添付ファイルの制限: 送受信できるファイルの種類やサイズを制限します。
- パスワードポリシー: 強固なパスワードの設定を義務付け、定期的な変更を促します。
- 誤送信防止策: 送信前の宛先確認の徹底や、ダブルチェックの義務化などを規定します。
例文:社内メール利用規定(一部)
件名:社内メール利用規定(一部抜粋)
従業員各位
平素は格別のご尽力、誠にありがとうございます。
この度、情報セキュリティ強化のため、下記の通りメール利用に関する規定を一部改定いたしました。
- 業務上のやり取りには、会社が貸与するメールアドレスのみを使用すること。
- 機密情報を含むメールを送信する際は、必ず上長の承認を得ること。
- 添付ファイルのサイズは10MB以内とし、それを超える場合はクラウドストレージを利用すること。
- 送信前に宛先を必ず確認し、誤送信防止に努めること。
詳細は社内ポータルサイトの規定集をご確認ください。
この例文は、社内メール利用規定の一部を抜粋したものです。
実際の運用に合わせて、より詳細な規定を定める必要があります。
従業員へのセキュリティ教育と意識向上
どんなに優れた規定やルールを作っても、従業員がそれを理解し、守らなければ意味がありません。
定期的なセキュリティ教育を実施し、従業員の意識向上を図ることが重要です。
- 研修の実施: 情報セキュリティに関する研修を定期的に実施し、最新の脅威や対策について周知します。
- 標的型メール訓練: 実際に標的型メールを模擬的に送信し、従業員の対応をテストします。
- 注意喚起: 社内報やポータルサイトなどを通じて、継続的に注意喚起を行います。
これらの施策を通じて、従業員一人ひとりがセキュリティ意識を高め、組織全体のセキュリティレベルを向上させることが可能になります。
さて、ここまでは組織的な対策について解説してきましたが、添付ファイルそのもののセキュリティ対策も重要です。
次の章では、「添付ファイルのセキュリティ強化 3つのポイント」について詳しく見ていきましょう。
添付ファイルのセキュリティ強化 3つのポイント

ここまでは、社内規定やメール運用ルールといった、組織全体での情報漏洩対策について解説してきました。
しかし、ルールが整備されていても、個々のメール利用者がセキュリティ意識を高く持たなければ、情報漏洩のリスクを完全に排除することはできません。
特に、添付ファイルはウイルス感染の侵入口になりやすく、また誤送信による情報漏洩のリスクも高いため、より一層の注意が必要です。
そこで、ここでは添付ファイルのセキュリティを強化するための3つのポイントを具体的に解説します。
ウイルス対策ソフトの導入と最新状態の維持
ウイルス対策ソフトの導入は、添付ファイル経由のウイルス感染を防ぐための基本中の基本です。
ウイルス対策ソフトは、メールに添付されたファイルがウイルスに感染していないかをスキャンし、感染している場合は警告を表示したり、自動的に駆除したりします。
ウイルス対策ソフトを使うときは、このような点に注意が必要です。
最新状態の維持
ウイルスは日々進化しているため、ウイルス対策ソフトの定義ファイル(ウイルス情報)を常に最新の状態に保つことが重要です。
多くのソフトは自動更新機能を備えているので、有効にしておきましょう。
OSやソフトウェアのアップデートも重要
ウイルスはOSやソフトウェアの脆弱性(セキュリティ上の欠陥)を突いてくることが多いため、OSや利用しているソフトウェアも常に最新の状態に保つようにしましょう。
クラウドストレージの活用とファイル共有
機密性の高いファイルをメールで直接送るのではなく、クラウドストレージを活用する方法も有効です。
クラウドストレージとは、オンライン上にファイルを保存・共有できるサービスです。
代表的なサービスとしては、Google Drive、Dropbox、OneDriveなどがあります。
クラウドストレージのメリット
- 誤送信対策: ファイルのURLを共有するため、ファイルそのものを誤送信するリスクを減らせます。
- アクセス制限: 共有相手やアクセス権限(閲覧のみ、編集可など)を細かく設定できます。
- バージョン管理: ファイルの変更履歴が残るため、誤って上書きした場合でも過去のバージョンに戻すことができます。
クラウドストレージの注意点
クラウドストレージ自体のセキュリティ対策も重要です。
信頼できるサービスを選び、パスワードを適切に管理しましょう。
ファイル形式によるリスクの違いと対策
ファイル形式によって、ウイルス感染のリスクや情報漏洩の危険性が異なります。
ファイルごとの注意点を紹介します。
実行形式ファイル(.exe, .batなど)
プログラムを実行するファイル形式であり、ウイルスが仕込まれている可能性が高いため、原則として送受信を避けるべきです。
マクロ付きファイル(.docm, .xlsmなど)
マクロ(自動処理プログラム)を含むことができるファイル形式であり、マクロウイルスに感染するリスクがあります。
信頼できる相手からのファイル以外は、マクロを無効にするか、開かないようにしましょう。
PDFファイル
比較的安全なファイル形式とされていますが、JavaScriptなどのスクリプトが埋め込まれている場合は、注意が必要です。
不審なPDFファイルは開かないようにしましょう。
ZIPファイル
パスワード付きで暗号化することで、セキュリティを高めることができますが、パスワードが漏洩すると意味がありません。
パスワードの管理には十分注意し、メールとは別の手段で伝えるようにしましょう。
これらのポイントを踏まえ、添付ファイルを安全に取り扱うことで、情報漏洩のリスクを大幅に低減できます。
しかし、どんなに対策を講じても、メールの誤送信は起こりうるものです。
次は、メール誤送信を防ぐための具体的な方法について見ていきましょう。
メール誤送信を防ぐための具体的な方法

ここまで、添付ファイル自体のセキュリティ対策について解説してきました。
しかし、どんなにファイルを保護しても、誤った宛先に送ってしまっては意味がありません。
ここでは、メールの誤送信を防ぐための具体的な方法をいくつかご紹介します。
これらの対策は、個人の努力だけでなく、組織全体で取り組むことで、より効果を発揮します。
送信遅延機能の活用
多くのメールソフトやサービスには、送信ボタンを押してから実際にメールが送信されるまで、一定時間猶予を設ける「送信遅延機能」が備わっています。
この機能を活用することで、送信直後に誤りに気づいた場合、送信を取り消すことができます。
送信遅延機能のメリット
- 送信ボタンを押した後に、宛先や内容の誤りに気づいても、取り消せる可能性がある。
- 落ち着いて最終確認をする時間的余裕が生まれる。
- 誤送信による情報漏洩のリスクを低減できる。
送信遅延機能の設定例
多くのメールソフトでは、「設定」メニューから送信遅延機能を有効化し、遅延時間を秒単位で設定できます。
例えば、Gmailの場合は、「設定」>「全般」>「送信取り消し」から設定可能です。
BCCとCCの適切な使い分け
メールアドレスを宛先に入力する際、TO、CC、BCCの使い分けも重要です。
特に、多数の宛先に一斉送信する場合は、BCCを適切に利用することで、受信者同士のメールアドレスを保護し、情報漏洩のリスクを低減できます。
例文:社外への一斉送信
件名:【ご案内】新商品発表会のお知らせ
[宛先]様
いつもお世話になっております。[会社名]の[氏名]です。
この度、弊社では新商品発表会を開催する運びとなりました。
つきましては、下記の通りご案内申し上げます。
[詳細]
ご多忙の折とは存じますが、ぜひご来場賜りますようお願い申し上げます。
この例文では、宛先にBCCを使用することを想定しています。
BCCを使用することで、受信者はお互いのアドレスを知ることができません。
CCとBCCの使い分け
- TO: メインの宛先。返信を期待する相手。
- CC: 情報を共有したい相手。TOの宛先の人にも、CCに誰が入っているか分かる。
- BCC: 他の受信者にアドレスを知られたくない相手。TOやCCの宛先の人には、BCCに誰が入っているか分からない。
メールソフトの誤送信防止機能
最近のメールソフトには、誤送信を防ぐための様々な機能が搭載されています。
例えば、以下のような機能があります。
- 宛先確認ダイアログ: 送信前に宛先を再確認するダイアログを表示する。
- 送信ドメイン制限: 特定のドメイン以外への送信を制限する。
- 添付ファイル警告: 添付ファイルがある場合に、警告を表示する。
- 外部ドメインへの警告: 社外ドメインへの送信時に警告を表示する。
これらの機能を有効にすることで、うっかりミスによる誤送信を大幅に減らすことができます。
例文:社内向けメールで、社外ドメインに誤送信した場合の警告
件名:[件名]
[宛先]様
[本文]
警告:社外ドメインへの送信が含まれています。宛先を再度確認してください。
上記は、メールソフトが社外ドメインへの送信を検知し、警告を表示する例です。
これらの対策を組み合わせることで、メール誤送信のリスクを大幅に低減できます。
しかし、最も重要なのは、送信前に必ず宛先と内容をダブルチェックする習慣を身につけることです。
機密情報メールの安全な取り扱いとセキュリティ対策 まとめ

ここまで、機密情報メールのリスクとその対策について解説してきました。
以下の点を意識することで、情報漏洩のリスクを大幅に減らせます。
- メールと添付ファイルの暗号化、パスワード設定の徹底。
- 社内規定とセキュリティポリシーの順守、従業員教育。
- 送信遅延やBCC/CCの活用、メールソフトの誤送信防止機能の利用。
まずは、ご自身のメール設定を見直し、送信遅延機能を有効にすることから始めてみてはいかがでしょうか。
日々の業務で機密情報を安全に取り扱い、信頼を築いていきましょう。
小さな心がけと継続的な取り組みが、大きな安心につながります。