クレーム対応記録の効果的な方法と活用術|再発防止と顧客満足度向上へ
クレーム対応内容の効果的な記録方法とその活用

クレーム対応って、本当に精神的にも時間的にも負担が大きいですよね。
お客様の怒りや不満を直接受け止めなければならないですし、丁寧な言葉遣いや適切な対応が求められます。
「また同じようなクレームが来てしまった…」
「対応内容を後から思い出せない…」
「他の担当者がどう対応したのか分からない…」
こんな悩みを抱えていませんか?
実は私も、以前はクレーム対応の記録を面倒に感じて、つい後回しにしてしまうことがありました。
でも、記録をしっかり取るようになってから、驚くほど業務が改善されたんです。
今回は、そんな経験も踏まえながら、クレーム対応の記録がいかに重要か、そしてその記録をどう活かせばいいのか、具体的な方法をあなたにお伝えします。
この記事を読めば、クレーム対応記録の悩みが解消され、クレームを単なる「厄介事」ではなく、あなたを成長させる「貴重なヒント」に変えることができるはずです。
なぜクレーム対応の記録が重要なのか?

クレーム対応が終わると、ほっとして、すぐに記録を残すのを忘れてしまいがちですよね。
でもこの記録こそが、今後のビジネスをより良くするための宝の山なんです。
なぜクレーム対応の記録がそんなに重要なのでしょうか?
いくつか理由を見ていきましょう。
同じクレームの再発を防ぐために
「前にも同じような問い合わせがあった気がする…」と感じたことはありませんか?
記録がなければ、その「気がする」は確信に変わりませんし、具体的な原因究明や対策も立てられません。
クレームの内容や原因、そしてどのような対応で解決したのかを記録しておくことで、同じ問題が繰り返し発生するのを防ぐための具体的なアクションを起こせるようになります。
例えば、特定の製品に関するクレームが多ければ製品改良のヒントになりますし、特定の手順で問題が起きていればマニュアルの見直しにつながります。
記録は、いわば「転ばぬ先の杖」のようなものですね。
対応品質の向上と均一化のために
クレーム対応は、担当者によって対応の質にばらつきが出てしまいがちです。
ベテランの担当者はうまく対応できても、経験の浅い担当者は戸惑ってしまうかもしれません。
過去の対応記録があれば、それを参照することで、誰が対応しても一定水準以上の、質の高い対応ができるようになります。
どのような言葉遣いが効果的だったか、どんな提案が受け入れられたかなど、成功事例も失敗事例も、すべてが貴重な学びとなります。
チーム全体で対応品質を底上げし、均一化するためにも、記録は欠かせないツールなのです。
顧客理解を深める貴重な情報源として
クレームは、お客様が何に不満を感じ、何を期待しているのかを知る絶好のチャンスです。
表面的には怒りや不満として現れていても、その奥には「もっとこうしてほしい」「こうだったら良かったのに」という本音が隠れていることが多いのです。
記録を通して、お客様の声(VOC: Voice of Customer)を丁寧に拾い上げて分析することでお客様が本当に求めていることが見えてきます。
これは新商品開発やサービス改善においても、非常に価値のある情報源となります。
お客様の期待を超えるサービスを提供するためにも、クレーム記録は大切にしたいですね。
法的なリスクに備えるために(軽く触れる程度)
あまり考えたくないことですが、クレームが深刻化し、法的な問題に発展する可能性もゼロではありません。
万が一そのような事態になった場合、いつ・誰が・どのような対応をしたのか、客観的な記録があることは、自社を守る上で非常に重要になります。
「言った」「言わない」の水掛け論を避け、事実に基づいた冷静な対応をするためにも、正確な記録は不可欠です。
日本のビジネス文化における記録の意義
日本のビジネスシーンでは、特に「丁寧さ」や「経緯の説明責任」が重視される傾向がありますね。
クレーム対応においても、「いつ、どのようなお問い合わせをいただき、弊社としてこのように対応いたしました」という経緯をきちんと説明できることは、お客様からの信頼を得る上で大切です。
また、社内での報告(報連相)においても、記録があればスムーズかつ正確に情報を共有できます。
上司や関係部署に状況を説明する際にも、客観的な記録は説得力を持ちます。
記録を残すことは、日本のビジネス文化の中で求められる「誠実さ」を示すことにもつながるのです。
効果的なクレーム記録に必要な項目
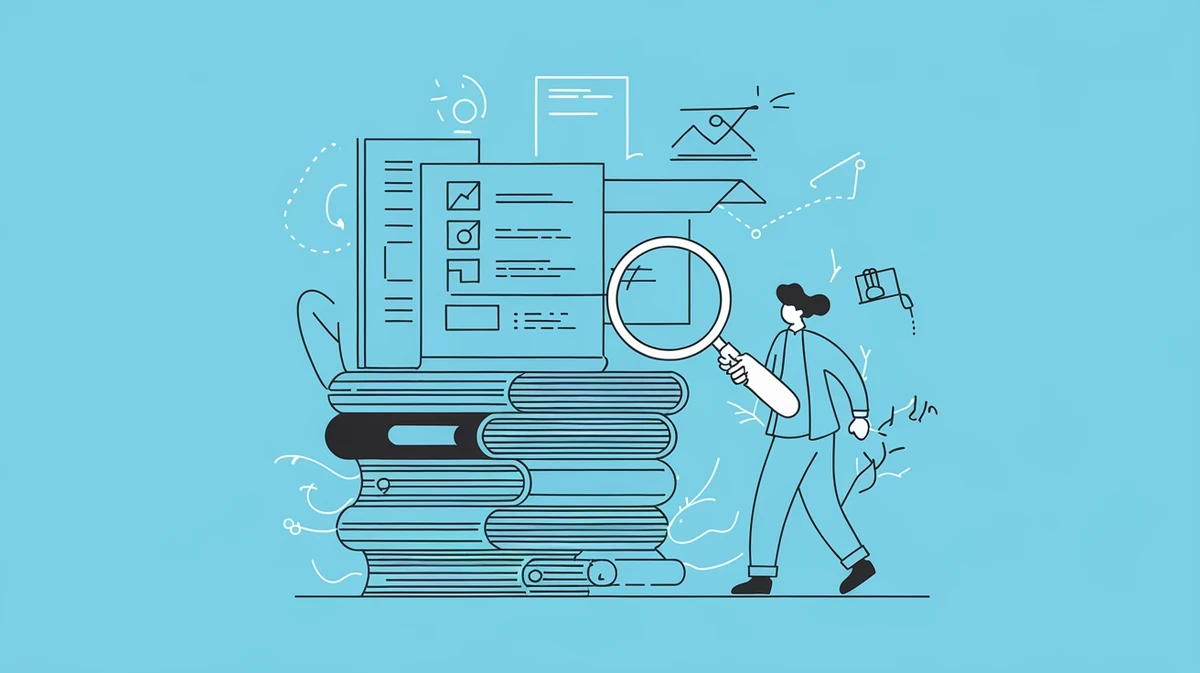
では、具体的にどのような情報を記録しておけば、後で役に立つのでしょうか?
ただ闇雲に記録しても、情報が整理されていなければ活用は難しいですよね。
ここでは、効果的なクレーム記録に含めるべき基本的な項目をご紹介します。
基本情報(日時、顧客情報、受付担当者など)
まずは、いつ、誰からのクレームだったのかを明確にする基本情報です。
- 受付日時: クレームを受けた正確な日時。
- 顧客情報: 氏名、連絡先(電話番号、メールアドレスなど)、可能であれば顧客IDなど。
- 受付チャネル: 電話、メール、対面、Webフォームなど、どの経路でクレームがあったか。
- 受付担当者: 最初にクレームを受けた担当者の氏名。
これらの情報は、後で特定のクレームを検索したり、対応の経緯を追跡したりする際に必須となります。
クレーム内容の詳細(いつ、どこで、何が、どのように)
クレームの核心部分です。
できるだけ具体的に、客観的な事実を記録することが重要です。
- 発生日時・場所: 問題が発生した具体的な日時や場所(店舗名、Webサイトのページなど)。
- 対象: 問題となった商品名、サービス名、担当者名など。
- 具体的な内容: 何が、どのように問題だったのかを具体的に記述します。顧客が話した言葉をそのまま引用するのも有効な場合があります。
- 発生状況: クレームが発生した際の具体的な状況や背景。
曖昧な表現を避け、「5W1H」(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識して記録すると、状況が正確に伝わります。
顧客の要望や感情(何を求めているか、怒りの度合いなど)
お客様がクレームを通して何を求めているのか、そしてどのような感情状態にあるのかを記録することも大切です。
- 顧客の要望: 具体的に何を要求しているか(謝罪、返金、交換、改善など)。
- 感情の状態: 非常に怒っている、不満を感じている、困惑しているなど、顧客の感情的なトーン。
- 期待: 問題解決に対してどのような期待を持っているか。
お客様の感情に寄り添った対応をするため、そして適切な解決策を見つけるためにも、この情報は非常に役立ちます。
ただし、記録する際は主観的な憶測ではなく、顧客の言葉や態度から客観的に判断できる範囲で記述しましょう。
対応経緯(初期対応、担当者、提案内容、解決策)
クレームを受けてから解決に至るまでのプロセスを時系列で記録します。
- 初期対応: 最初にどのような対応を行ったか(傾聴、共感、謝罪など)。
- 担当者の変更: 対応を引き継いだ場合、その担当者名と日時。
- 調査内容: 問題の原因究明のために行った調査とその結果。
- 提案内容: 顧客に提示した解決策や代替案。
- 交渉経緯: 解決策について顧客とどのようなやり取りがあったか。
この記録があることで、対応の進捗状況を把握しやすくなり、途中で担当者が変わってもスムーズな引き継ぎが可能になります。
最終的な結果と顧客の反応
クレーム対応がどのように終結したのか、そしてその結果に対するお客様の反応を記録します。
- 最終的な解決策: 合意に至った具体的な解決内容。
- 解決日時: クレームが解決した日時。
- 顧客の反応: 解決策に対する顧客の満足度や反応(納得した、不満が残っているなど)。
- 追加対応: アフターフォローなど、今後必要な対応があれば記載。
対応が成功したのか、それとも課題が残ったのかを客観的に評価することで、次に活かすための重要な情報となります。
今後の対策や教訓
今回のクレーム対応から得られた学びや、今後の再発防止策を記録します。
- 原因分析: クレームが発生した根本的な原因は何か。
- 再発防止策: 同じ問題を防ぐために、具体的にどのような対策を講じるか(プロセスの見直し、マニュアル改訂、従業員教育など)。
- 担当者の所感: 対応を通して感じたことや、改善点などの個人的な気づき(任意)。
この項目をしっかり記録することで、クレームを単なる処理で終わらせず、組織全体の改善につなげることができます。
クレーム記録を「活用」するためのポイント
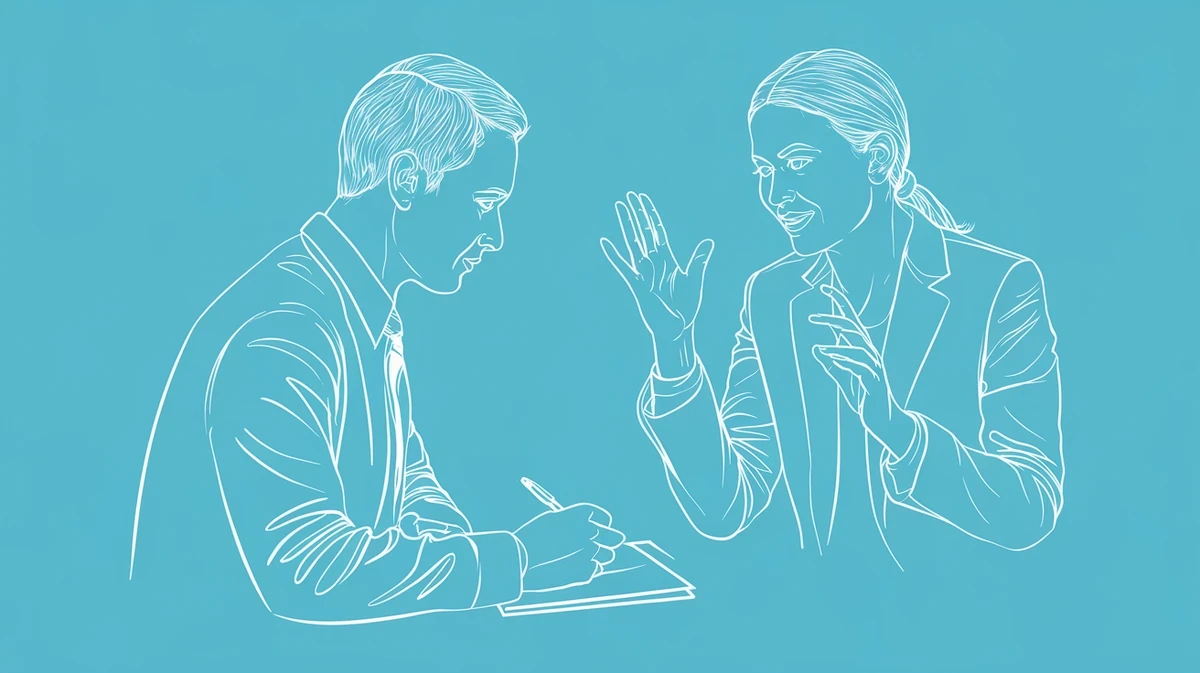
記録は、取るだけでは意味がありません。
せっかく時間をかけて記録したのですから、それを最大限に活用してこそ価値が生まれます。
では、どのようにクレーム記録を活用すればよいのでしょうか?
いくつかの具体的なポイントを見ていきましょう。
定期的な分析と傾向把握(パターンを見つける)
記録されたクレームデータを定期的に見返し、分析することが重要です。
- 発生頻度: どのようなクレームが多いのか?
- 発生時期: 特定の時期に集中するクレームはあるか?(季節商品、キャンペーン期間など)
- 発生チャネル: どの経路からのクレームが多いか?
- 顧客セグメント: 特定の顧客層からのクレームが多いか?
- 共通する原因: 複数のクレームに共通する根本原因はないか?
このようにデータを分析することで、問題のパターンや傾向が見えてきます。
例えば、「特定の商品の初期不良が多い」「Webサイトの特定のページで操作に関する問い合わせが集中している」といった発見があれば、ピンポイントで対策を打つことができますね。
チーム内での情報共有とノウハウ蓄積
クレーム対応は、一人で抱え込むべきではありません。
記録した情報をチーム内で共有することで、他のメンバーも同じようなクレームに対応する際に参考にできます。
- 定例会議での共有: 定期的にクレーム事例を共有し、対応方法について話し合う。
- データベース化: 検索可能なデータベースに記録を蓄積し、誰でもアクセスできるようにする。
- 成功事例・失敗事例の共有: うまくいった対応方法だけでなく、うまくいかなかった対応方法も共有し、チーム全体の学びとする。
情報共有を進めることで、属人化(特定の担当者に依存し過ぎている状況)を防ぎ、チーム全体の対応スキルを向上させることができます。
また、他のメンバーの対応記録を見ることで、「こんな解決策があったのか!」と新たな気づきを得られることもあります。
研修やマニュアル作成への活用
蓄積されたクレーム記録は、新人研修や既存スタッフ向けの研修資料として非常に有効です。
- 具体的な事例: 実際のクレーム事例を基に、ロールプレイング研修を行う。
- FAQの作成: よくあるクレームとその標準的な対応方法をまとめたFAQ(よくある質問とその回答)を作成する。
- 対応マニュアルの改善: クレーム記録から得られた教訓を反映し、対応マニュアルを定期的に更新する。
リアルな事例に基づいた研修は、座学だけでは得られない実践的なスキルを身につけるのに役立ちます。
また、充実したマニュアルがあれば、担当者は安心して対応に臨むことができるでしょう。
製品やサービスの改善へのフィードバック
お客様の声は、製品やサービスをより良くするための貴重なヒントの宝庫です。
クレーム記録を分析し、そこから得られた知見を関連部署(開発、製造、マーケティングなど)にフィードバックしましょう。
- 製品の欠陥や使いにくさ: 顧客が指摘した問題点を具体的に伝え、改善を促す。
- サービスの改善要望: 手続きの煩雑さ、説明不足など、サービスに対する不満点を共有し、改善策を検討する。
- 新たなニーズの発見: クレームの中に隠れた、顧客の潜在的なニーズや期待を発見し、新商品・サービス開発に活かす。
顧客視点での改善を進めることで、顧客満足度を高め、結果的にクレームそのものを減らすことにもつながります。
担当者の精神的負担軽減(記録があることの安心感)
クレーム対応は精神的に大きな負担がかかります。
しかし、対応内容をきちんと記録しておくことは、担当者の心理的な支えにもなります。
- 対応の正当性の担保: 「自分は適切に対応した」という客観的な証拠が残る。
- 記憶への依存からの解放: 詳細をすべて記憶しておく必要がなくなり、精神的なプレッシャーが軽減される。
- 引き継ぎの容易さ: 途中で他の担当者に引き継ぐ場合でも、記録があればスムーズに情報を伝えられ、安心感につながる。
記録があることで、「万が一何かあった時にも説明できる」という安心感が生まれ、担当者はより落ち着いて対応に集中できるようになるでしょう。
クレーム記録を効率化するコツ

「記録が重要なのは分かったけど、忙しくてなかなか時間が取れない…」
「記録作業が面倒で、つい後回しにしてしまう…」
そんな声も聞こえてきそうです。
確かに、日々の業務に追われる中で、詳細な記録を残すのは大変ですよね。
そこで、クレーム記録を少しでも効率的に、そして楽にするためのコツをいくつかご紹介します。
テンプレートやフォーマットの活用
毎回ゼロから記録を作成するのではなく、あらかじめ決まったテンプレートやフォーマットを用意しておきましょう。
必要な項目がリストアップされていれば、記入漏れを防ぎ、記録にかかる時間を短縮できます。
- チェックリスト形式: 選択肢を選ぶだけで記録できる項目を増やす。
- 必須項目と任意項目: 必ず記録すべき項目と、余裕があれば記録する項目を分けておく。
- デジタルツールの活用: Excelやスプレッドシート、専用の顧客管理システムなどを使えば、入力や集計、検索が容易になります。
自社の状況に合わせて使いやすいテンプレートを作成し、チーム内で統一して使うのがおすすめです。
事実と感情を分けて客観的に記録する
クレーム対応中は、お客様の感情に引きずられてしまうこともあります。
しかし、記録する際には、できるだけ冷静に、「事実」と「お客様の感情・要望」、「担当者の対応」を分けて記述することを意識しましょう。
- 事実は客観的に: 「〇〇というエラーが表示された」「〇月〇日に購入した商品が破損していた」など、具体的な事実を記述。
- 感情は引用や客観描写で: 「『非常に困っている』とおっしゃっていた」「声が震えていた」など、顧客の言葉や様子を客観的に記述。主観的な解釈(例:「〇〇に違いない」)は避ける。
- 対応も具体的に: 「〇〇について謝罪した」「代替品の手配を提案した」など、行った対応を具体的に記述。
このように整理して記録することで、後で見返したときに状況を正確に把握しやすくなります。
簡潔かつ具体的に書く練習
「記録」は、長い文章で書く必要はありません。
要点を押さえて、簡潔に、かつ具体的に書くことを心がけましょう。
- 箇条書きの活用: 長文になりそうな場合は、箇条書きを使って情報を整理する。
- 専門用語や社内用語は避ける: 誰が読んでも理解できるように、平易な言葉で書く。
- 一文を短く: 長い文章は読みにくく、意味も伝わりにくくなるため、適度な長さで区切る。
最初は難しく感じるかもしれませんが、何度か練習するうちに、効率的に要点をまとめるスキルが身についてくるはずです。
音声入力やツールの活用を検討する
キーボード入力が苦手な方や、電話対応しながらメモを取るのが難しい場合は、音声入力ツールを活用するのも一つの方法です。
スマートフォンやパソコンのマイクに向かって話すだけで、テキストに変換してくれるので、記録作成の手間を大幅に削減できる可能性があります。
また、世の中には様々な業務効率化ツールがあります。
例えば、報告書やメールの下書き作成をサポートしてくれるツールなども登場しています。
文章を作成するのが苦手だったり、記録をまとめるのに時間がかかってしまったりする場合には、そうしたツールの導入を検討してみるのも良いかもしれません。
そんな悩みを解決するのが、『代筆さん』です。
代筆さん は、簡単な指示や要点を伝えるだけで、AIがビジネス文書を作成してくれるWebサービスです。
クレーム対応の記録を作成する際にも、
- 対応の要点(顧客の要望、対応内容、結果など)を箇条書きで伝えるだけで、整理された報告書の下書きを作成できます。
- 定型的な報告フォーマットをテンプレートとして保存しておけば、毎回同じ指示を繰り返す手間が省けます。
- 客観的で丁寧な表現の文章を作成する手助けになります。
記録作成の時間を短縮し、本来集中すべき顧客対応や改善活動により多くの時間を使うことができるようになるはずです。
人が操作するので、完全自動化は難しいですが、日々の記録作成の負担を軽減する強力なサポーターとなってくれるでしょう。
まとめ:クレーム記録を未来への投資に

今回はクレーム対応記録の重要性から、具体的な記録方法、そしてその活用術までお話ししてきました。
クレーム対応は、確かにとても大変な業務です。
しかし、お客様からの一つ一つの声に真摯に向き合い、丁寧に記録し、そして分析・活用することで、それは単なる「処理すべき問題」から、「ビジネスを成長させるための貴重な機会」へと変わります。
記録を続けることで同じ失敗を繰り返さなくなり、対応品質も向上し、何よりお客様が本当に求めていることが見えてくるはずです。
記録を面倒だと感じる気持ちもよくわかります。
でも、テンプレートを活用したり、代筆さん のようなツールを試してみたりと、少しでも効率化できる方法を探してみてください。
今日からできる小さな一歩として、まずはクレーム記録のテンプレートを見直す、あるいは次回のクレーム対応で一つでも多くの項目を意識して記録してみる、ということから始めてみてはいかがでしょうか。
その積み重ねが、きっとあなたの会社の未来にとって、大きな「投資」となるはずです。




