【状況別】もう怖くない!クレーム対応で使える鉄板例文集と対応のコツ
様々な状況で使えるクレーム対応の例文集

「お客様からのクレーム対応って、どうしたらいいんだろう…」
「またクレームの電話だ…気が重いな…」
あなたは日々のお客様対応の中で、クレームに頭を悩ませていませんか?
実は私も、以前はお客様からの厳しいご指摘に、どう対応すればいいのか分からず、落ち込んだり緊張したりしていました。
特に、予期せぬ内容のクレームや、感情的なお客様への対応は、本当に難しいものですよね。
でも、安心してください。
クレーム対応には、しっかりとした「型」と「心構え」があります。
今回は、様々な状況でそのまま使えるクレーム対応の鉄板例文と、誠意が伝わる対応のコツを、私の経験も踏まえながらご紹介します。
この記事を読めば、もうクレーム対応に怯える必要はありません。
自信を持って、落ち着いて対応できるようになるはずですよ。
クレーム対応の基本姿勢と心構え

クレーム対応で最も大切なのは、テクニック以前に「姿勢」と「心構え」です。
これがしっかりしていないと、どんなに良い例文を使っても、お客様の信頼を得ることはできません。
まずは基本となる4つのポイントを押さえましょう。
まずは冷静に、お客様の話を傾聴する
クレームをいただいた時、まず心がけるべきは「冷静になること」です。
お客様は、何らかの不満や怒りを感じていらっしゃいます。
その感情に引きずられてこちらも感情的になってしまっては、問題解決どころか、事態を悪化させかねません。
まずは深呼吸して、落ち着きましょう。
そして、何よりも大切なのが「傾聴」です。
お客様が何に困っていて、何を伝えたいのか、最後までじっくりと耳を傾けましょう。
途中で話を遮ったり、反論したりするのは厳禁です。
「はい」「さようでございますか」と相槌を打ちながら、お客様の気持ちに寄り添う姿勢を示しましょう。
また、メモを取りながら聞くと内容を整理しやすく、お客様にも「真剣に聞いてくれている」という印象を与えられます。
誠意をもって謝罪する(ただし、安易な全面謝罪は避ける)
お客様のお話を聞き、不快な思いをさせてしまったことに対しては、まず誠意をもって謝罪しましょう。
「この度は、ご不快な思いをおかけし、誠に申し訳ございません」
「ご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます」
といった言葉で、真摯な気持ちを伝えます。
ただし、ここで注意したいのが「安易な全面謝罪」です。
事実関係がはっきりしない段階で、「全面的にこちらが悪いです」といった謝罪をしてしまうと、後々、過剰な要求につながる可能性もあります。
謝罪は、「ご不快な思いをさせたこと」「お手間を取らせてしまったこと」に対して行い、原因については事実確認後に改めて説明するというスタンスが重要です。
事実確認を丁寧に行う
謝罪の後は、具体的な状況を把握するための「事実確認」に移ります。
お客様のお話を鵜呑みにするのではなく、客観的な情報を集めることが大切です。
「恐れ入りますが、もう少し詳しく状況をお伺いしてもよろしいでしょうか?」
「いつ、どこで、どのような状況でしたでしょうか?」
このように、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識しながら、丁寧な言葉遣いで質問しましょう。
お客様の記憶違いや誤解がある可能性も考慮し、冷静に、客観的な事実を積み重ねていくことが重要です。
もし手元に情報があれば、それと照らし合わせながら確認を進めるとスムーズですね。
解決策を提示し、迅速に対応する
事実確認ができたら、次はお客様が納得できる「解決策」を提示します。
すぐに解決できることであれば、その場で対応方法を伝えましょう。
「ご迷惑をおかけし申し訳ございません。すぐに新しい商品とお取り替えいたします」
「大変失礼いたしました。担当者に代わり、私が責任を持って対応させていただきます」
もし、その場で判断できない場合や調査が必要な場合は、正直にその旨を伝え、いつまでに回答できるかの目安を示します。
「申し訳ございません。詳細を確認し、〇〇(日時)までにご連絡差し上げます」
「社内で確認の上、改めて担当者よりご連絡させていただきます」
大切なのは、お客様を待たせない「迅速な対応」です。
約束した期日までに必ず連絡を入れましょう。
進捗状況を適宜報告することも、お客様の不安を和らげる上で効果的ですよ。
状況別 クレーム対応例文集

ここからは、具体的な状況別に使えるクレーム対応の例文をご紹介します。
もちろん、これはあくまで一例です。
お客様の状況や口調に合わせて、言葉遣いを調整してくださいね。
大切なのは、例文を丸暗記することではなく、誠意が伝わるように、自分の言葉で話すことです。
商品・サービスに関するクレーム
商品やサービスに対するクレームは、最も多いケースかもしれません。
丁寧に対応することで、かえってファンになっていただける可能性もあります。
不良品・故障の場合
「この度は、ご購入いただいた商品に不具合があったとのこと、誠に申し訳ございません。」
「ご不便をおかけし、大変恐縮しております。」
「すぐに商品の状態を確認させていただき、交換または修理にて対応させていただきます。」
「恐れ入りますが、商品の詳しい状況(型番、購入日、不具合の内容など)をお伺いしてもよろしいでしょうか?」
「代替品をお送りするお手配をいたします。お届け先のご住所とお名前を頂戴できますでしょうか。」
期待外れ・効果がなかった場合
「この度は、私どもの商品(サービス)が、お客様のご期待に沿えず、誠に申し訳ございません。」
「貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。」
「よろしければ、どのような点にご満足いただけなかったか、具体的にお聞かせいただけますでしょうか。」
「今後の商品開発(サービス改善)の参考にさせていただきたく存じます。」
(返金や代替案を提示する場合)
「ご満足いただけなかったとのこと、大変心苦しく思っております。つきましては、〇〇といった対応をさせていただきたく存じますが、いかがでしょうか。」
説明不足・誤解があった場合
「この度は、私どもの説明が至らず、お客様に誤解を与えてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。」
「ご指摘いただき、ありがとうございます。認識の相違があった点について、改めてご説明させていただいてもよろしいでしょうか。」
「〇〇という点について、説明が不足しており失礼いたしました。正しくは△△でございます。」
「今後は、より分かりやすい説明を心がけてまいります。」
接客・応対に関するクレーム
スタッフの対応に関するクレームは、お客様の感情に直接関わるため、特に慎重な対応が求められます。
店員の態度が悪かった場合
「この度は、店舗スタッフの応対により、お客様にご不快な思いをおかけしましたこと、誠に申し訳ございません。」
「責任者として、深くお詫び申し上げます。」
「大変恐縮ですが、いつ頃、どの店舗での出来事か、また、どのような応対であったか、詳しくお聞かせいただけますでしょうか。」
「ご指摘いただいた内容は、該当スタッフに厳重に注意し、全社的に指導を徹底してまいります。」
「今後は、お客様に気持ちよくご利用いただけるよう、従業員教育に一層力を入れてまいります。」
待ち時間が長かった場合
「この度は、長時間お待たせしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。」
「貴重なお時間を頂戴したにもかかわらず、ご不便をおかけしましたこと、重ねてお詫び申し上げます。」
「当日は混雑しており、十分な対応ができず大変失礼いたしました。」
「今後はスタッフの増員やオペレーションの見直しを行い、待ち時間の短縮に努めてまいります。」
説明が不十分だった場合
「この度は、私どもの説明が不足しており、お客様にご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。」
「ご不明な点がございましたら、改めて丁寧にご説明させていただきます。」
「どの点について説明が分かりにくかったか、お聞かせいただけますでしょうか。」
「今後はお客様の視点に立ち、より丁寧で分かりやすい説明を心がけてまいります。」
納期・配送に関するクレーム
ECサイトなどを利用していると、納期や配送に関するトラブルも起こり得ますよね。
ここでも迅速な状況確認と、誠実な対応が鍵となります。
納期遅延の場合
「この度は、ご注文いただいた商品の納期が遅れておりますこと、誠に申し訳ございません。」
「ご迷惑をおかけし、大変恐縮しております。」
「ただいま、詳しい状況を確認しております。確認でき次第、改めてご連絡させていただきます。」
(原因が判明した場合)
「確認しましたところ、〇〇(遅延理由)により、お届けが遅れております。現在のところ、〇月〇日頃のお届け予定でございます。」
「お待ちいただくことになり、大変申し訳ございませんが、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。」
商品が届かない場合
「この度は、ご注文いただいた商品がお手元に届いていないとのこと、ご心配をおかけし誠に申し訳ございません。」
「すぐに配送状況を確認いたします。恐れ入りますが、ご注文番号をお伺いしてもよろしいでしょうか?」
(確認後)
「お調べしましたところ、現在〇〇(配送状況)となっております。」
「配送会社に確認し、状況が分かり次第、改めてご連絡いたします。」
(配送事故などの場合)
「配送途中で何らかのトラブルがあった可能性がございます。すぐに代替品を再発送する手配をいたします。」
破損・汚損していた場合
「この度は、お届けした商品に破損(汚損)があったとのこと、誠に申し訳ございません。」
「ご不快な思いをおかけし、大変恐縮しております。」
「すぐに新しい商品とお取り替えいたします。お手数ですが、破損(汚損)状況を詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか?可能であれば、お写真などをいただけますと幸いです。」
「ご迷惑をおかけしますが、破損した商品は、配送業者が引き取りに伺うよう手配いたします。」
理不尽な要求・悪質なクレームへの対応
残念ながら、中には理不尽な要求や、度を超えた悪質なクレームもあります。
そのような場合は、毅然とした態度で対応することも必要です。
丁寧にお断りする際の表現
「誠に申し訳ございませんが、お客様のご要望にお応えすることは致しかねます。」
「弊社の規定により、〇〇といった対応はできかねますこと、何卒ご了承ください。」
「ご意向に沿えず大変心苦しいのですが、ご理解いただけますと幸いです。」
「これ以上の対応は難しい状況でございます。」
エスカレーションする場合の伝え方
「私の一存では判断致しかねますので、上司に相談の上、改めてご連絡させていただきます。」
「恐れ入りますが、この件につきましては、担当部署より改めてご回答させていただきます。」
「お客様のご意見は、責任を持って上司(担当部署)に申し伝えます。」
決して感情的にならず、冷静に、しかしはっきりとこちらの限界を伝えることが大切です。
必要であれば、警察や弁護士への相談も検討しましょう。
クレーム対応で避けるべきNG表現

良かれと思って使った言葉が、かえってお客様の感情を逆なでしてしまうこともあります。
ここでは、クレーム対応で避けるべきNG表現をいくつかご紹介します。
無意識に使ってしまわないように、注意しましょう。
責任転嫁や言い訳と受け取られる言葉
- 「~のはずですが…」
- 「普通は~なのですが…」
- 「担当者が不在で分かりません」
- 「前任者はそう言ったかもしれませんが…」
- 「私も聞いていなかったので…」
これらの表現は、責任を回避している、言い訳をしている、と受け取られがちです。
まずは組織として謝罪し、責任を持って対応する姿勢を示しましょう。
お客様の感情を逆なでする言葉
- 「ですから」「だって」「でも」 (反論と受け取られやすい)
- 「規則ですので」「決まりですので」(一方的な押し付けに聞こえる)
- 「ご理解いただけましたか?」(高圧的に聞こえる場合がある)
- 「落ち着いてください」(火に油を注ぐ可能性が高い)
- 「クレーマー」(絶対に口にしてはいけません)
お客様の感情に寄り添わず、一方的にこちらの主張を押し付けたり、お客様を否定したりするような言葉は、絶対に避けましょう。
曖昧な表現や憶測での回答
- 「たぶん~だと思います」
- 「~かもしれません」
- 「なるべく早く対応します」
- 「善処します」
不確かな情報や曖昧な約束は、さらなる不信感につながります。
分からないことは正直に伝え、確認してから回答するようにしましょう。
すぐに返答ができない場合は、いつなら対応が可能なのか、具体的な期日を示すことも重要です。
クレームをチャンスに変えるために
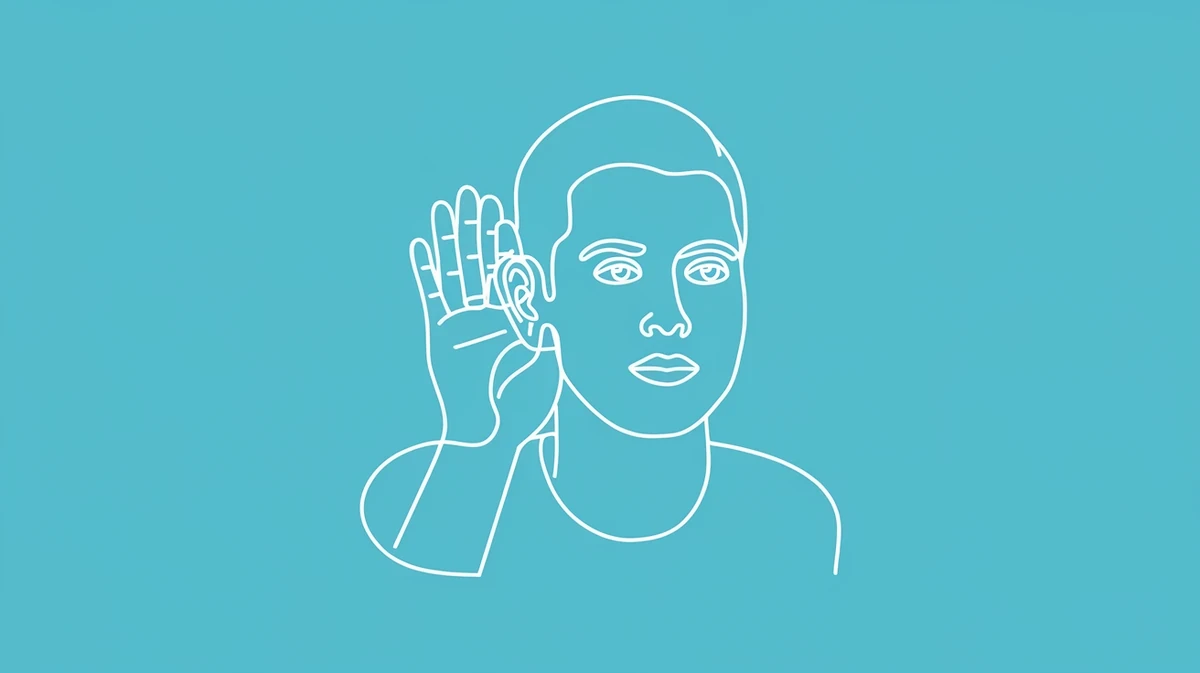
クレームは、決してネガティブなものばかりではありません。
見方を変えれば、お客様の生の声を聞ける貴重な機会であり、サービス改善のヒントが隠されていることも多いのです。
誠実に対応することで、ピンチをチャンスに変えることも可能です。
クレームから学ぶ顧客のニーズ
お客様がなぜクレームを言わざるを得なかったのか、その背景にある「本当のニーズ」を探ってみましょう。
「もっとこうしてほしかった」「こんな機能があったら便利なのに」といった、普段は聞けない本音が隠れているかもしれません。
いただいたご意見を真摯に受け止め、分析することで、商品開発やサービス改善に役立つ貴重なインサイトが得られます。
再発防止策を検討し、改善につなげる
同じようなクレームが繰り返されるようであれば、それは組織や仕組みに問題がある可能性があります。
クレームの内容を記録・共有し、原因を分析して、具体的な再発防止策を検討しましょう。
マニュアルを見直したり、研修を実施したり、システムを改善したりするなど、具体的なアクションにつなげることが重要です。
改善結果をお客様に報告できれば、さらに信頼度が高まるでしょう。
誠実な対応で信頼回復を目指す
クレーム対応で最も大切なのは、やはり「誠意」です。
たとえお客様の要求にすべて応えられなかったとしても、最後まで真摯に向き合い、できる限りの対応を尽くす姿勢が伝われば、お客様の怒りも少しずつ和らいでいくはずです。
そして、その誠実な対応によって、失いかけた信頼を取り戻し、むしろ以前よりも強い関係性を築くきっかけになることさえあります。
「あの時の対応は丁寧だった」「しっかり話を聞いてくれた」と思っていただければ、お客様はきっとまた戻ってきてくれますよ。
メールでのクレーム対応を効率化する方法
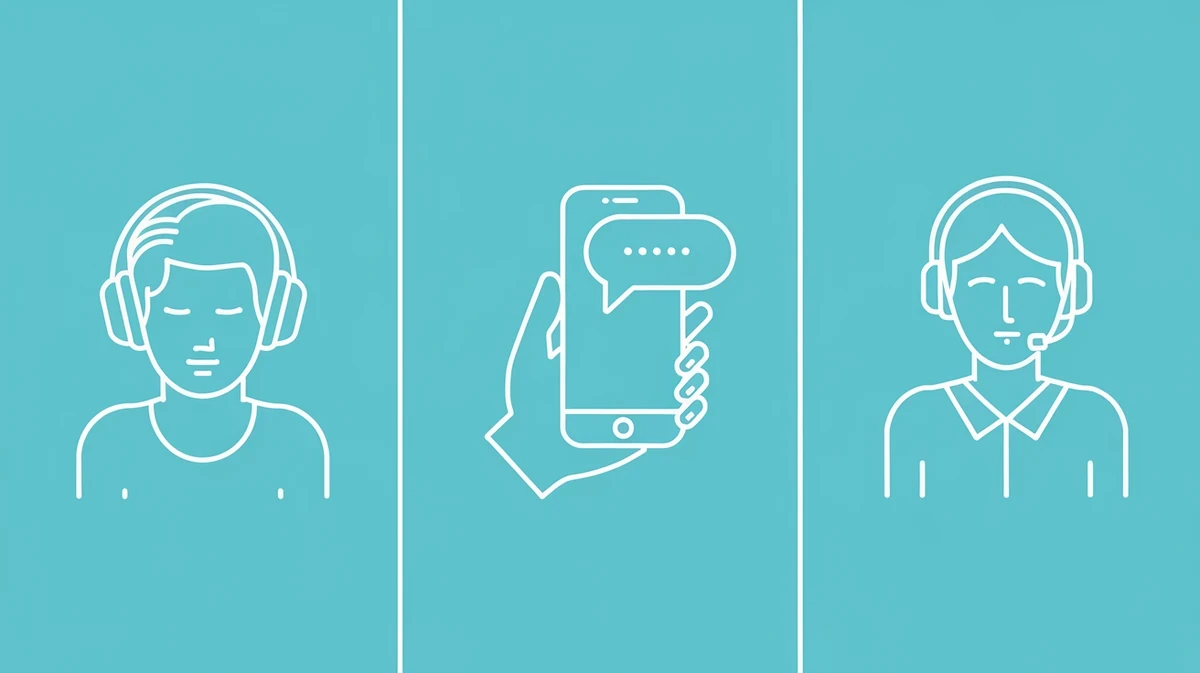
電話だけでなく、メールでクレームをいただくことも増えていますよね。
メールでの対応は、記録が残る、時間をかけて丁寧な文章を作成できるといったメリットがある一方、返信に時間がかかると、お客様の不満を増幅させてしまう可能性もあります。
迅速な一次対応の重要性
メールでクレームを受け取ったら、まずは「受け付けました」という一次対応を迅速に行うことが重要です。
「お問い合わせいただきありがとうございます。〇〇(部署名・担当者名)でございます。メールを拝見いたしました。」
「詳細を確認の上、改めてご連絡させていただきます。恐れ入りますが、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。」
このような自動返信メールを設定しておくのも有効です。
これにより、お客様は「無視されているわけではない」と安心することができます。
もちろんその後、できるだけ早く具体的な返信をする必要があります。
定型文だけに頼らない個別対応のポイント
クレームの内容は千差万別です。
定型文をコピー&ペーストするだけでは、お客様に「事務的な対応だ」と感じさせてしまう可能性があります。
もちろん、基本的な構成や謝罪の言葉などはテンプレート化しておくと効率的ですが、必ずお客様の状況に合わせた個別の言葉を加えるようにしましょう。
- お客様のお名前をきちんと記載する
- いただいたクレーム内容を具体的に引用し、理解していることを示す
- お客様の感情に寄り添う言葉を入れる(「ご不便をおかけし、心苦しく思っております」など)
- 具体的な解決策や今後の対応を明確に記載する
少しの手間を加えるだけで、メールの印象は大きく変わりますよ。
AIを活用したメール作成支援という選択肢
とはいえ、一件一件丁寧なメールを作成するのは時間もかかりますし、精神的にも負担が大きいですよね。
特に、日本のビジネスシーンでは、丁寧な言葉遣いや敬語の使い分けなど、気を遣うべき点が多く、メール作成に時間がかかりがちです。
人手不足の中で、クレーム対応に多くの時間を割くのは、億劫に感じてしまいます。
そんな悩みを解決するのが、『代筆さん』です。
代筆さん は、簡単な指示や要件を伝えるだけで、AIがビジネスメールを作成してくれるWebサービスです。
例えば、お客様からのクレームメールの内容と、「謝罪と交換対応を伝えたい」といった指示を入力するだけで、AIが状況に応じた丁寧な返信メールの案を作成してくれます。
もちろん、AIが作成した文章をそのまま送るのではなく、ご自身の言葉で修正を加える必要はありますが、ゼロから文章を考える手間が大幅に削減されます。
- 謝罪メールの作成: クレーム内容に応じて、適切な謝罪の言葉を含んだメールを作成します。
- 返信メールの作成: お客様のメール内容を貼り付けて指示を出すだけで、その内容を踏まえた返信案を作成します。
- 多言語対応: 日本語で指示を出しても、英語など、相手の言語に合わせたメールを作成することも可能です。(海外のお客様からのクレームにも対応できますね!)
- テンプレート保存: よく使う指示やフレーズを保存しておけば、次回からさらに効率的にメールを作成できます。(クレームの種類ごとにテンプレートを用意しておくと便利です)
メール作成の時間を短縮できれば、その分、お客様への他の対応や根本的な原因解決、再発防止策の検討といった、より本質的な業務に集中できます。
人が行う丁寧な対応はそのままに、AIを文章作成のサポート役として活用することで、クレーム対応全体の質と効率を向上させることが期待できます。
まとめ:誠意ある対応で信頼を築く

今回は、クレーム対応の基本的な心構えから、状況別の具体的な例文、そして対応を効率化するヒントまで、幅広くご紹介しました。
クレーム対応は決して簡単な仕事ではありませんが、避けては通れない重要な業務です。
大切なのは、お客様の声に真摯に耳を傾け、誠意をもって対応すること。
そして、いただいたご意見をサービス改善につなげていく前向きな姿勢です。
今回ご紹介した例文や対応のコツを参考に、自信を持ってクレーム対応に臨んでみてください。
もし、日々のメール作成に負担を感じているなら、代筆さん のようなツールを活用することも、業務効率化の一つの有効な手段となるでしょう。
あなたの誠実な対応が、お客様との信頼関係をより強く、深いものにしていくことを願っています。




