クレーム対応が上手い人の特徴とは?信頼される話し方のコツを徹底解説
クレーム対応が上手い人の特徴と話し方

クレーム対応って、本当に気が重いですよね。
お客様の怒りや不満を直接受け止めなければならないし、言葉遣い一つで状況が悪化してしまう可能性もあります。
私も以前は、クレームの電話が鳴るたびにドキッとして、どう対応すればいいのか分からず、ただただ謝ることしかできませんでした。
でも、周りにはどんなクレームにも冷静に対応して、最後にはお客様から「ありがとう」と言われているような、クレーム対応が上手い人もいますよね。
一体、何が違うのでしょうか?
今回は、そんなクレーム対応に悩むあなたに向けて、クレーム対応が上手い人の特徴と、すぐに実践できる話し方のコツを詳しくご紹介します。
この記事を読めば、あなたも自信を持ってクレーム対応に臨めるようになるはずです。
なぜクレーム対応は難しいのか?日本のビジネス文化との関係

クレーム対応が難しいと感じる背景には、いくつかの理由があります。
特に日本のビジネスシーン特有の文化も、その難しさに拍車をかけているのかもしれません。
丁寧さが求められるプレッシャー
日本のビジネスコミュニケーションでは、相手への敬意を示す丁寧な言葉遣いが非常に重視されますよね。
特にクレーム対応の場面では、普段以上に言葉を選び、失礼がないように気を配る必要があります。
間違った敬語を使ってしまったり、少しでも不適切な表現をしてしまったりすると、お客様の感情をさらに逆撫でしてしまうのではないか、というプレッシャーを感じてしまうことはありませんか?
この「丁寧さへの過剰な意識」が、スムーズな対応を妨げてしまうことがあるんです。
感情的な相手への対応の難しさ
クレームを伝えてくるお客様は、怒りや不満、不安といった強い感情を抱えていることが多いです。
そうした感情的な言葉を直接ぶつけられると、こちらも冷静でいるのが難しくなってしまいますよね。
相手の感情に引きずられてしまったり、逆に自分を守るように防御的になってしまったり…。
感情的な相手と冷静に、かつ建設的な対話を進めることは、本当に難しいスキルだと思います。
失敗への恐れと責任感
「自分の対応一つで、会社の評判を落としてしまうかもしれない」
「問題をこじらせてしまったらどうしよう」
クレーム対応には、このような失敗への恐れがつきまといます。
特に、真面目で責任感の強い人ほど、このプレッシャーを強く感じてしまう傾向があるのではないでしょうか。
失敗を恐れるあまり、思い切った判断や提案ができず、対応が後手に回ってしまうこともあります。
人手不足と対応時間の制約
近年、多くの企業で課題となっているのが人手不足です。
少ない人数で多くの業務をこなさなければならない中で、クレーム対応に十分な時間を割くことが難しい状況もあるでしょう。
お客様はじっくり話を聞いてほしい、早く解決してほしいと思っているのに、時間的な制約から十分な対応ができない…そんなジレンマを抱えている方もいるかもしれませんね。
日本の長時間労働の問題も、こうした状況に影響を与えていると言えるでしょう。
クレーム対応が上手い人の共通点:5つの特徴

では、難しいクレーム対応をスムーズにこなし、お客様の信頼を得ている人は、どのような特徴を持っているのでしょうか?
ここでは、クレーム対応が上手い人に共通する5つの特徴を見ていきましょう。
1. 冷静さを保つ力
まず何よりも大切なのが、冷静さを失わないことです。
お客様がどんなに感情的になっていても、対応する側が落ち着きを保つことで、状況の悪化を防ぐことができます。
上手い人は、相手の言葉を個人的な攻撃として受け止めず、「お客様が困っている状況」と「その感情」を客観的に捉えようとします。
深呼吸をしたり、心の中で一歩引いて状況を俯瞰したりする習慣を持っているのかもしれませんね。
2. 傾聴力:相手の話を最後まで聞く姿勢
クレーム対応が上手い人は、抜群の傾聴力を持っています。
途中で話を遮ったり、反論したりせず、まずはお客様の言い分を最後までじっくりと聞くことに徹します。
相槌を打ちながら、「なるほど」「そうだったのですね」といった言葉で、聞いている姿勢を示すことも忘れません。
お客様は、「自分の話をちゃんと聞いてもらえている」と感じることで、少しずつ冷静さを取り戻し、心を開いてくれることが多いのです。
3. 共感力:相手の感情に寄り添う
ただ話を聞くだけでなく、相手の感情に寄り添う姿勢も重要です。
「大変申し訳ございません」という謝罪の言葉だけでなく、「ご不便をおかけし、さぞご不快な思いをされたことと存じます」「お気持ちお察しいたします」といった、
相手の感情に共感する言葉を添えることで、お客様は「自分の気持ちを理解してもらえた」と感じます。
ただし、ここで重要なのは、相手の言い分すべてに同意するということではありません。
あくまで、「不快な思いをさせてしまったこと」「困らせてしまったこと」に対する共感を伝えるのです。
4. 問題解決能力:本質を見抜く力
クレーム対応の目的は、ただ謝ることではありません。
お客様が抱えている問題を正確に把握し、適切な解決策を見つけ出すことです。
上手い人は、お客様の話の中から、問題の本質は何か、お客様が本当に望んでいることは何かを素早く見抜く力を持っています。
そして、事実確認を丁寧に行い、実現可能な解決策を具体的かつ分かりやすく提示します。
時には、代替案を提案したり、今後の改善策を伝えたりすることも、お客様の信頼回復につながります。
5. ポジティブ思考:ピンチをチャンスに変える
クレームは、一見ネガティブな出来事ですが、実はサービスや製品の問題点、お客様の隠れたニーズを知る貴重な機会でもあります。
クレーム対応が上手い人は、このことをよく理解しています。
クレームを単なる「厄介事」として捉えるのではなく、「改善のチャンス」「お客様との関係を深めるチャンス」と前向きに捉える姿勢を持っています。
このポジティブな姿勢が、お客様にも伝わり、最終的には「この会社はちゃんと対応してくれる」という信頼につながるのです。
心をつかむ!クレーム対応が上手い人の話し方テクニック

クレーム対応が上手い人の特徴がわかったところで、次は具体的な話し方のテクニックを見ていきましょう。
ちょっとした言葉遣いの工夫で、お客様の受け止め方は大きく変わりますよ。
クッション言葉を効果的に使う
会話をスムーズに進め、相手への配慮を示すために、「クッション言葉」は非常に有効です。
例えば、何かをお願いする前には「恐れ入りますが」「お手数ですが」、反論や否定的な内容を伝える前には「申し訳ございませんが」「あいにくですが」、
確認する際には「失礼ですが」「念のためご確認させていただけますでしょうか」といった言葉を添えるだけで、印象がぐっと柔らかくなります。
特にクレーム対応では、これらのクッション言葉を意識的に使うことで丁寧な印象を与え、お客様の感情を和らげる効果が期待できます。
事実確認と感情の受け止めを分ける
お客様の話を聞く際には、「何が起こったのか(事実)」と「お客様がどう感じているか(感情)」を分けて捉えることが大切です。
まずは、「〇〇ということがあったのですね」と事実を確認し、その上で「それは大変ご不快な思いをされましたね」と感情を受け止める言葉を伝えます。
これを混同してしまうと、「つまり、こちらが全面的に悪いということか!」とお客様が誤解してしまったり、話がこじれたりする原因になります。
事実確認は客観的に、感情の受け止めは共感的に、これを意識して話を進めましょう。
謝罪の言葉は適切に使う
クレーム対応において謝罪は欠かせませんが、使い方には注意が必要です。
何に対して謝っているのかを明確にすることが大切です。
例えば、「ご不便をおかけしたこと」「ご不快な思いをさせてしまったこと」に対しては、まず真摯に謝罪します。
「大変申し訳ございませんでした」とはっきりと伝えましょう。
一方で、事実確認ができていない段階で、全面的に非を認めるような謝罪は避けるべきです。
状況に応じて、「確認いたしますので、少々お待ちいただけますでしょうか」のように、調査・確認に時間が必要であることを伝えましょう。
謝罪の言葉を多用しすぎると、かえって軽く聞こえてしまうこともあるので、タイミングと内容を見極めることが重要です。
解決策を具体的に提示する
お客様が最も知りたいのは、「この問題をどう解決してくれるのか」ということです。
謝罪や共感の言葉を伝えた後は、具体的な解決策や対応策を提示する必要があります。
「できる限り対応させていただきます」といった曖昧な表現ではなく、「〇〇の対応をさせていただきます」「明日中に改めてご連絡いたします」のように、誰が、いつまでに、何をするのかを具体的に伝えましょう。
もしすぐに対応できない場合でも、「現時点では〇〇までしかお約束できませんが、△△については確認して改めてご連絡いたします」のように、
できることとできないこと、今後のステップを明確に伝えることが、お客様の安心感につながります。
ポジティブな言葉で締めくくる
クレーム対応の最後は、できるだけポジティブな言葉で締めくくることを意識しましょう。
もちろん、解決に至らなかった場合など、状況によっては難しいこともありますが、「この度は貴重なご意見をいただき、ありがとうございました」「今後の改善に努めてまいります」といった感謝や前向きな姿勢を示す言葉で終えることで、お客様の印象も変わってきます。
たとえ完全な満足には至らなくても、「ちゃんと話を聞いてくれた」「改善しようとしてくれている」と感じてもらえれば、将来的な信頼関係につながる可能性があります。
AIはクレーム対応の味方になる?

最近、様々な分野でAIの活用が進んでいますが、クレーム対応においてもAIは役立つのでしょうか?
AIと人間の役割分担について考えてみましょう。
AIが得意なこと:定型的な回答や情報提供
AIは、よくある質問への回答や、手続きの案内など、定型的な情報提供を得意としています。
膨大な情報の中から、関連する情報を素早く見つけ出し、正確に回答することができます。
また、同じ質問に何度でも、感情的になることなく、忍耐強く対応できる点もAIの強みです。
例えば、ウェブサイトのチャットボットなどで、簡単な問い合わせにAIが自動で答えてくれる場面が増えていますよね。
これにより、人間の担当者はより複雑な対応に集中することができます。
AIの限界:複雑な感情への対応
一方で、AIには限界もあります。
特に、クレーム対応で重要となる、お客様の複雑な感情の機微を完全に理解し、心から共感することは、現在のAI技術ではまだ難しいと言えます。
AIは共感的な言葉を生成することは得意ですが、それはあくまでプログラムされた反応であり、人間のような真の感情ではありません。
お客様が本当に求めている「気持ちを分かってほしい」という部分に応えるのは、やはり人間の役割が大きいでしょう。
人間との連携が鍵
クレーム対応において、AIは万能ではありませんが、人間のサポート役として非常に有効なツールとなり得ます。
AIが定型的な業務や情報収集をサポートし、人間はより高度な判断や、お客様の感情に寄り添ったコミュニケーションに注力する。
このように、AIと人間がそれぞれの強みを活かして連携することが、より質の高いクレーム対応を実現する鍵となります。
AIはあくまでサポートツールであり、最終的な判断やお客様との心の通ったコミュニケーションは、人間が行うべき大切な部分なのです。
メール対応を効率化するツールの活用
クレーム対応では、電話だけでなくメールでのやり取りも多く発生しますよね。
特に、丁寧な言葉遣いや正確な情報伝達が求められるメール作成は、時間もかかり、精神的な負担も大きいものです。
そんな悩みを解決するのが、『代筆さん』です。
代筆さん は、簡単な指示や要件を伝えるだけで、AIがビジネスメールを作成してくれるWebサービスです。
要点を伝えるだけで丁寧なメールを作成
クレームへのお詫びメールや、状況説明のメールなど、伝えたい要点を入力するだけで、AIが状況に応じた丁寧なビジネスメールを作成してくれます。
「どのような点に謝罪したいか」「今後の対応策は何か」といったポイントを伝えるだけで、適切な敬語や表現を使ったメール文面案を複数提案してくれるので、メール作成にかかる時間を大幅に短縮できます。
返信メール作成もサポート
お客様からのクレームメールへの返信も、相手のメール内容を貼り付けて指示をすれば、AIが内容を理解し、適切な返信文案を作成してくれます。
相手の主張を踏まえつつ、こちらが伝えたい内容を盛り込んだ返信メールを素早く作成できるので、返信のスピードアップにもつながりますね。
定型文の保存で効率アップ
よく使う謝罪文や対応説明のフレーズなど、指示内容をテンプレートとして保存しておくことも可能です。
毎回同じような内容のメールを作成する手間が省け、より効率的にメール対応を進めることができます。
クレーム対応のメール作成に時間がかかっている、もっと効率化したいと感じているなら、ぜひ 代筆さん のようなツールの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
ただし、AIが作成した文章は、必ず最終的にご自身の目で確認し、状況に合わせて修正することが大切です。
クレーム対応スキルを磨くために
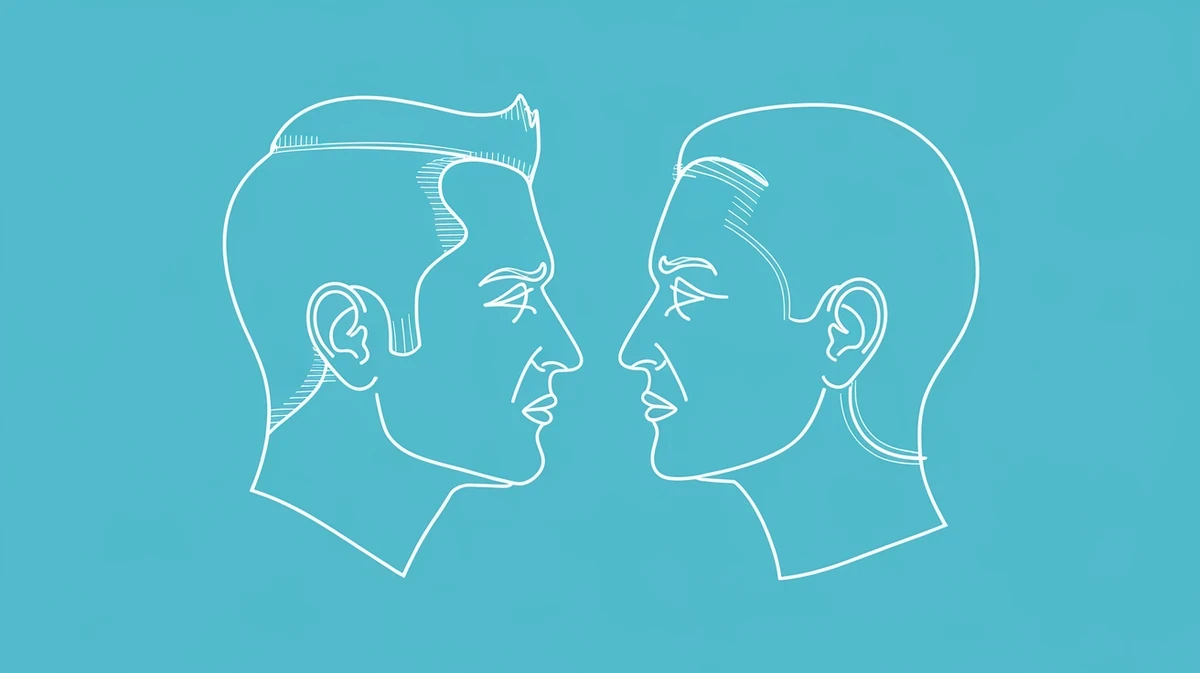
クレーム対応のスキルは、一朝一夕に身につくものではありません。
日々の意識と継続的な努力が大切です。
ここでは、スキルアップのための具体的な方法をいくつかご紹介します。
ロールプレイングで練習する
実際のクレーム場面を想定したロールプレイングは、非常に効果的な練習方法です。
同僚や上司に協力してもらい、お客様役と対応者役に分かれて、様々なクレームシナリオをシミュレーションしてみましょう。
実際に声に出して対応してみることで、言葉遣いや話の進め方の課題が見えてきます。
また、客観的なフィードバックをもらうことで、自分では気づかなかった改善点を発見できます。
上手い人の対応を観察・模倣する
あなたの周りにいるクレーム対応が上手い人の対応を、注意深く観察してみましょう。
どのような言葉遣いをしているか、どのようなタイミングで謝罪や共感を示しているか、どのように話を進めているかなど、具体的なテクニックを学ぶことができます。
そして、良いと思った点は積極的に真似てみましょう。
最初は模倣からでも、繰り返すうちに自然と自分のスキルとして身についていきます。
フィードバックをもらう
自分一人で悩まず、上司や先輩、同僚に自分の対応についてフィードバックを求めることも大切です。
「あの時の対応、どうでしたか?」「もっとこうした方が良かった点はありますか?」と積極的に聞いてみましょう。
他者からの客観的な意見は、自分自身の成長にとって非常に貴重なものです。
また、困った事例があれば、チーム内で共有し、どのように対応すべきだったかを話し合うことも、組織全体の対応力向上につながります。
知識をアップデートし続ける
クレームの内容は、社会の変化や新しいサービス・製品の登場によって常に変化していきます。
自社の商品やサービスに関する知識はもちろん、関連する法律や業界の動向など、常に最新の情報をインプットしておくことが重要です。
また、コミュニケーションスキルや心理学に関する書籍を読んだり、研修に参加したりすることも、対応力の向上に役立ちます。
学び続ける姿勢が、自信を持ってクレーム対応に臨むための土台となるでしょう。
まとめ:クレーム対応は成長のチャンス

クレーム対応は、確かに精神的な負担が大きい仕事です。
しかし、避けて通ることはできません。
むしろ、クレームはお客様の生の声を聞ける貴重な機会であり、あなた自身の成長のチャンスでもあります。
今回ご紹介した、クレーム対応が上手い人の特徴(冷静さ、傾聴力、共感力、問題解決能力、ポジティブ思考)を意識し、話し方のテクニック(クッション言葉、事実と感情の分離、適切な謝罪、具体的な解決策提示、ポジティブな締めくくり)を実践してみてください。
すぐに完璧にできなくても大丈夫です。
一つひとつ意識して取り組むことで、あなたの対応は必ず変わっていきます。
そして、日々のメール作成の負担を軽減したいと感じたら、AIメール作成支援ツール『代筆さん』の活用も検討してみてください。
簡単な指示で丁寧なメールを作成できるため、クレーム対応におけるメール業務の効率化に役立つはずです。
クレーム対応を通じて得られるスキルは、ビジネスパーソンとしてのあなたの価値を大きく高めてくれます。
ぜひ、前向きな気持ちで取り組んでいきましょう。




