クレーム対応代行サービスで負担軽減!メリットと賢い選び方
クレーム対応代行サービスの活用メリットと選び方

「またクレームの電話だ…」
「どう返信したら角が立たないだろう…」
日々の業務の中で、クレーム対応に頭を悩ませている方は本当に多いのではないでしょうか。
実は私も、以前はお客様からのお問い合わせ対応で、時には厳しいご意見をいただくこともあり、そのたびにどう対応すべきか、どんな言葉を選べば良いのか、本当に苦慮していました。
特に、日本のビジネスシーンでは、言葉遣い一つで印象が大きく変わってしまうため、細心の注意が必要ですよね。
人手不足が叫ばれる中、クレーム対応に貴重な時間や人材が割かれてしまうのは、企業にとっても大きな課題です。
今回は、そんなあなたの悩みを少しでも軽くするために、クレーム対応代行サービスを活用するメリットや、自社に合ったサービスの選び方などを、詳しくご紹介します。
クレーム対応の現実と課題

クレーム対応は、どんなビジネスにおいても避けては通れない道と言えます。
お客様の声を真摯に受け止め、改善に繋げることは、サービスの質を高める上で非常に重要です。
しかし、その裏側には多くの課題が潜んでいるのも事実です。
精神的な負担が大きいクレーム対応
クレーム対応と聞いて、まず思い浮かぶのは精神的な負担の大きさかもしれません。
お客様からの厳しい言葉や、時には理不尽とも思える要求に、心がすり減ってしまう経験をされた方も少なくないでしょう。
特に、感情的になっているお客様を相手にする場合、冷静さを保ちながら丁寧に対応することは、想像以上にエネルギーを消耗します。
「また自分か…」と、担当になった時のプレッシャーは計り知れません。
このような状況が続くと、従業員のモチベーション低下や、最悪の場合、離職に繋がってしまう可能性も否定できません。
時間とリソースの圧迫
クレーム対応は、精神的な負担だけでなく、時間的な拘束も大きいです。
一件のクレームに対応するために、事実確認、関係部署との連携、そしてお客様への説明と、多くのステップが必要になります。
その間、本来行うべきコア業務が滞ってしまうことも少なくありません。
日本の企業では、慢性的な人手不足が課題となっている場合が多く、一人の従業員が複数の業務を抱えていることも珍しくありません。
そんな中で、クレーム対応に多くの時間を割かれてしまうのは、企業全体の生産性にとっても大きなマイナスと言えます。
「この対応に、一体どれだけの時間がかかっているんだろう…」と、ため息をつきたくなる気持ち、よくわかります。
専門知識の必要性
クレームの内容によっては、製品やサービスに関する深い知識だけでなく、法律や業界のルールといった専門知識が求められることもあります。
例えば、個人情報の取り扱いに関するクレームや、契約内容の解釈に関する問い合わせなど、適切な知識なしに対応してしまうと、問題をさらに大きくしてしまうリスクも否定できません。
社内に専門の担当者がいれば良いのですが、そうでない場合、対応する従業員がその都度調べたり、専門家を探したりする必要があり、迅速な解決が難しくなることがあります。
「この件、私に判断できるかな…」と不安になることもあるでしょう。
日本のビジネス文化におけるクレーム対応の難しさ
日本のビジネスコミュニケーションは、丁寧さや相手への配慮が非常に重視される文化です。
そのため、クレーム対応においても、言葉遣いや表現方法に細心の注意を払う必要があります。
敬語の使い方が少し違うだけで、相手に不快感を与えてしまうこともあります。
また、直接的な表現を避け、婉曲的な言い回しを好む傾向もあるため、お客様の真意を正確に汲み取り、適切な対応をすることが求められます。
「この言い方で、ちゃんと気持ちが伝わるだろうか…」と、何度も文章を練り直す経験は、多くの方がお持ちではないでしょうか。
社内と社外で言葉遣いを使い分ける必要があったり、上司や先輩への「報連相」が欠かせなかったりと、対応プロセス自体も複雑になりがちです。
クレーム対応代行サービスとは何か

ここまで、クレーム対応の難しさについてお話ししてきましたが、「もう、うんざりだ…」と感じている方もいるかもしれません。
そんな時に頼りになるのが、クレーム対応代行サービスです。
まずは、クレーム対応代行サービスとは具体的にどのようなものなのか、見ていきましょう。
サービスの基本的な仕組み
クレーム対応代行サービスとは、その名の通り、企業に代わってお客様からのクレーム対応業務を行ってくれるサービスです。
多くの場合、専門のトレーニングを受けたオペレーターが、電話やメール、チャットなど、様々なチャネルを通じてお客様からのクレームを受け付け、一次対応から解決に向けたサポートまでを行います。
企業側は、事前にサービス提供会社と対応範囲やルール、報告方法などを細かく取り決めておくことで、スムーズな連携が可能になります。
イメージとしては、自社に専門のクレーム対応部門を外部に持つような感覚に近いかもしれません。
どのような業務を代行してくれるのか
代行してくれる業務の範囲は、サービス提供会社や契約内容によって異なりますが、一般的には以下のような業務をカバーしています。
- 電話によるクレーム受付・対応: お客様からの電話を受け、内容をヒアリングし、初期対応を行います。
- メールによるクレーム受付・対応: クレームメールの内容を分析し、適切な返信文案の作成や送信を行います。
- チャットによるクレーム対応: Webサイト上のチャットシステムなどを通じて、リアルタイムでお客様の疑問や不満に対応します。
- 内容の記録と報告: 対応内容を詳細に記録し、企業側に定期的に報告します。
- エスカレーション対応: 専門的な判断が必要な場合や、解決が難しい複雑なクレームの場合、事前に定めたルールに従って企業側の担当者へ引き継ぎます。
これらの業務をプロに任せることで、自社の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
利用する企業の主な目的
企業がクレーム対応代行サービスを利用する目的は様々ですが、主に以下のようなものが挙げられます。
まず、最も大きな目的は、やはり従業員の負担軽減でしょう。
精神的にも時間的にも負荷の高いクレーム対応業務を外部に委託することで、従業員が本来の業務に集中できる環境を作ることができます。
次に、対応品質の向上も重要な目的です。
専門のトレーニングを受けたプロが対応することで、お客様に対してより的確で丁寧な対応が期待でき、顧客満足度の維持・向上に繋がります。
さらに、コスト削減を目的とする場合もあります。
自社でクレーム対応専門の人材を雇用・育成するコストや、対応にかかる時間的コストと比較して、代行サービスを利用する方が結果的に費用を抑えられるケースがあるのです。
また、24時間365日対応が必要なサービスを提供している企業にとっては、自社だけでは難しい広範な対応時間を確保できるという点も大きな魅力です。
クレーム対応代行サービス活用のメリット
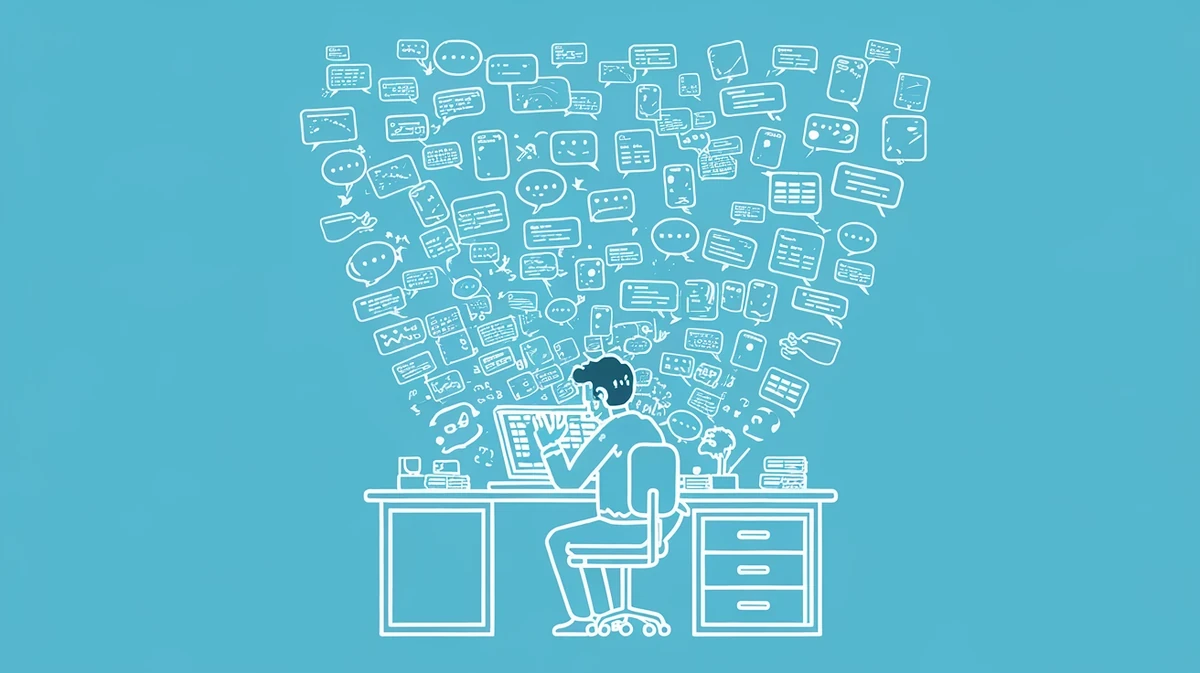
では、実際にクレーム対応代行サービスを活用すると、どのような具体的なメリットがあるのでしょうか。
精神的負担の軽減と従業員満足度の向上
クレーム対応の最前線に立つ従業員の精神的なストレスは、本当に深刻です。
代行サービスを利用することで、従業員が直接厳しい言葉にさらされる機会が減り、精神的な安定を保ちやすくなります。
「クレーム対応から解放された!」という安心感は、日々の業務へのモチベーションアップに繋がり、結果として従業員満足度の向上も期待できるでしょう。
働きがいのある職場環境を作る上で、非常に重要なポイントです。
コア業務への集中による生産性向上
クレーム対応に追われて、本来やるべき仕事がなかなか進まない…そんな経験はありませんか?
代行サービスにクレーム対応を任せることで、従業員はそれぞれの専門分野や主要な業務に集中できるようになります。
これにより、個々の生産性が向上するだけでなく、企業全体の業績アップにも繋がる可能性があります。
日本の企業が抱える「長時間労働」や「業務の属人化」といった課題の解決にも、一役買ってくれるかもしれません。
専門家による適切な対応で顧客満足度を維持・向上
クレーム対応は、一歩間違えれば顧客離れを引き起こしかねない、非常にデリケートな業務です。
代行サービスのスタッフは、クレーム対応に関する専門的な知識やスキル、豊富な経験を持っています。
そのため、感情的になっているお客様に対しても冷静かつ的確に対応し、問題を円満に解決へと導いてくれる可能性が高まるでしょう。
適切な対応は、逆に顧客の信頼を取り戻し、ファンになってもらうチャンスにもなり得ます。
コスト削減の可能性
「代行サービスって、費用が高いんじゃないの?」と不安に感じる方もいるでしょう。
しかし、長期的な視点で見ると、コスト削減に繋がるケースも少なくありません。
例えば、自社でクレーム対応専門のスタッフを雇用し、教育・研修を行うには相応の費用と時間がかかります。
また、クレーム対応によって他の業務が滞ることによる機会損失も考慮に入れる必要があります。
代行サービスを利用することで、これらのコストを圧縮できる可能性があります。
もちろん、サービス内容や料金体系は様々なので、自社の状況に合わせて比較検討することが大切です。
いわゆる「費用対効果」をしっかり見極めたいポイントです。
24時間365日対応可能な場合も
特に、オンラインショップや24時間営業のサービスを提供している企業にとって、夜間や休日のクレーム対応は大きな課題です。
自社で24時間体制を組むのは、人員的にもコスト的にも非常に難しいのが現実でしょう。
クレーム対応代行サービスの中には、24時間365日対応してくれるところもあります。
これにより、お客様はいつでも問い合わせができる安心感を得られ、企業側は対応漏れのリスクを減らすことができます。
顧客満足度向上にも繋がる、心強いサポートと言えるのではないでしょうか。
クレーム対応代行サービスの選び方

ここからはクレーム対応代行サービスを選ぶ際のポイントをいくつかご紹介します。
後悔しないためにも、ポイントをしっかりとおさえて慎重に選びましょう。
自社の課題とニーズを明確にする
まず最初にやるべきことは、自社がクレーム対応においてどのような課題を抱えていて、代行サービスに何を期待するのかを明確にすることです。
例えば、
- 特定の時間帯だけ対応が手薄になる
- 特定の製品に関する専門的なクレームが多い
- メール対応に時間がかかりすぎている
- クレーム対応による従業員の精神的負担が大きい
など、具体的な課題を洗い出しましょう。
そして、その課題を解決するために、どのようなサポートが必要なのか(例:電話対応のみ、メール対応も含む、24時間対応など)を整理します。
これが明確になっていないと、どのサービスが自社に合っているのか判断できません。
対応範囲と専門性の確認
次に、サービス提供会社がどのような範囲の業務に対応してくれるのか、そしてどの程度の専門性を持っているのかを確認しましょう。
- 電話、メール、チャットなど、対応可能なチャネルは何か?
- 一次対応のみなのか、ある程度の解決まで試みてくれるのか?
- 自社の業界や製品・サービスに関する知識や対応経験はあるか?
特に、専門的な知識が必要なクレームが多い場合は、その分野に強いサービス提供会社を選ぶことが重要です。
実績や事例などを参考に、しっかりと見極めましょう。
料金体系と契約期間の比較
料金体系は、サービス提供会社によって大きく異なります。
月額固定制、従量課金制(対応件数や時間に応じる)、成果報酬型など様々です。
自社のクレーム発生頻度や予算を考慮し、最適なプランを選びましょう。
初期費用やオプション料金の有無や、契約期間の縛りがあるかどうかも重要なチェックポイントです。
最初は短期間で試してみて、効果を実感できたら長期契約に切り替えるといった柔軟な対応ができるかどうかも確認しておくと安心です。
実績と評判のチェック
実際にそのサービスを利用した企業の事例や、口コミ、評判などをチェックすることも大切です。
サービス提供会社のウェブサイトに掲載されている導入事例だけでなく、可能であれば第三者の評価も参考にしましょう。
同業他社での実績があれば、より安心感が増します。
長年の実績がある会社は、それだけ多くの経験とノウハウを蓄積している可能性が高いと言えます。
「この会社なら任せられそう」という信頼感が持てるかどうか、しっかり見極めましょう。
セキュリティ体制と情報管理
クレーム対応では、お客様の個人情報や企業の機密情報を取り扱うことになります。
そのため、サービス提供会社のセキュリティ体制や情報管理の仕組みが万全であることは、絶対条件です。
プライバシーマークやISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証などを取得しているかどうかも、一つの判断基準になるでしょう。
情報の取り扱いに関する契約内容もしっかりと確認し、万が一の情報漏洩リスクに備えることが重要です。
安心して任せられる体制が整っているか、厳しくチェックしてください。
クレーム対応代行サービス導入の注意点
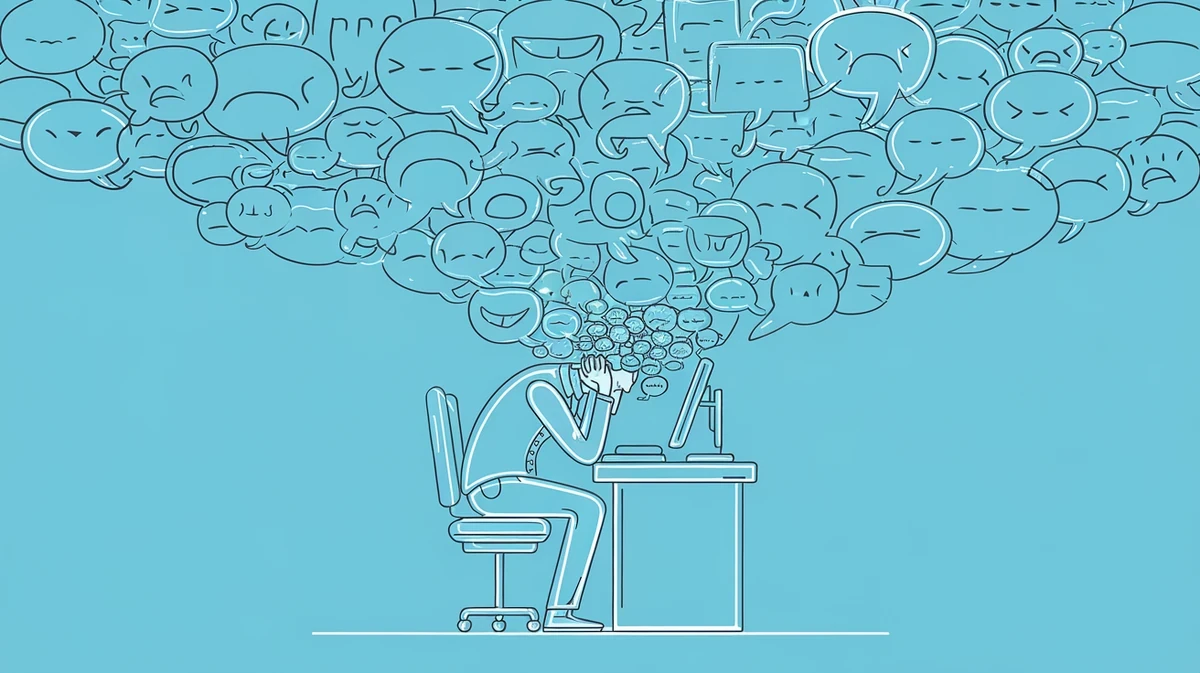
クレーム対応代行サービスは非常に便利ですが、導入する際にはいくつか注意しておきたい点があります。
丸投げにしない!社内連携の重要性
代行サービスを利用するからといって、クレーム対応を完全に「丸投げ」してしまうのは避けるべきです。
代行サービスはあくまで「代行」であり、最終的な責任は自社にあります。
サービス提供会社との間で、定期的な情報共有や報告の仕組みを確立し、どのようなクレームが発生し、どのように対応されているのかを社内でも把握しておくことが重要です。
また、代行サービスで対応しきれない複雑な案件や、経営判断が必要なクレームについては、スムーズに社内の担当者へエスカレーションできる体制を整えておく必要があります。
「代行会社任せで、社内では何も把握していない」という状況は避けましょう。
情報共有の仕組みづくり
代行サービス会社と自社との間で、円滑な情報共有は不可欠です。
クレームの内容、対応状況、顧客からのフィードバックなどを、リアルタイムに近い形で共有できる仕組みを作りましょう。
共有ツールを活用したり、定期的なミーティングを設けたりするのも効果的です。
特に、製品やサービスに関する重要な変更点や、新たなキャンペーン情報などは、速やかに代行サービス会社に伝える必要があります。
情報が不足していると、お客様に誤った案内をしてしまう恐れがあります。
「報連相」は、社内だけでなく、代行会社との間でも大切です。
自社ブランドイメージとの整合性
クレーム対応は、企業の顔としてお客様と接する重要な業務です。
代行サービスの対応が、自社のブランドイメージや企業理念と合致しているかどうかは、非常に重要なポイントです。
例えば、非常に丁寧で親身な対応をブランドイメージとしている企業が、あまりにも事務的で冷たい印象の対応をする代行サービスを選んでしまうと、顧客からの信頼を損ねる可能性があります。
サービス提供会社を選ぶ際には、対応のトーン&マナーや企業文化についても確認し、自社のブランドイメージを損なわないように注意しましょう。
サービス提供会社とのコミュニケーション
代行サービスを導入した後も、サービス提供会社との継続的なコミュニケーションは欠かせません。
定期的に対応状況のレビューを行い、改善点があれば率直に伝え、共に対応品質を高めていく姿勢が大切です。
問題が発生した場合には、迅速に連携を取り、解決に向けて協力し合う必要があります。
良好なパートナーシップを築くことが、代行サービス活用の成功に繋がると言えます。
お互いに信頼し合える関係を目指していきましょう。
クレーム対応の質をさらに高めるために

クレーム対応代行サービスを活用することは、大きな助けになります。
しかし、それに加えて、社内でも対応の質を高める努力を続けることが、顧客満足度向上や企業成長には不可欠です。
社内でのフィードバック体制の構築
代行サービスからの報告や、お客様の声を社内で共有し、そこから学びを得る体制を構築しましょう。
「どのようなクレームが多いのか」「お客様は何に困っているのか」を分析し、製品やサービスの改善に繋げることが重要です。
また、社内で対応したクレームについても、うまくいった点や改善すべき点をチームで共有し、ノウハウを蓄積していくことが大切です。
「あの時の対応は参考になったね」と、お互いに学び合える環境作りを心がけましょう。
クレームから学ぶ改善サイクルの確立
クレームは、企業にとって「改善のヒント」が詰まった貴重な情報源です。
受け取ったクレームをただ処理するだけでなく、その根本原因を分析し、再発防止策を講じる。
そして、その結果を検証し、さらに改善していくという「改善サイクル」を確立することが理想的です。
このサイクルを回し続けることで、製品やサービスの品質は継続的に向上し、結果としてクレームの発生自体を減らすことにも繋がるでしょう。
ピンチをチャンスに変える発想が大切です。
AIを活用した文章作成サポートの可能性
クレーム対応の中でも、特にメールでの返信は、言葉遣いや表現に細心の注意が必要で、時間も手間もかかるものです。
「この言い方で失礼にならないだろうか…」「もっと早く返信できれば…」と悩むことも多いのではないでしょうか。
そんな悩みを解決するのが、『代筆さん』です。
『代筆さん』は、簡単な指示や要件を伝えるだけで、AIがビジネスメールを作成してくれるWebサービスです。
例えば、お客様からのクレームメールの内容と、伝えたい要点を入力するだけで、丁寧で適切な返信文案をAIが提案してくれます。
日本語で指示しても、相手が海外の方であれば、その言語に合わせたメールを作成することも可能です。
よくあるクレームへの初期対応文面などは、指示を保存しておくことで、次回から瞬時に作成できるので、カスタマーサポート部門などでは特に業務効率が向上します。
人が操作するので、24時間完全自動対応は難しいかもしれませんが、日々のメール作成業務の負担を大幅に軽減し、より迅速で質の高いコミュニケーションを実現するお手伝いができます。
もちろん、最終的な確認は人の目で行うことが大切ですが、文章作成の時間を短縮できれば、その分、他の重要な業務に集中できるでしょう。
まとめ:クレームを成長の機会に変えるために

クレーム対応は、確かに精神的にも時間的にも大きな負担を伴う業務です。
しかし、お客様の声を真摯に受け止め、適切に対応することは、企業の信頼を守り、さらには成長の機会へと繋げるための重要なステップと言えます。
少子高齢化による人手不足や、働き方改革による業務効率化の必要性が叫ばれる現代において、クレーム対応代行サービスは、従業員の負担を軽減し、企業がコア業務に集中するための有効な選択肢の一つです。
自社の課題やニーズをしっかりと見極め、最適なサービスを選ぶことができれば、その導入効果は大きいでしょう。
そして、日々のメール対応においては、例えば『代筆さん』のようなAIを活用した文章作成支援ツールを試してみるのも、業務効率化の一つの方法です。
簡単な指示でビジネスメールを作成できるので、クレームへの返信メール作成にかかる時間や精神的な負担を軽減できるかもしれません。
あなたも、クレーム対応の悩みを少しでも減らし、より前向きに業務に取り組める環境づくりを目指してみませんか?




