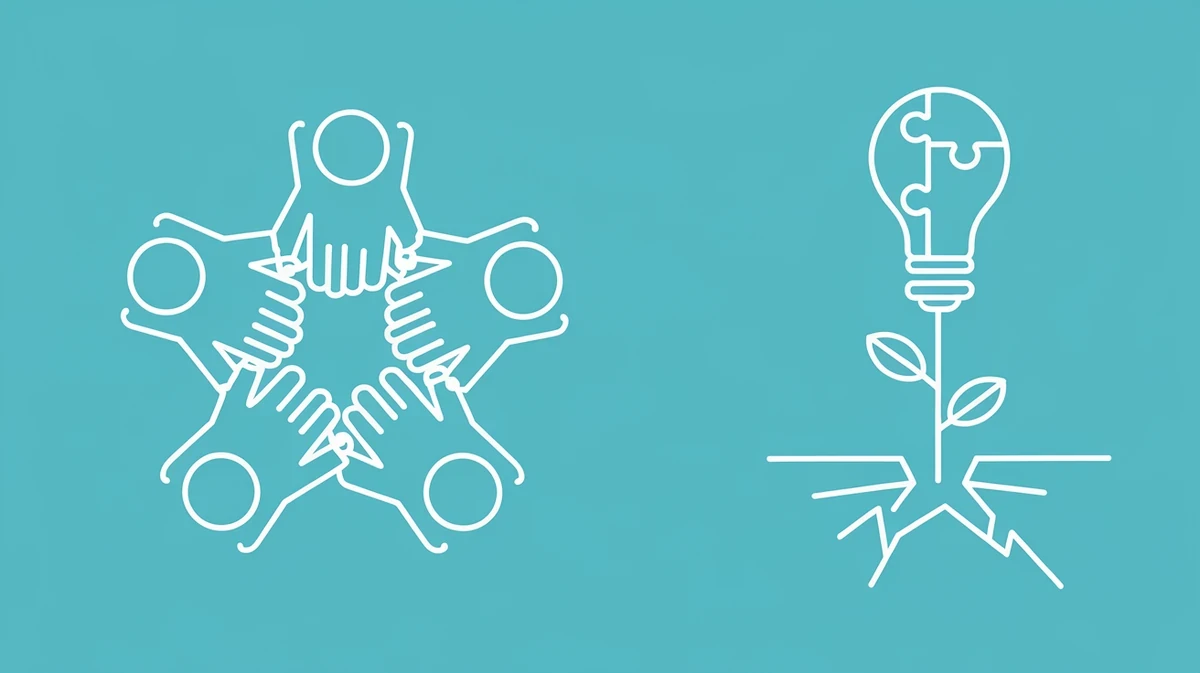ビジネスを脅かすフィッシングメールの見分け方と対策5選
フィッシングメールに注意

「怪しいメールが届いたけど、これってフィッシング…?」
ビジネスシーンで、そう感じた経験はありませんか?
巧妙化するフィッシングメールは、今や企業にとって無視できない脅威です。
ひとたび被害に遭えば、金銭的な損失だけでなく、顧客からの信頼失墜、機密情報の漏洩など、ビジネスに深刻な影響を及ぼしかねません。
本記事では、そんなフィッシングメールの脅威と、具体的な対策について解説します。
この記事を読めば、フィッシングメールの脅威を正しく理解し、適切な対策を講じることで、あなたのビジネスを守ることができるでしょう。
巧妙化するフィッシングメールの脅威とビジネスへの影響

近年のフィッシングメールは、手口が巧妙化しており、一見しただけでは本物と見分けがつかないケースが増えています。
かつては、不自然な日本語や機械的な文章が特徴でしたが、最近では、実在する企業やサービスを装い、正規のメールと区別がつかないほど精巧なものが多くなっています。
ビジネスメール詐欺の深刻な被害事例
フィッシングメールによる被害は、個人だけでなく、企業にとっても深刻です。
ここでは、ビジネスメール詐欺(BEC)の代表的な被害事例をいくつかご紹介します。
事例1:取引先になりすましたメールによる金銭被害
ある企業に、取引先を装ったメールが届きました。
メールには、「請求書の支払先口座が変更になった」と記載されており、担当者は疑うことなく指定された口座に数百万円を振り込んでしまいました。
しかし、これは巧妙に偽装されたフィッシングメールであり、振り込んだお金は詐欺犯の手に渡ってしまいました。
事例2:社内システムへの不正アクセスによる情報漏洩
ある企業の従業員に、社内システム管理者になりすましたメールが届きました。
メールには、「システムメンテナンスのため、パスワードを更新してください」と記載されており、URLリンクが添付されていました。
従業員がリンクをクリックし、偽のログインページにパスワードを入力してしまった結果、社内システムに不正アクセスされ、顧客情報が漏洩してしまいました。
事例3:ランサムウェア感染による業務停止
ある企業の従業員に、添付ファイル付きのメールが届きました。
メールの件名や本文は業務に関係する内容であり、従業員は不審に思わず添付ファイルを開いてしまいました。
しかし、このファイルはランサムウェアであり、社内ネットワーク全体が感染し、業務が数日間にわたって停止してしまいました。
これらの事例は、フィッシングメールがいかに巧妙で、ビジネスに深刻な影響を与えるかを示しています。
被害に遭わないためには、メールの真偽を見極める力と、適切な対策が不可欠です。
標的型攻撃メールとなりすましメールの違い
フィッシングメールには、大きく分けて「標的型攻撃メール」と「なりすましメール」の2種類があります。
それぞれの特徴と違いを理解しておきましょう。
標的型攻撃メール
特定の企業や組織、個人をターゲットにしたフィッシングメールです。
事前にターゲットの情報を収集し、関係者を装ったり、業務に関係する内容を装ったりすることで、受信者を信用させ、不正な操作をさせようとします。
標的型攻撃メールの特徴
- 特定のターゲットに合わせた内容
- 関係者を装う
- 業務に関係する内容を装う
- 巧妙な日本語や自然な文章
- 添付ファイルやURLリンクを含むことが多い
なりすましメール
実在する企業やサービス、個人になりすましたフィッシングメールです。
不特定多数に大量に送信され、正規のメールと誤認させ、個人情報や金銭をだまし取ろうとします。
なりすましメールの特徴
- 実在する企業やサービス、個人になりすます
- 不特定多数に大量送信
- 一般的な内容(例:パスワードの変更、アカウントの確認)
- 不自然な日本語や誤字脱字が見られる場合もある
- URLリンクを含むことが多い
標的型攻撃メールは、特定のターゲットに特化しているため、より巧妙で、見分けるのが難しい傾向があります。
一方、なりすましメールは、不特定多数に送信されるため、比較的見分けやすい場合もありますが、最近では巧妙化が進んでいます。
どちらのタイプのメールも、注意深く確認し、不審な点があれば、安易にURLリンクをクリックしたり、添付ファイルを開いたりしないことが重要です。
怪しい?フィッシングメールを見分ける7つのチェックポイント

フィッシングメールは、巧妙化の一途をたどり、一見しただけでは本物と区別がつかないケースも増えています。
しかし、注意深く観察することで、フィッシングメールに隠された罠を見抜くことができます。
ここでは、ビジネスシーンで特に注意すべき、フィッシングメールを見分けるための7つのチェックポイントを解説します。
これらのポイントを意識することで、フィッシング詐欺のリスクを大幅に軽減できるでしょう。
送信元アドレスの確認 本当に信頼できる?
まず確認すべきは、送信元メールアドレスです。
表示されている名前だけでなく、メールアドレス自体を必ず確認しましょう。
公式ドメインとの一致
企業やサービスからのメールは、通常、公式ドメインのメールアドレスを使用します。
例えば、@example.com のような形式です。
フリーメールアドレスの悪用
@gmail.com や @yahoo.co.jp などのフリーメールアドレスは、なりすましに悪用されやすいため、注意が必要です。
スペルミスの確認
一見すると正規のドメインに見えても、よく見ると1文字違う、といったケースがあります。
例えば、examp1e.com (lが1になっている) のように、巧妙に偽装されている場合があります。
不自然な日本語表現や誤字脱字に注意
フィッシングメールは、海外の攻撃者によって作成されることが多いため、日本語の表現が不自然であったり、誤字脱字が多かったりする傾向があります。
機械翻訳のような文章
不自然な敬語や、直訳調の表現が見られる場合は、注意が必要です。
明らかな誤字脱字
日本語として意味が通じない、誤字や脱字が目立つ場合も、フィッシングメールの可能性が高いです。
例文:不自然な日本語表現
件名:[銀行名]からのお知らせ
[宛先]様
あなたのアカウントは、異常な活動のために一時的に停止されました。
下記のリンクをクリックして、アカウントを再アクティブ化してください。
[URL]
敬具
この例文では、「再アクティブ化」という不自然な表現が使われています。
URLリンクの確認 偽サイトへの誘導を見抜く
フィッシングメールの多くは、偽のウェブサイトに誘導し、IDやパスワード、クレジットカード情報などを盗み取ろうとします。
メール内のURLリンクは、安易にクリックせず、必ず確認しましょう。
リンク先のURLをプレビュー
リンクにマウスカーソルを合わせる(クリックはしない)と、リンク先のURLが表示されます。
正規のURLとの比較
表示されたURLが、正規のウェブサイトのURLと一致するか確認します。
短縮URLの利用
bit.ly などの短縮URLは、リンク先が分かりにくいため、注意が必要です。
例文:偽サイトへの誘導
件名:[サービス名] ご利用料金のお支払いについて
[宛先]様
いつも[サービス名]をご利用いただきありがとうございます。
ご登録のクレジットカードの有効期限が切れているため、お支払いができませんでした。
以下のリンクから、新しいクレジットカード情報をご登録ください。
[偽URL]
今後とも[サービス名]をよろしくお願いいたします。
このメールは、クレジットカード情報の更新を促していますが、リンク先のURLが正規のサービスとは異なる偽サイトになっています。
添付ファイルの確認 不用意に開かない
フィッシングメールには、マルウェア(ウイルス)が仕込まれた添付ファイルが添付されていることがあります。
不審なメールの添付ファイルは、絶対に開かないようにしましょう。
拡張子の確認
.exe .zip .doc .xls などの拡張子は、特に注意が必要です。
ファイル名
ファイル名が文字化けしていたり、意味不明な文字列だったりする場合は、警戒が必要です。
マクロの有効化
WordやExcelファイルを開いた際に、「マクロを有効にしますか?」というメッセージが表示された場合は、特に注意が必要です。
例文:不審な添付ファイル
件名:請求書 [請求書番号]
[宛先]様
いつもお世話になっております。
[請求書番号]の請求書を添付いたしましたので、ご確認ください。
[添付ファイル名].zip
よろしくお願いいたします。
このメールは、請求書を装っていますが、添付ファイルがZIP形式で圧縮されており、不審です。
通常、請求書はPDFのような、そのまま開ける形式で送られてきます。
業務上、ZIP形式のファイルを受け取る習慣がない場合は、特に注意が必要です。
個人情報やパスワードを尋ねる内容に警戒
正規の企業やサービスが、メールで個人情報やパスワードを尋ねることは、通常ありません。
メールでこれらの情報を要求された場合は、フィッシングメールを疑いましょう。
パスワードの入力要求
メール内のリンクから、パスワードの入力を求められた場合は、特に注意が必要です。
クレジットカード情報の入力要求
クレジットカード番号や有効期限、セキュリティコードなどを、メールで尋ねることはありません。
個人情報の確認
住所、氏名、電話番号などの個人情報を、メールで確認することも通常ありません。
例文:個人情報を尋ねる
件名:【重要】[サービス名] アカウント情報確認のお願い
[宛先]様
お客様のアカウント情報に誤りがある可能性がございます。
以下のリンクから、アカウント情報をご確認ください。
[偽URL]
ご協力をお願いいたします。
このメールは、アカウント情報の確認を装い、偽サイトに誘導して個人情報を入力させようとしています。
緊急性を煽る文面に注意
フィッシングメールは、「アカウントがロックされます」「支払いが確認できません」など、緊急性を煽る文面で、受信者を焦らせ、冷静な判断を奪おうとします。
時間制限
「24時間以内に対応しないと…」など、時間制限を設けている場合は、注意が必要です。
脅迫的な文言
「法的措置を取ります」など、脅迫的な文言が使われている場合は、フィッシングメールの可能性が高いです。
例文:緊急性を煽る
件名:【緊急】[サービス名] アカウント停止のお知らせ
[宛先]様
お客様のアカウントに不正アクセスがありました。
24時間以内に以下のリンクからパスワードを変更しない場合、アカウントを停止させていただきます。
[偽URL]
ご理解とご協力をお願いいたします。
このメールは、アカウント停止をちらつかせ、緊急性を煽って偽サイトに誘導しようとしています。
公式情報との照合
少しでも不審に感じたら、メールに記載されている企業やサービスの公式サイトや、公式の連絡先に問い合わせて、事実確認を行いましょう。
公式サイトの確認
メールに記載されているURLではなく、自分で検索して公式サイトにアクセスし、情報を確認します。
公式連絡先への問い合わせ
公式サイトに記載されている電話番号やメールアドレスに、直接問い合わせて確認します。
これらのチェックポイントを総合的に判断し、少しでも不審な点があれば、安易にメール内のリンクをクリックしたり、添付ファイルを開いたりせず、慎重に対応することが重要です。
次のセクションでは、これらの見分け方を踏まえ、ビジネスで実践すべき具体的なフィッシングメール対策について解説します。
ビジネスで実践すべきフィッシングメール対策5選

フィッシングメールの巧妙な手口を見破るためのチェックポイントを理解したところで、次は、ビジネスの現場で実践すべき具体的な対策について解説していきます。
どんなに注意深くても、人間はミスを犯す可能性があります。
システムと人、両面からの対策で、フィッシングメールのリスクを最小限に抑えましょう。
メールセキュリティ対策ソフトの導入
まず検討したいのが、メールセキュリティ対策ソフトの導入です。
これらのソフトは、スパムメールやフィッシングメールを自動的に検出し、隔離または削除してくれます。
メールセキュリティ対策ソフトの主な機能
- 迷惑メールフィルタリング
- URLフィルタリング (不正なURLへのアクセスをブロック)
- 添付ファイルのスキャン (マルウェアの検知)
- サンドボックス (不審なファイルを隔離された環境で実行し、安全性を確認)
多くの製品が存在するため、自社の環境やニーズに合ったものを選ぶことが重要です。
多要素認証の導入で不正ログインを防ぐ
IDとパスワードによる認証だけでなく、スマートフォンアプリによる認証や生体認証など、複数の認証要素を組み合わせる「多要素認証(MFA)」を導入しましょう。
これにより、万が一パスワードが漏洩した場合でも、不正ログインを防ぐことができます。
多要素認証の例
- パスワード + スマートフォンへのワンタイムパスワード送信
- パスワード + 指紋認証
- パスワード + 顔認証
特に、クラウドサービスやリモートアクセスを利用している場合は、多要素認証の導入を強く推奨します。
従業員へのフィッシングメール対策訓練の実施
どんなに優れたセキュリティシステムを導入しても、従業員がフィッシングメールに騙されてしまっては意味がありません。
定期的な訓練を実施し、従業員のセキュリティ意識を高めることが重要です。
訓練内容の例
- フィッシングメールの見分け方に関する講習
- 模擬フィッシングメールを使った実践的な訓練
- 最新の攻撃手口に関する情報共有
例文:訓練メールの例
件名:【重要】パスワード再設定のお願い
〇〇株式会社の皆様
いつもお世話になっております。
システム管理者です。
セキュリティ強化のため、全従業員のパスワード再設定をお願いしております。
以下のURLから新しいパスワードを設定してください。
[偽のURL]
ご協力よろしくお願いいたします。
この例文は、件名や本文で緊急性を煽り、偽のURLへ誘導する典型的なフィッシングメールです。
訓練では、このようなメールに騙されないよう、注意点などを解説します。
不審なメールの報告体制と対処法の確立
従業員が不審なメールを受信した場合、速やかに情報システム部門やセキュリティ担当者に報告できる体制を整えましょう。
報告されたメールを分析し、適切な対処を行うことで、被害の拡大を防ぐことができます。
報告体制のポイント
- 報告窓口の明確化 (メールアドレス、内線番号など)
- 報告手順の簡素化 (テンプレートの用意など)
- 報告者へのフィードバック (対応状況の共有)
OSやソフトウェアを常に最新の状態に保つ
OSやソフトウェアの脆弱性を悪用した攻撃も、フィッシングメールと並んで深刻な脅威です。
常に最新のバージョンにアップデートし、セキュリティパッチを適用することで、攻撃のリスクを低減できます。
確認すべきポイント
- OS (Windows, macOS, Linuxなど)
- Webブラウザ (Chrome, Firefox, Edgeなど)
- メールソフト (Outlook, Thunderbirdなど)
- その他利用しているソフトウェア
これらの対策を総合的に実施することで、フィッシングメールによる被害を大幅に減らすことができます。
しかし、万が一、被害に遭ってしまった場合はどうすればよいのでしょうか?
次の章では、被害発生時の対処法について解説します。
もし被害に遭ってしまったら?冷静な対処と報告

万全の対策を講じていても、フィッシングメールの被害に遭ってしまう可能性はゼロではありません。
ここでは、被害に気づいた際に、冷静に対処し、被害を最小限に抑えるための方法を解説します。
パスワードの変更とアカウントの保護
フィッシングサイトにパスワードを入力してしまった、または不審な添付ファイルを開いてしまった場合は、直ちにパスワードを変更しましょう。
同じパスワードを使い回している場合は、他のサービスのアカウントも同様に変更が必要です。
変更対象
- フィッシングメールに関連するアカウント
- 同じパスワードを使用している全てのアカウント
パスワードのポイント
- 推測されにくい、複雑なパスワードを設定する
- パスワードマネージャーを活用する
関係各所への迅速な報告
被害状況を正確に把握し、二次被害を防ぐためには、迅速な報告が不可欠です。
社内
- 情報システム部門、セキュリティ担当者、上長へ報告
- 社内規定に従い、インシデント対応チームへ連絡
社外
- 取引先、顧客など、影響が及ぶ可能性がある関係者へ連絡
- 状況に応じて、顧問弁護士へ相談
例文:社内報告メール
件名:【至急】フィッシングメール被害に関するご報告
情報システム部 [担当者名]様
お疲れ様です。[部署名]の[氏名]です。
本日[日時]頃、[概要]と思われるフィッシングメールを受信し、[被害状況]が発生いたしました。
指示に従い、パスワードは変更済みです。
今後の対応について、ご指示いただけますようお願いいたします。
この例文は、社内の情報システム部やセキュリティ担当者への報告を想定しています。
状況に応じて、件名や本文を調整してください。
被害状況の確認と証拠の保全
冷静に、以下の情報を確認・記録しましょう。
確認事項
- いつ、どのようなメールを受信したか
- どのような操作を行ったか(URLクリック、添付ファイル開封、情報入力など)
- どのような情報が漏洩した可能性があるか(パスワード、個人情報、機密情報など)
- 他に影響を受けたシステムやアカウントはないか
証拠保全する内容
- フィッシングメールの保存(削除しない)
- アクセスログの確認
- スクリーンショットの取得
これらの情報は、後の調査や警察への届け出の際に役立ちます。
警察や専門機関への相談
被害状況によっては、警察や専門機関への相談も検討しましょう。
相談先の例
- 警察庁Webサイト: 各都道府県警察の相談窓口
- 情報処理推進機構(IPA): 情報セキュリティに関する相談窓口
- JPCERT/CC: インシデント対応の支援
相談内容の例
- 被害状況の説明
- 今後の対応に関するアドバイス
- 必要に応じて、被害届の提出
これらの機関は、専門的な知識や技術で、問題解決をサポートしてくれます。
被害に遭った際は、焦らず、冷静に、上記の手順で対処しましょう。
そして、今回の経験を教訓に、より強固なセキュリティ対策を講じることが重要です。
最後に、ここまでの対策のまとめを見ていきましょう。
フィッシングメール対策でビジネスを守る まとめ

ここまでの内容を振り返り、重要なポイントをまとめます。
- 怪しいメールは徹底的に確認
- セキュリティ対策は多層的に実施
- 被害に遭っても冷静に対処
まずは、普段から訓練メールなどを活用し、不審なメールに気づけるよう意識を高めておくことをおすすめします。
そして、万が一、被害に遭ってしまった場合に備え、社内での報告体制を整えておくことも重要です。
日々の少しの注意と対策が、あなたのビジネスを脅威から守ります。
共に協力し、安全なデジタル環境を築いていきましょう。